令和6年司法試験民事訴訟法の優秀答案とは?(論文50位代合格・評価A)
2025年4月18日
司法試験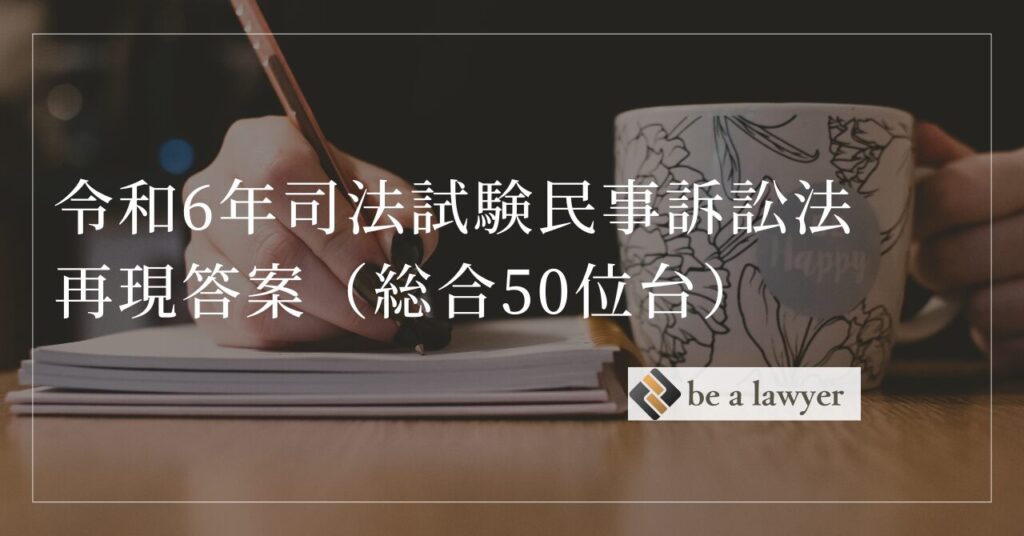
第一 設問1課題1
任意的訴訟担当とは、訴訟物である権利義務の本来の主体の意思に基づいて訴訟追行権を授権された訴訟担当者が、当事者として訴訟を追行することをいう。
任意的訴訟担当は本来の権利義務主体とは異なる者が訴訟追行することを可能にするため、これによって弁護士代理の原則(民事訴訟法(以下法名略)54条)や訴訟信託の禁止(信託法10条)の規律を損なう可能性がある。そのため、任意的訴訟担当を認めるための合理的必要性があり、認めても右規律を回避、潜脱するおそれがない場合に認められると解する。
第二 設問1課題2
今回は、賃貸借契約において共同賃貸人であるX1からX3は賃借人のYに訴訟提起しようとしているところ、そのうちX1が賃貸人側の任意的訴訟担当者となれるかが問題となっている。
XらはAの権利義務を共に相続した相続人同士という関係性であり、業務上の多数人の集まりで任意的訴訟担当を認めた判例の状況と異なる。もっとも、Xらは本件契約の更新、賃料の徴収及び受領、本件建物の明渡しに関する訴訟上あるいは訴訟外の業務についてはX1が自己の名で行うことが取り決められていた。このように訴訟だけでなく実体上の業務執行権が与えられていたことは判例の状況と同じである。そもそも上記規律を回避、潜脱するおそれがないと言えるために一番重要なことは担当者によって他の権利義務者の権利義務が不当に損なわれるかであり、そのためには担当者が日頃から実体上の権利執行者であったかや権利義務の内容について理解しているかが検討されるべきである。そのため、判例とは異なる相続人間という関係性で少ない人数であったとしても、それらの事情によって上記規律を回避、潜脱するおそれがあるとは言えない。また、今回X2とX3は当事者になることによって時間的・経済的負担が大きいことを理由にX1が訴訟担当者になることを求めている。時間的理由については原則通り弁護士に委任することも考えられるが、弁護士に委任する場合は費用負担を強いられるため、すでに実体上の管理代表者がいる場合にはその者に任せた方が時間的、経済的に負担も少なく迅速である。そのため、合理的必要性も認められる。
したがって、X1による訴訟担当は認められる。
第三 設問2
1 裁判上の自白(179条)とは、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の、弁論期日における弁論としての陳述である。
「自己に不利益な事実」とは、相手が立証責任を負う訴訟物についての主要事実をいう。なぜなら、弁論主義(事実や証拠の収集及び提出を当事者の権能かつ責任とする建前)の自白原則により裁判所は自白のあった事実を判決の基礎としなければならないところ、審理の弾力化のために主要事実に限る方が合理的かつ明確であるからである。そして、民事訴訟は実体法上の権利の実現手段であり、その立証責任は自己に有利な効果を定めた実体法上の要件事実を主張すべきかによって決められる。
2 本件陳述に裁判上の自白が成立するか。
本件陳述は、「令和3年10月以降、自分の妻が、本件建物において何回か料理教室を無償で開いたことがあった。X1は夫婦でその料理教室に毎回参加していたが、賃料の話など一切出なかった。」旨のものであり、料理教室を開いたことは、本件契約における居住用に使用するという特約に反し、賃借人の用法遵守義務(民法616条、594条1項)に違反することを指している。そして、用法遵守義務違反は、賃貸借契約の解除事由(民法594条3項、542条)となるものであり、解除を主張する賃貸人が立証責任を負う。そうすると、Yの、本件建物で料理教室を開催したという陳述は、自己に不利益な陳述となる。また、これは第一回弁論準備手続期日にされているため、弁論期日になされている。
そのため、本件陳述に裁判上の自白が成立する
3 上記自白の撤回は許されるか。
裁判上の自白は、前述の通り裁判所に対して審判排除効果を及ぼし、当事者間でも不要証効果があるため、自白がなされるとそれが判決の基礎になるという相手方の信頼が生じる。そのため、自白の撤回が行われると右信頼を損なうこととなり、信義則に反する。そこで、裁判上の自白の撤回は原則禁止される。したがって、このような信頼を損なわないと評価できる場合には例外として撤回を許容すべきである。
今回本件陳述は弁論準備手続上で行われているところ、この手続は、賃料不払による無催告解除の可否に関して当事者間の信頼関係の破壊を基礎付ける事実関係の存否につき、当事者双方が口頭で自由に議論するという目的で行われており、裁判所及び当事者間で用法遵守義務を解除事由とするケースについては想定されていなかった。そして、本件陳述は、賃借人のYが、自身に賃料未払いがなかったことを主張する意思で発言されたものである。そのため、Yは本件陳述が自身の用法遵守義務違反に当たり自白になることを意識しないままに発言してしまったといえ、このような発言につき裁判上の自白になることについて、相手型の信頼が生じる事情ではない。にもかかわらず、Xらはこれを幾何として裁判上の自白として援用し、新たな解除事由を主張しており、このような揚げ足取りの形となる援用を撤回してもXらの信頼を害すると言えない。
したがって、本件陳述による裁判上の自白を撤回は許容される。
第四 設問3
1 既判力(114条1項)は、確定判決の判断に与えられる通用性ないし拘束力を指し、前訴訴訟物と先決・矛盾・同一関係にある後訴について、前訴訴訟物の存否を前提とし(積極的作用)、矛盾する主張や証拠を排斥する(消極的作用または遮断効)という作用をもつ。これによって確定判決の判断を後から別の訴訟で蒸し返されることを防いで相手方や裁判所の二重の負担を避けることが趣旨である。そして、既判力の発生根拠は、前訴の事実審口頭弁論集結時まで当事者は主張及び証拠の提出が可能であった(民事執行法35条2項)という手続的保障が与えられていたことにある。そのため、前訴の事実審口頭弁論集結時を時的限界とし、それまでに生じた事由に上記作用が及ぶと考える。したがって、右基準時前の事由に関する主張で前訴訴訟物に矛盾する主張が遮断される。
2 そして、今回本件判決の訴訟物は賃貸借契約解除に基づく明渡請求権で、Xらが提起しようとしているのも同じ訴訟物であるから、本件判決の既判力が作用する関係にある。また、XらはYが本件建物で本件セミナーを行なっていたことを解除事由に当たることを主張しようとしているところ、本件判決の事実審口頭弁論集結時は令和5年4月で、本件セミナーの開催は令和3年1月から令和5年1月までの間であり、基準時前の事情である。そうすると、基準時前に本件契約の解除事由があったというXらの上記主張は、本件契約の解除事由がなかったという本件判決の判断と矛盾し、遮断されるとも思える。
これに対し、同じ解除事由であっても本件判決と今回とでは用法遵守義務違反の内容が異なっており、本件セミナー開催という用法遵守義務違反行為について本件判決の確定後に判明しているのだから、この主張を遮断することはXらに対して不都合であり、遮断効を及ぼすべきでないという主張が考えられる。確かに、既判力の発生根拠は前訴で主張や証拠提出について手続保障が与えられていたことであり、前訴で発覚していなかった解除事由については主張の期待可能性がなかったとも言える。しかしながら、この手続保障は前訴において紛争を解決するための主張証拠の調査を尽くすことに対しても敷かれているものであり、遮断効に例外を認めることは慎重に考えるべきである。そこで、不当に調査の機会が害されていたというような明確な特殊事情がない限りは、調査ができなかったことにつき責任を負うべきである。そして、今回Xらが本件セミナーについて本件判決の基準時までに知ることができなかったという特殊事情は見られず、むしろ、本件セミナーの開催は令和3年1月から令和5年1月までと長期間にわたって行われていたのであり、本件判決中にその調査を行うことは可能であったと考えられる。そうすると、Xらの本件セミナーについての主張は原則遮断されるべきである。
以上より、本件判決の既判力によって解除権行使の主張を遮断することは相当である。
以上

