令和6年司法試験刑法の優秀答案とは?(論文50位代合格・評価A)
2025年4月19日
司法試験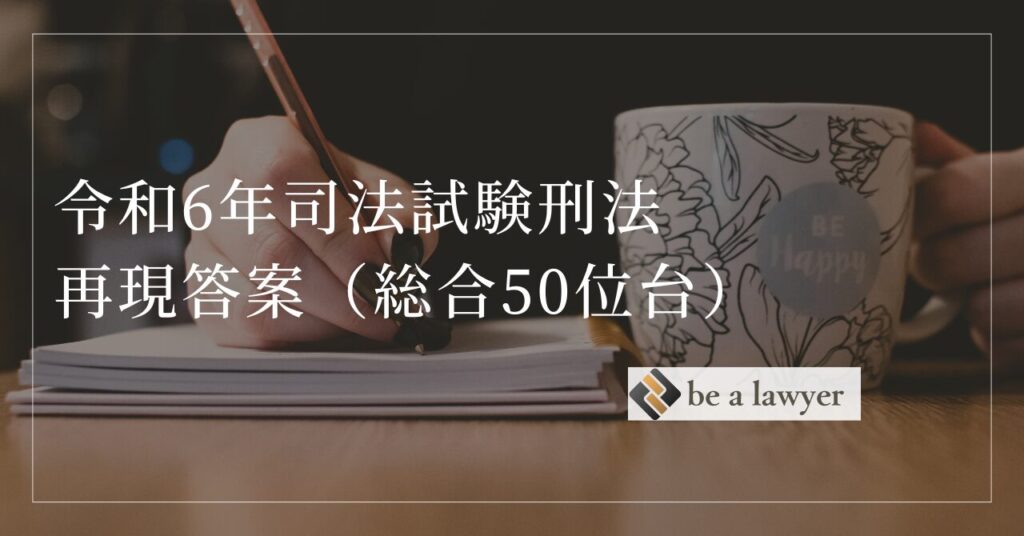
第一 設問1甲の罪責
1 甲は腹部を繰り返し蹴るという暴行を行なって、Aに肋骨骨折等の傷害を負わせているから、この行為に傷害罪(刑法(以下法名略)204条)が成立する。
2 甲が、本件財布を自身のポケットに入れた行為に強盗罪(236条1項)が成立するか。甲は上記暴行後に本件財布をとっているため、問題となる。
この点、強盗罪の「暴行または脅迫」とは相手方の反抗を抑圧する程度のものであるが、これは財物奪取に向けられていることが必要であり、上記暴行時に甲は本件財布の存在を知っているため、「暴行または脅迫」とは言えない。しかし、暴行後に財物を奪取した場合には先行して相手方の反抗抑圧状態が出来上がっていたと言えるなら、それを維持・継続する行為があれば「暴行または脅迫」があったと評価する。そして、甲の暴行はAに執拗に暴力を振るって生命の危機になりかねない重大な怪我を負わせるもので、その際に反抗抑圧状態が出来上がっていたと言える。このようにAが甲に抵抗できない状態であることを認識しながらAに対して「財布をもらっておく」と述べる行為は財布を素直に差し出さないとまた暴行される危険性があると示すことと同等と評価でき、「脅迫」と言える。また、本件財布は「他人の財物」で、ポケットに入れる行為は「強取」であり、甲には故意(38条1項)があったと言える。
そのため、甲の上記行為は強盗罪となる。
3 よって、上記各行為について甲には傷害罪と強盗罪が成立し、両者は併合罪(45条)となる。
第二 設問1乙の罪責
1 乙は、バタフライナイフの刃先をAの眼前に示しながら本件財布に入っていた本件カードの暗証番号を聞き出そうとしているが、この行為に強盗罪(刑法236条2項)が成立するか。
まず、バタフライナイフの刃先を眼前に示す行為は相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫行為と言えるところ。そして、これによって聞き出そうとしている本件カードの暗証番号は「財産上不法の利益」といえるかが問題となるところ、本件カードはキャッシュカードであり、このようなカードは暗証番号を入力することでATMから金銭を引き出すことができる。そうすると、本件カードの暗証番号を聞くことは、本件カードを使ってATMからAの預金を引き出すことができる地位という財産的な利益を得ることにつながる。また、乙には故意も認められる。
しかしながら、今回Aが乙に伝えたのは間違った暗証番号であり、これでは本件カードを使ってATMからAの預金を引き出すことができる地位を得られないのであるから、強盗は未遂(243条)となる。
よって、強盗罪の未遂が成立する。
2 乙は本件カードをATMに挿入して間違った暗証番号を入力しているところ、不正な操作として取引が停止されて預金を引き出すことができなかった。このうち、暗証番号の入力行為が窃盗罪(235条)に当たらないか。
ATMから不正に預金を引き出す行為は、その預金の占有者である銀行に対する窃盗罪となる。そのため、乙がAの意思に反して本件カードをATMに入れて暗証番号を入力する行為は窃盗罪の実行行為に着手していると思える。しかし、乙がATMに入力した暗証番号は間違ったものであり、客観的に預金を引き出すことはできなかったのであるから、構成要件的結果発生の現実的危険性がなかったとして不能犯となり、そもそも不可罰になるとも思える。
上記の通り実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるところ、これにあたるかは、行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を判断の基礎とし、一般人の立場から危険性があるかによって判断する。そして、乙も一般人も、Aから聞き出した番号を本件カードの暗証番号として認識していたのであり、一般人の立場からすれば本件カードとこの番号をATMに入力することは預金を窃取する危険性があると言える。
また、乙にはAの預金を窃取する故意があったと言えるが、取引停止により実際に預金を窃取することはできなかった。
よって、窃盗罪の未遂が成立する。
3 以上より、乙には強盗罪の未遂と窃盗罪の未遂が成立し、両者は併合罪となる。
第三 設問2(1)
丙の1回目殴打及び2回目殴打はどちらも殴打という暴行(208条)と言えるところ(後述のように甲との間で共同正犯となる)、これらの行為に正当防衛(36条1項)が成立するか。
1 正当防衛の要件は、「急迫不正の侵害に対して」「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずに」行ったことである。
1回目殴打については、Cが丙に対して殴りかかろうとしているから急迫不正の侵害が認められ、自身や一緒にいた甲の身を守るために行っている。そして、Cと性別や年齢のそうかわらない丙が拳で殴ってくるCに対して同じく拳で1回のみ殴った行為は相当な防衛行為としてやむを得ない。
2回目殴打についても、1回目殴打と同じようにCが丙に対して殴りかかろうとしており、丙は自身や甲の身を守るために1回目殴打と同様の防衛行為をしているから、上記要件を満たす。
2 したがって、丙の1回目殴打及び2回目殴打には正当防衛が成立し、違法性が阻却されるため不可罰になる。
第四 設問2(2)丁の罪責
丁は丙に対して「頑張れ。ここで待っているから終わったらこっちに来い。」と声をかけ、丙がCに2回目殴打を行った後に本件バイクの後部座席に丙を乗せてその場から立ち去っている。この行為は、丁が丙の2回目殴打を容易にするものとして、暴行罪の幇助犯(62条1項)になると思える。
幇助とは物理的・心理的に実行行為者に働きかけて正犯の行為を容易にすることいい、今回丁は丙がCを殴るのを応援する声かけをし、その後丙が本件バイクに乗って逃げられるように待機していることを示唆している。そうすると、丁の声かけは丙の暴行を容易くするもので、実際に丙を乗せて現場から逃げているから物理的な働きかけもしていると言える。そのため、暴行罪の幇助犯に当たる。
しかし、前述の通り2回目殴打は正当防衛として違法性が阻却されるため、上記幇助も連帯して違法性阻却される。なぜなら、幇助はあくまで正犯を容易にする行為であって、正犯を通して違法な行為を惹起することに処罰根拠があるため、正犯の違法性の有無が連帯すべきだからである。そのため、丁が、丙が正当防衛のためにCを殴っていることを知らなかった場合でも、丁の行為は違法性が阻却される。
したがって、丁の暴行罪の幇助は違法性が阻却されて不可罰になる。
第五 設問2(2)甲の罪責
甲は以前よりCと敵対関係にあり、今回Cに文句を言いにC方に赴いているところ、事前にCから殴られるかもしれないと予測し、その機会を利用して粗暴な丙に殴り返させることでCを痛めつけようと考えていた。そして、実際に殴りかかってきたCに丙が殴り返している。
1 上記について丙と甲の間で暴行罪の共同正犯(60条)が成立するか。
共同正犯の成立要件は共謀及びそれに基づく実行行為であるところ、当初Cが数回丙を殴っており、それに対して甲が丙に「俺がCを押さえるから、Cを殴れ。」と言っている。そして、甲は実際にCを押さえはしなかったものの、丙は甲の言うことを聞いて1回目殴打に及んでおり、甲と丙との間では共同してCに暴行を加える認識を互いにする共謀があったと言える。そして、右共謀に基づいて丙は暴行をしているため、共同正犯と言える。また、2回目殴打についてもCが連続して殴っている中でやり返すと言う一連の流れの中で行われていることから、共同正犯となる。
2 前述の通り丙は正当防衛のために1回目殴打及び2回目殴打を行っていて違法性が阻却されるところ、共同正犯の甲も連帯して違法性阻却されるかが問題となる。もっとも、共同正犯の場合は上記の幇助の場合と異なり、従犯ではないから正犯がそれぞれ独立していて、互いに因果を及ぼし合って実行行為を惹起することに処罰根拠がある。そこで、違法性阻却事由があるかは個別的相対的に考慮されるべきである。
今回甲はCによる先行的な暴行を予期してC方に臨んでおり、その機会を利用して攻撃を行う意思があったため、甲にとってCによる暴行は「急迫不正の侵害」とは言えない。また、自身や丙を防衛する意思はなく攻撃意思を持って丙と共謀を行っているため、「防衛のため」とも言えない。そのため、甲については正当防衛が成立せず、違法性は阻却されない。
3 したがって、甲には丙との間で暴行罪の共同正犯が成立する。
以上

