令和6年司法試験刑事訴訟法の優秀答案とは?(論文50位代合格・評価A)
2025年4月24日
司法試験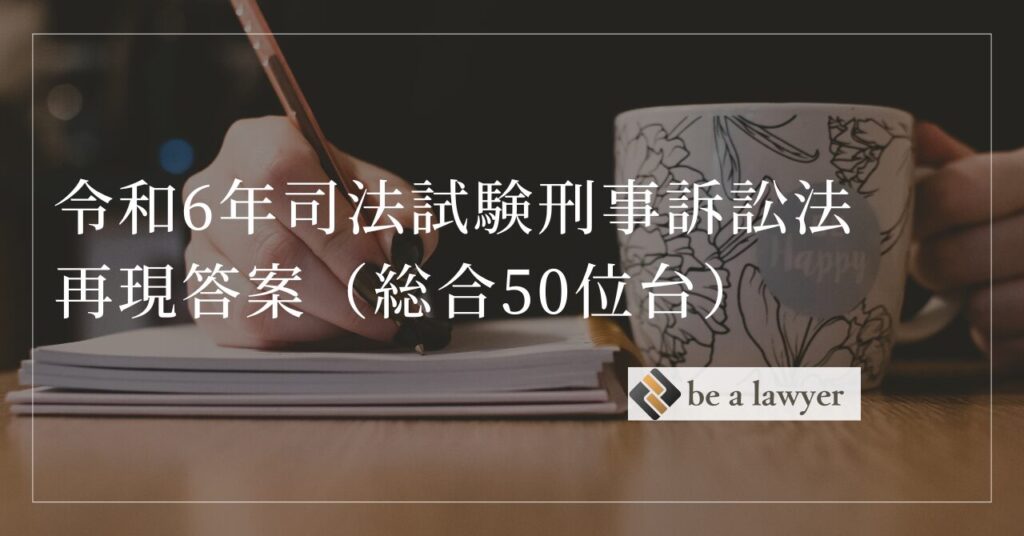
第一 設問1
鑑定書に証拠能力が認められるか。
1 鑑定書は、捜索差押許可状に基づいて差し押された結晶が覚醒剤である旨のものである。そして、この捜索差押許可状は捜査報告書①及び捜査報告書②を疏明資料として発布されているところ、この2つの報告書を作成する過程で違法捜査が行われた疑いがある。
違法捜査から派生した証拠について証拠能力を認めると、適正手続、将来の違法捜査の抑止、司法の廉潔性の観点から問題がある。もっとも、少しの違法によって派生証拠が排除されるとなるとかえって真相解明を妨げることとなり不都合である。そこで、証拠収集手続に令状主義を没却するような重大な違法があり、証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から不相当と認められる場合に証拠能力を否定する。そして、証拠獲得手続きそのものではなく手段を採るまでの先行手続において違法手続きが存在する場合は、違法手続きと問題となる証拠の密接関連性があるかを検討する。
2 まず、鑑定書獲得までの過程に違法な手続きがあったかを検討する。
鑑定書獲得の端緒として、警察官Pは甲へ職務質問をしており(警職法2条1項)、甲は覚醒剤の密売か行われているという情報のある本件アパート201号室から出てきて、男から本件封筒を受け取ったためそこに覚醒剤が入っているという疑いがあった。そのため、甲は合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者であり、このような者に対する職務質問自体は適法である。
3 もっとも、職務質問中に甲はいきなりその場から走って逃げ出しており、Pはこれを追いかけて甲の前方に回り込んで、甲の持っていた本件かばんのチャックを開けてその中に手を差し入れて中を覗き込みながら在中物を手で探って注射器を発見している。この行為について、所持品検査の限界を超えるものでないか問題となる。
所持品検査は、嫌疑のある者について職務質問をして犯罪を未然に防ぐために必要であり、職務質問と共に行うことができると考えられる。しかし、職務質問が相手方の任意で行われることや、所持品について捜査機関が見るという点でプライバシーに触れるものであることから、原則承諾を得て行うべきである。そして、承諾がない場合でも捜索に至らない程度で強制にわたらない程度であれば比例原則(警職法1条2項)に反さず認められると考える。
そして、Pは甲の承諾なく所持品の本件かばんの中に手を入れて探り、さらに中を覗き込んでいる。このような行為は所持品について詳細に調べるものといえ、既に捜索に至っておいる。そうすると、今回のPの行為は捜索許可状(刑訴法(以下法名略)222条1項、106条)無くして行われた捜索(以下、「本件捜索」とする。)であり、令状主義(憲法35条)に反する。
そのため、鑑定書獲得までに違法手続きがあったと言える。
2 本件捜索は、令状主義を没却するような重大な違法があり、証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から不相当と認められるか。
本来捜索とはその物の所持者のプライバシー権を侵害する物であるから、事前に裁判所の司法審査を経て令状を発布するという手続きを踏んで慎重に行われるべき物である。また、令状によって捜索の対象に限定をかけなければ、捜査機関が自由に捜索することが可能となり、人権侵害の程度も大きくなる。にも関わらず、令状なく捜索を行うことは右令状主義を没却する重大な違法があると言える。また、このような証拠を許容するとなれば将来同様の行為が繰り返されることが推測されて妥当でなく、将来の違法捜査抑制の見地から不相当といえる。
したがって、このような手続きから派生した証拠について証拠能力を認めることが相当でないと言える。
3 では、本件捜索と鑑定書に密接関連性が認められるか。
本件捜索後、Pは職務質問を実施した経緯に関する捜査報告書(捜査報告書①)及び注射器発見の経緯に関する捜査報告書(捜査報告書②)を作成し、これらを疏明資料として本件かばんについての捜索差押許可状が適法発布されている。そのため、裁判官が事前に審査して適法な令状によって本件捜索の違法性が断絶されているとも思える。もっとも、捜査報告書②にはPが本件かばんに手を入れて探り、書類の下から注射器を発見して取り出したことについて記載されていなかった。そうすると、捜査報告書②は令状主義の精神を没却する重大な違法が承継しており、このような報告書を疏明資料として発布された令状は適切な司法審査が行われたとは言えない。
仮に捜査報告書①のみが疏明資料であった場合には、その内容は覚醒剤の密売拠点と疑われる本件アパートから出てきた人物から甲が封筒を受け取ったことや甲の前科、甲が覚醒剤常用者の特徴を示していたこと、Pに質問されて逃げ出していたことが記載されており、これのみによっても令状が発布されたことが考えられる。しかし、捜査報告書②は覚醒剤摂取のために使用される注射器の発見について書かれており、通常甲が覚醒剤犯罪に関わっていることを示す直接的な証拠であるから、捜査報告書①のみでも令状発布されたと安易に考えて違法性がなくなったとすることは妥当でない。
そのため、捜査報告書①及び捜査報告書②を疏明資料として発布された捜索差押許可証は適法に発布されたとは言えず、本件捜索の違法性を承継しているといえる。また、この令状によって差し押さえた本件かばんの結晶及びその鑑定書についても、違法手続きによって得られたものとして密接関連性が認められる。
4 以上より、鑑定書の証拠能力は認められない。
第二 設問2捜査①の適法性
1 Pは喫茶店内で同店店長の許可を得た上で店内に着席していた男性をビデオカメラで撮影している(捜査①)。この捜査は強制処分(刑訴法(以下法名略)197条1項ただし書き)か。
強制処分は、強制処分法定主義及び令状主義(憲法35条)による厳格な手続き規制を受けるべき処分をいい、これに当たらない処分は任意処分となる。そこで、相手方の明示又は黙示の意思に反し、重要な権利利益を実質的に制約する処分と定義する。
本件で捜査①は男性の承諾を得ずにその姿態をビデオカメラで撮影しており、許可なく自身の姿を捜査機関にビデオカメラで撮られることは通常想定しないから、黙示的に意思に反すると言える。そして、上記撮影は姿態を撮影されない自由に反するものであり、この自由はプライバシー権(憲法13条に含まれる重要権利)を侵害しかねない。もっとも、今回の撮影は喫茶店で行われたもので、私的領域とは言えず、周りに他人がいてその人たちによって自己の容姿を見られることは許容されていると言える。そのため、重要な権利利益に対する実質的制約があるとは言えない。
そのため、捜査①は強制処分ではない。
2 捜査①は任意処分となるが、任意処分だとしても少なからず権利利益を制約するものであり、目的のために必要な限度でなされる必要がある(197条1項本文)。そのため、捜査①が任意処分の限度内か否かを検討する。具体的には、捜査を行う必要性や緊急性と比べて相当な限度かを基準とする。
捜査①の目的は、撮影対象の男性を乙であることを特定することであり、乙は覚醒剤拠点と思われる本件アパート201号室の賃貸借契約の名義人で覚醒剤取締役法の前科があった。覚醒剤犯罪は組織的で密行性がある重大犯罪で、右犯罪に関わっている者を検挙する必要性が高く、逃げられないように早期に解決する緊急性もある。
そして、乙は首右側にタトゥーが入っていて捜査対象の男性と顔が極めて酷似していたことから、男性の首右側にタトゥーが入っていることが確認できれば男性と乙の同一性を判断することができ、これによって男性を検挙できる。捜査①ではビデオカメラで対象男性を撮影するという手段をとっており、男性の首元を確実に撮影するためにはシャッターを押す必要のある静止画を撮るカメラではなくビデオカメラで撮影することは相当である。また、撮影は約20秒間とごくわずかな時間で行われている。撮影内容には男性の容姿や飲食の様子が写っているが、この内容であれば男性のプライバシーを大きく侵害するものではない。また、後方の客が映り込んでいたとしても、人が何人も集まる喫茶店で撮影する以上許容される。そのため、上記必要性及び緊急性に対して相当な手段で行われていると言える。
よって、捜査①は任意処分の限度内として許容される。
3 したがって、捜査①は適法である。
第三 設問2捜査②の適法性
1 捜査②は強制処分か。
Pは本件アパート201号室の玄関ドア御及び付近の共用通路を、向かい側のビル2階の部屋の窓からビデオカメラで2ヶ月間の間撮影している(捜査②)。アパートの住人は通常その玄関や共用通路について捜査機関から撮影されることを許容していないため、黙示の意思に反する。そして、上記撮影では本件アパート201号室に出入りする人々や玄関の内側、奥の部屋に通じる廊下が映り込むため、これらを撮影されない自由を侵害することとなる。そして、喫茶店とは異なり、アパートの部屋の共用通路や部屋の中は私生活を送るための場所として私的領域と言える。また、この部分はアパートの向かい側にあるビルの部屋の窓からでないと見えないのであり、その点でもプライバシーがあるという期待は高く、この場所についてのプライバシーの要保護性も高い。さらに、今回Pは2ヶ月間の間毎日24時間撮影をしていたのだから、このような長期間撮影することでアパートの共用通路や201号室の内部やそこに住む人の生活を具体的に知ることができ、プライバシー侵害の度合いも大きくなる。そうすると、捜査②は乙の生活のプライバシーという重大な権利を実質的に侵害していると言える。
したがって、捜査②は強制処分である。そして、ビデオカメラによる撮影は五感の作用によって現象を感知する捜査として検証の性質を有するから、強制処分法定主義には反しないが、令状なく行われているため令状主義に反する(218条1項、憲法35条)。
2 よって、捜査②は違法である。
以上

