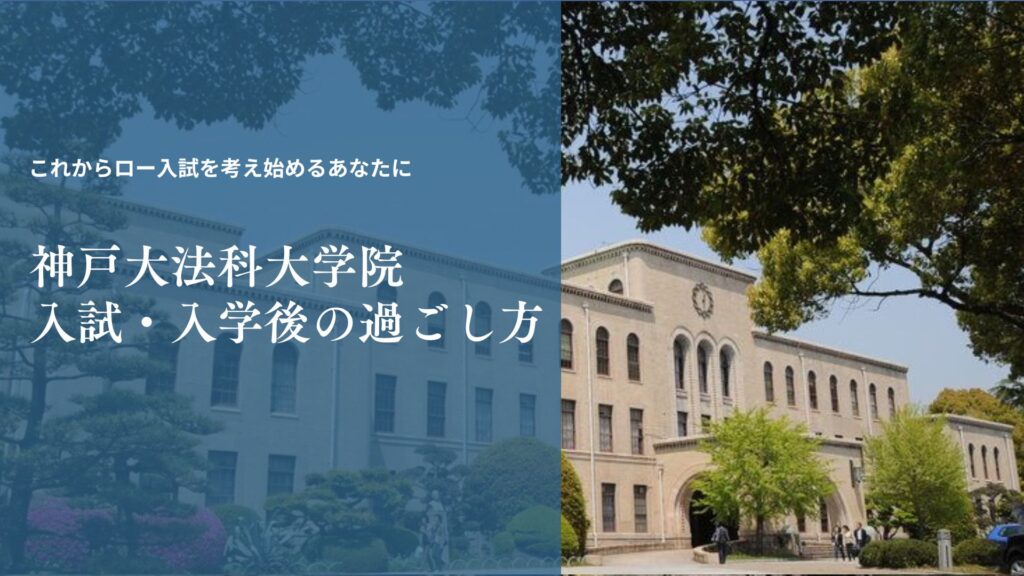
第1 神戸大学法科大学院(ロースクール)入試まで
1 試験形式
・論述式試験(憲法 50 点、行政法 50 点、民法 100 点、民事訴訟法 50 点、刑法100 点、刑事訴訟法 50 点、会社法 50 点):450 点満点
・論述試験と書類審査の比率は6:1
・試験科目7科目のうち2科目以上が一定の成績に達しない場合には、他の科目で合格点に達していて不合格となるため、注意が必要。
2 ロー入試対策としての勉強方法
・憲法
まずは基本書を読み、百選掲載の判例が出てきたらその都度百選で当該判例の事案と判旨を読むところから始めましょう。基本書は「基本憲法」がおすすめです(章末問題では事例問題の解き方も練習できます)。
また、憲法は出題範囲の限定がなく、どこを重点的に勉強すべきか悩むと思いますが、過去問を見ると人権範囲から出題される傾向にあるため、人権分野全般については広く勉強しておきましょう。
さらに、出題形式は三者間形式の論述と憲法上の問題点を論じさせるものとがあります。いずれの出題方法でもバランスよく論述できるよう準備しておきましょう。
より具体的な学習内容としては、ロースクール入試の過去問や予備試験過去問を用いて演習を行うことが重要です。余力があれば、重要判例解説を使って最新判例のアップデートも行っておきましょう。
・行政法
憲法と異なり、出題範囲がかなり具体的に絞られていることから、出題範囲として挙げられた行政法上の仕組みや定義をまずは正確に論述できるよう理解することが重要です。また、個別法の仕組みは複雑で、事例ごとに検討する必要があるため基本書を読み進める中で個別法の読解力を磨くことが有用です。
教材としては、「基本行政法」「行政法Ⅰ」(興津征雄)がおすすめです。神戸ローに入学した場合「行政法Ⅰ」(興津征雄)は教科書として指定されるはずなので持っていて損はないですし、ロー入試対策としても試験問題とマッチしていると思います。
・民法
出題範囲は財産法に限定されており、家族法分野からは出題されません。
また、民法上の制度の基本的な部分を理解しているかが問われる傾向にありますので、最初は初学者向けの基本書を使って全体像を掴んだ上で、より発展的な学習に進むことが有効です。
初学者向けの勉強教材としてはストゥディアがおすすめです。そして、通読の際には、出てきた条文を六法で引くことを心がけましょう。(民法は条文が膨大なので、大体の条文の場所を把握しておくことが重要です。)。
また、答案作成の前提として各論点について自分で論証を作成するのには時間がかかりすぎるため市販の論証集を購入して暗記をするところから始めましょう(但し論証集の記載内容を過信するのではなく、判例や基本書を読み進めながら自分自身の言葉で論証をブラッシュアップしていくことをオススメします。)
・刑法
刑法は答案の型があるため、数多く問題を解いて自分の書き方を見つけることが重要です。
基本書は「基本刑法」がスタンダードですが、初学者でも勉強が進んでいる方でも神大ローを目指す方は「徹底チェック刑法」を用いて勉強することをオススメします(入学後の定期試験対策でも役立ちます。)。
具体的な勉強方法としては、構成要件・違法性・責任の区別をしっかりと行い、該当する論点がどこの話なのか意識して検討する癖をつけましょう。
また、各論の勉強に入る前に総論を固めておかないと答案がめちゃくちゃになりますので総論(特に共犯関係)は時間をかけて丁寧に学習しましょう。
刑法は定義・趣旨など、他の科目に比べて暗記の部分が多く、逆に言うとそれさえやってしまえば、一定の点数は獲得できます。したがってまずは論証集を使って、各条文の定義・趣旨を暗記しましょう。
・会社法
会社法についてはまず、ストゥディアを読むところから始めましょう(会社法という分野についての全体像を掴むことが重要です。)。
次に「会社法」(俗にいう「紅白本」)を用いて各論点についての理解を深めましょう。紅白本はやや難解ですが、ロースクールの授業でも指定図書とされており、コラムまで含めると司法試験まで対応できる良書なので、持っていて損はないです。
また、会社法は条文操作が命です。にもかかわらず扱う条文数は非常に多いため、基本書を読む際は、出てきた条文を規則に至るまで全て六法で引いて確認するようにしましょう。その際は、目次欄と照らし合わせて、どの条文がどのあたりにあるか把握しておくことも有益です。
そして何より、問題の出題形式や出題者独特の癖に慣れるために、数多くの過去問を解きましょう。
・民事訴訟法
基本書としては「基礎からわかる民事訴訟法」がおすすめです。民訴は1周目で理解できる科目ではないため、問題演習を重ねる中で基本書の該当ページ、そして百選を何度も読み込むことが重要です。
民訴は基本書を読んで理解したつもりになっていても、実際に事例問題を解くとわからないといったことが往々にしてあります。したがって簡単な問題(学部の定期試験など)でも自分の頭で考えて、答案を組み立てる練習をしておくとよいです。
出題傾向としては、弁論主義や既判力の客観的・主観的範囲と具体的な作用の仕方、二重起訴といった民事訴訟法上の基本的概念・制度の理解の正確性を問う問題が出題されています。したがって、細かい論点や学説よりも基本的制度を正確に理解し、使えるようにしておくことが重要です。
・刑事訴訟法
基本書は「基本刑事訴訟法Ⅱ論点理解編」がおすすめです。併せて、「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」も学習すると過不足なく必要な知識を得ることができます。
出題範囲は特に限定されていませんが、刑事訴訟法における基本的事項(捜査法、証拠法を中心とする)という指示が出ています。よって、具体的事案との関係で各論点について知識を使いこなせるよう百選を読み込むこと、基本的な論証が素早くできるよう暗記しておくことが重要です。
第2 法科大学院(ロースクール)入学後の過ごし方
・憲法
前期に開講される対話型演習憲法では、主に人権分野について、判決文の内容を確認しながら学習を進めることになると思います。対話型の授業ですが、問題に対する解答を作成しなくても、判決文の内容を事前に確認さえすれば足り、予習の負担はさほど大きくないと思います。
後期に開講される応用憲法においては、主に総論・統治分野について、判決文の内容を確認しながら学習します。 対話型の授業ではないので、予習の負担はさほど大きくありません。
・行政法
前期の対話型演習行政法Ⅰにおいては行政実体法を、後期の対話型演習行政法Ⅱにおいては行政救済法を学習します。例年通りであれば、複数の班に分けられ、班ごとに特定の裁判例を答案化して報告することが求められます。答案化は班の中で役割分担して行うため、打ち合わせや話し合いなど授業外での活動も必須です。
・民法
基本的な知識の理解の確認、判決文の内容の確認、事例問題の検討など、担当者によって授業の内容が異なるので、予習の負担の程度も担当者によって異なります。担当者の指示する予習・復習を行うことが重要であることは言うまでもありませんが、民法は学習すべき内容が多く、時間の制約から百選掲載の重要判例や司法試験頻出論点であっても授業で扱われないものが多くあります。期末試験対策としては授業で取り扱った内容を中心に学習するのが正解ですが、司法試験対策としては授業内容を完璧に理解するだけでは不十分な可能性があり、授業外の内容も自学自習して民法全体の理解を深めることが望ましいです。
・刑法
前期に開講される対話型演習刑法Ⅰにおいては主に刑法総論の分野を、後期に開講される対話型演習刑法Ⅱにおいては主に刑法各論の分野を学習します。指示された事例問題について基本書や判例集などを確認しながら答案を作成する必要があるので、予習の負担はある程度あります。しかし、授業で扱う事例問題は「徹底チェック刑法」の問題が下敷きとなっておりますので最低限この内容さえ押さえていれば、中間・期末試験も問題なくこなせると思います。
・会社法
対話型演習商法Ⅰ・Ⅱにおいては、清算、持分会社、社債などの司法試験における出題可能性が低い分野を除いた分野を学習します。 商法Ⅰは、全ての授業の中で最も予習の負担が大きく、最もハイペースな授業です。授業は事前に用意された設問に指名された学生が回答する形で進み、その設問の量はとても多いです。しかし、きちんと基本書や判例集を読み、条文を引き、設問への回答を準備していれば、十分授業にはついていけますし、確実に力がつきます。
・民事訴訟法
前期に開講される応用民事訴訟法においては、複数請求訴訟、多数当事者訴訟、上訴、再審などについて学習します。担当者によって授業の内容は異なりますが、主に講義形式の授業であり、予習の負担は大きくありません。
後期の対話型演習民事訴訟法においては、民事訴訟法の全体の論点について学習します。いきなり司法試験レベルの話を展開することも多いため、自分で基礎的な部分を固めたうえで授業に臨む必要があります。
・刑事訴訟法
前期の対話型演習刑事手続実務においては、刑事手続における各論点や証拠からの事実認定の方法などについて、実務家教員から学習します。 指示された課題について事前に検討をして授業に臨む必要があるので、予習の負担は大きいと思います。後期の対話型演習刑事訴訟法においては、刑事手続における各論点について判例文の内容を確認しながら学習します。事前に質問の内容を考えておく必要がある点が特徴です。
さて、ここまで色々と書いて参りましたが、神大ローの教授陣は総じて質が高く、授業内外での熱心な指導が魅力的です。これを読んでいるあなたも是非神大ローで共に合格を掴み取りましょう!!

be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


