強盗罪にいう「暴行又は脅迫」の考え方〜令和3年司法試験刑法を題材として〜
2025年8月9日
お知らせ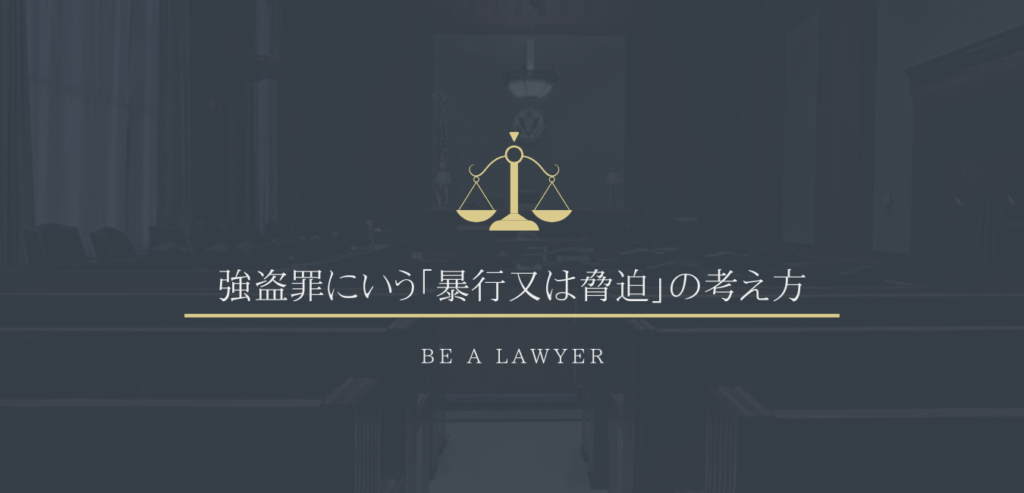
今回は、令和3年度司法試験の刑法を題材として、合格答案と不合格答案を比較し,なぜ優秀答案が高い評価を受け,他方で不合格答案が低い評価にとどまったのかという点を分析し,受験生の皆さんがどのような点に気を付けて答案を作成すれば,合格答案を書くことができるようになるのかをレクチャーしていきたいと思います。本記事は,令和3年度司法試験刑法の問題文1段落目から5段落目までを読んだ上で,読んでいただければより理解が深まると思います。
では、早速、合格答案(A評価答案)と不合格答案(C評価答案)の2つの答案を見ていきましょう。
【優秀答案のの当てはめ】
『「脅迫」とは、財物奪取に向けられた相手方の犯行を抑圧するに足る害悪の告知をいうところ、たしかに、甲は刃渡り 20 センチメートルに及ぶ本件ナイフを丙に示した上で、「殺されなかったら時計を入れろ」と申し向けており、犯行を抑圧するに足る害悪の告知があるようにも思える。もっとも、甲は、あらかじめ丙との間で、刃物を示して脅しているうちに時計を持ち去る旨の意思連絡をしており、上記行為はこの計画に基づいて行われている。そうすると、そもそも上記行為は、丙の財物を奪取するために向けられていないから、強盗罪にいう「脅迫」にあたらない。』
【不合格答案のの当てはめ】
『強盗における「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる有形力の行使または害悪の告知をいい、これにあたるかは社会通念に従い、客観的に判断する。甲は、丙に対して刃体の長さ約 20 センチメートルもの長さの本件ナイフを示しながら、「殺されたくなかったら」、「刺すぞ」と語気を強めて言っている。このように本件ナイフを示しながら、上記のようなことを言われた場合には、通常、人は本当に殺されるかもしれないと考え、反抗抑圧するといえる。したがって、上記甲の行為は、丙の反抗を抑圧するに足りる有形力の行使または害悪の告知にあたり、強盗における「暴行又は脅迫」が認められる。』
【両答案の比較検討】
まず、C答案(不合格答案)の「暴行又は脅迫」の定義に着目していただきたいです。一見A答案の「脅迫」の定義と同じように見えますが、C答案の定義には「財物奪取に向けられた」という部分が抜けています。これは不正確な定義です。
なぜなら、強盗罪は財産犯であるため、強盗罪の実行行為たる「暴行又は脅迫」は財物奪取に向けられていなければ認められるはずがないからです。したがって、規範定立の時点でC答案は減点されている可能性があると言えます。このようなことから、規範は正確に指摘できるように日頃から意識して勉強していただきたいと思います。
次に当てはめについて見てみましょう。まず、C答案は『甲は、丙に対して刃体の長さ約 20 センチメートルもの長さの本件ナイフを示しながら、「殺されたくなかったら」、「刺すぞ」と語気を強めて言っている。このように本件ナイフを示しながら、上記のようなことを言われた場合には、通常、人は本当に殺されるかもしれないと考え、反抗抑圧するといえる。』と当てはめを行っています。問題文の具体的な事実を拾いつつ、事実に対する自分なりの評価も加えることができているので、一見すると一定の評価を受ける答案に思えます。しかし、結果はC評価、現在の司法試験では不合格答案に該当します。果たして、なぜ一見よく書けているように見える答案がこれほどまでに低い評価にとどまったのでしょうか。ここからは、この点について掘り下げて検討してみましょう。
出題趣旨を見てみましょう。出題趣旨では、『甲が丙に対して,サバイバルナイフを示し,「殺されたくなかったら,これに時計を入れろ。」と要求した行為は,一般的には 相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫と評価することが可能であろうが,甲と丙があらかじめ内通していた事実を隠蔽するために,あたかも丙が犯人から脅されたかのように仮装することを企図し,実際にその計画どおりに犯行を遂行したにすぎない本事例の事実関係の下では,甲が丙にサバイバルナイフを示して前記文言を述べた行為は,財物の奪取に向けられたものと評価することはできず,強盗罪の「脅迫」たり得ないし,また,甲はそのことを認識しているのであるから,強盗罪の故意を認めることもできない』と指摘されています。つまり、丙は甲の犯行を知っていた以上、甲の脅迫行為は、丙の財物を奪取することに向けられたものではなく、いわば甲と丙の間で合意された計画を成功させることに向けられたものということになります。そうすると、甲の行為は、強盗罪にいう「暴行又は脅迫」の定義のうち、「財物奪取に向けられた」という部分に該当せず、強盗罪の実行行為には当たり得ないのです。それと同時に、故意とは客観的構成要件を認識し、かつ認容することと一般的に定義されますが、上記のように甲は財物奪取に向けられた脅迫ではなく、甲は,甲と丙の間で合意された計画を成功させることに向けられた脅迫をすることしか認識認容していないことになりますので、強盗罪の故意についても当然否定されることになります。立ち止まって考えてみると、およそ財物奪取に向けられていない「脅迫」行為に強盗罪の実行行為たる「脅迫」を認めてしまえば、甲には最低でも強盗未遂罪が成立することが確定してしまいますので、財産犯たる強盗罪の趣旨に反することは明らかといえます。この点については,採点実感でも『本問で強盗罪(又は強盗未遂罪)の成立を認めた答案は,強盗罪の実質に関する理解が著しく不足しており,個別の要件を形式的に判断するにとどまっているといわざるを得ない。また,結論として強盗(未遂)罪の成立を否定した答案にも,甲の行為が強盗罪の「脅迫」に該当するとした上で,丙が現実に反抗を抑圧されていないことのみを根拠とするものや,強盗(未遂) 罪の構成要件該当性を肯定しながら,丙が財物の強取に同意していることから違法性が阻却されるとするものなど,結論を導く前提や論理過程に誤りを含む答案が散見された』と酷評されており,強盗罪の成立を認めることはもちろん,強盗未遂罪を成立させた答案も著しく低い評価を受けていることが分かります。
これまでの検討を前提として次に合格答案を見てみましょう。合格答案は,強盗の故意部分についての認定は欠いているものの、「脅迫」のあてはめについては,財物奪取に向けられたものではないという点を指摘できており,非常によく書けていることが分かると思います。合格答案の受験生がなぜ「脅迫」の当てはめを不合格答案の受験生のように間違えなかったかというと、それは規範の正確性にあると思われます。不合格答案は冒頭でも指摘したように、そもそも強盗罪にいう「暴行又は脅迫」の規範が誤ってしまっていますので、不正確な規範に対して当てはめを行なってしまい、結果として結論自体も不正確なものになってしまったというわけです。本問は、規範が不正確だと当てはめも不正確になるという際たる例だと分析することができます。
この両答案の比較を通して、司法試験・予備試験の合格答案を書く上で重要なことは「規範を正確に理解する」ことだと考えられます。ここで,「規範を暗記する」とあえてしなかったのは、先の例で言うと、強盗罪が財産犯であることは司法試験を受験するレベルの受験生であれば、どの受験生も知っているはずです。しかし、規範を単に暗記するだけにとどまり,規範の意味を正確に理解できていなければ,今回の例のように当てはめを正確に行うことができません。これが規範を単に暗記することの弊害だと言えるでしょう。他方で、「規範を正確に理解」できていれば、強盗罪が財産犯であることから、当然その実行行為たる「暴行又は脅迫」は財物を奪取することに向けられていなければならず、そのような観点から本問の事情を見れば,甲の脅迫行為が丙の財物を奪取することに向けられていないことは明らかなので,強盗罪の実行行為に当たるはずがないということを迷うことなく答案に示すことができるはずです。
今回は,強盗罪にいう「暴行又は脅迫」を題材として合格答案と不合格答案の分析を行なってきましたが,「規範を正確に理解すること」は刑法の他の論点についてはもちろんのこと,他の法律科目についても重要だといえるでしょう。受験生の皆さんには,論招集を単に暗記するだけではなく,判例がなぜそのような規範を定立したのか,を常に考えて勉強するという姿勢を忘れないでもらいたいと思います。

be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


