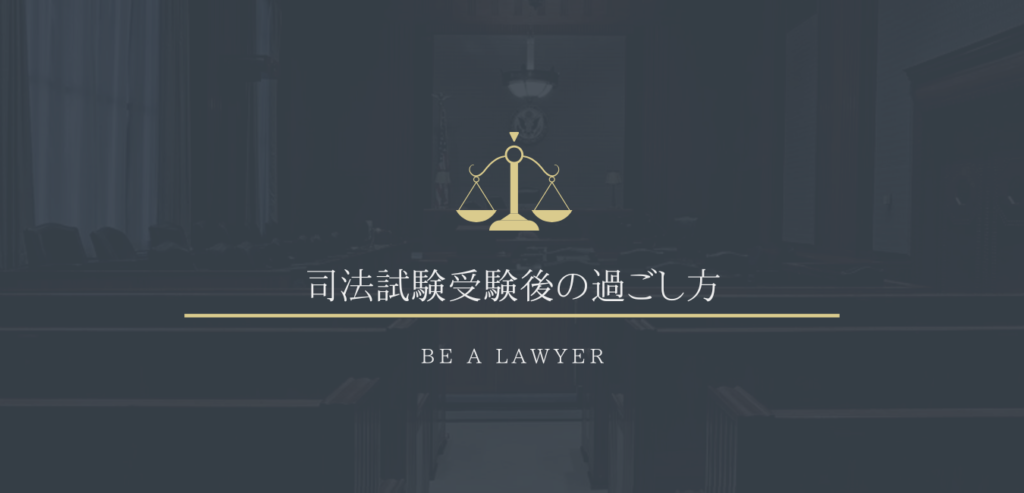
こんにちは、be a lawyer講師のI.Sです。今回は司法試験受験後から合格発表までの過ごし方についてまとめてみましたのでよろしければご覧ください。
1 はじめに
司法試験を終えた皆さん、本当にお疲れ様でした。人生をかけた大勝負を乗り越えた今、肩の荷が下りたという解放感と、結果が分からないという緊張感や不安が入り混じる、独特の時期を過ごしているのではないでしょうか。
もっとも、合格発表までの数か月間は、決して「ただ待つだけの時間」ではありません。特に、合格の可能性が高いと感じている人にとっては、今後の進路を見極める上で極めて重要な時期です。
この記事では、司法試験合格の可能性が高い方に向けて、この期間を有意義に過ごすためのポイントを主に、①就職活動、②その他の生活面の観点から解説していきます。
2 就職活動
(1)自己分析
司法試験を終えた直後の今こそ、自分がどんな法曹になりたいかを真剣に考える絶好のタイミングです。弁護士、検察官、裁判官のいずれを志望するのか、特に弁護士の場合にはどのような分野を取り扱いたいのか、弁護士事務所に所属するのか、企業内弁護士になるのか等、法曹の進路は多岐にわたります。
将来の志望分野を1つでも決めておくことで、就職活動も効率的かつ具体的に進めることができます。周りの人に相談して、自分の興味関心を掘り下げておきましょう。
(2)弁護士の就職活動(サマークラーク・事務所説明会等への参加)
最近では法律事務所の就職活動がどんどん前倒しとなり、中には司法試験を受験する前に実質的な内定先が決まっている人も存在します。しかし、あくまでそのような人は稀であって、「周りより就活が遅れているのではないか」と焦る必要は全くありません。
多くの法律事務所や企業では、司法試験直後の夏から秋にかけて「サマークラーク」や「事務所説明会」「事務所訪問」が行われます。アットリーガル等の就職情報サイトを逐一チェックして採用選考に関する情報を取得し、積極的に参加しましょう。
もちろん司法修習が開始されてから就職活動を始めても遅くはありませんが、修習では毎日忙しい日々を送ることから、並行して就職活動も行うのはかなり大変です。また、将来働きたいと思っている地域と司法修習地とが異なると、場合によっては当該地域まで移動しなければならなくなり、手間と費用がかかることになってしまいます。そのため、時間がある今の時期に、少しでもいいので就職活動に取り組んでおくことを推奨します。
(3)検察官・裁判官の就職活動
意外に思われるかもしれませんが、検察官や裁判官を志望している人にとっても、弁護士就活の状況は無関係ではありません。
実際に検察官や裁判官の就職活動が始まるのは司法修習が開始されてからですが、そこでは、弁護士事務所などの内定を有していることが、検察官・裁判官就活にとっても有利に働くと言われています。
そのため、(2)で述べたように、サマークラーク・事務所説明会等には積極的に参加しておくことをおすすめします。
(4)エントリーシートの書き方
いざサマークラーク等に参加しようとすると、エントリーシートの提出が求められることがほとんどです。
エントリーシートには何を書けばいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。筆者もかなり苦労した経験がありますので、その経験も踏まえて、個人的にやるべき・書くべきだと思っているポイントをいくつかお伝えします。
(i) 企業分析
まずは、エントリーシートを提出しようとしている弁護士事務所等のホームページをチェックしましょう。どのような分野を取扱っていて、その分野に対しどの程度注力しているのかを確認することが、最初の第1歩です。もし可能であれば、その事務所等がどのような弁護方針を採っているのか、事務所内の雰囲気作りとして、いかなる点を重視しているのかについても、ホームページや周囲の人から情報を取得できるとよいでしょう。
(ii) 価値観を共有できるか
自分が将来取り組みたい仕事や、希望する働き方が、その事務所で実現できるのかどうかについて記載することをおすすめします。
例えば、自分が大きい案件の一部に関わりたいとするならば、そのような大型案件を主に取り扱う事務所がマッチしていると思いますし、他方、中小規模の案件を自分で最初から最後まで取り組みたいのであれば、そのような案件を主に取り扱う事務所が合っていると思います。また、興味分野がよくわからない方は、司法試験の選択科目を手掛かりに、その分野に力を入れている事務所を探してみるのもいいかもしれません。
そして働き方についても、出勤時間が固定されているのか、それとも自由なのか、必ず事務所にいなければならない時間が存在するのか等についてもリサーチできると良いでしょう。
3 その他の生活面
(1)まずは心身のリフレッシュ
受験勉強が長引けば長引くほど、知らず知らずのうちに心も体も疲弊しています。今は焦らず、生活リズムを整え、十分な休息を取ることが次のスタートにとっても大切です。軽い運動、友人との時間、趣味に没頭するなど、リラックスできる時間を意識的に持ちましょう。
個人的には、海外旅行に行くことを強くお勧めします。海外の風土や文化に触れて価値観を広げておくことは、一生の財産になります。
(2)スキルアップに挑戦してみる
少し元気が戻ってきたら、語学(特に英語)やパソコンスキル(Word、Excel、PowerPoint)など、社会人としての基本的なスキルを磨くのもおすすめです。特に英語力は、渉外系事務所や企業法務では重視されるポイントの一つであることに間違いありません。
(3)合格発表を「ゴール」ではなく「スタート」と考える
司法試験は文系最難関の試験ともいわれており、「もし不合格だったら…」という不安が頭をよぎることも多々あるかもしれません。筆者も、11月の合格発表が近づくにつれて不安が襲い掛かってきたのを今でも昨日のように覚えています。
しかし、合格発表前に準備しておくことは、仮に再受験になっても決して無駄にはなりません。むしろ、早い段階から動いている人ほど、次のフェーズでの選択肢が広がります。
(4)司法修習の準備
合格後は司法修習がスタートします。どの修習地を希望するか、どのようなカリキュラムなのか、修習中に何を重視すべきか、生活費はどれくらいかかるのかなど、今のうちに情報を集めておくと安心です。第6希望まで選択できる修習地。修習地によっては生活スタイルや出費も大きく変わるため、現実的な生活設計を考えておくとよいでしょう。
そして、検察官・裁判官を志望している人にとっては、修習地選びがさらに重要な意味を持ちます。高等裁判所のある大規模修習地で検察官・裁判官が実際に業務に取り組む姿を見ておくことは、将来必ず役に立ちます。他方、中小規模修習地での修習は大規模修習地に比べ、指導担当の目が届きやすく熱心に指導されるため、検察官・裁判官の内定者が多いとの噂もあります。修習地を選ぶにあたっては慎重に情報を取捨選択しましょう。
(5)社会人マナーの習得
司法試験合格者であっても、「社会人としての基本」ができていないと、就職先や修習先で苦労することになります。名刺交換、言葉遣い、服装など、最低限のビジネスマナーをこの期間に習得しておきましょう。
4 おわりに
司法試験が終わった今、気持ちに一息つくのは当然です。ただし、ここでただ「待つ」だけの時間にしてしまうのはもったいないことです。合格発表までの数か月間は、法曹としてのキャリアをスタートするためのいわば“助走期間”です。この時期をどう過ごすかが、来年以降の自分を大きく左右します。
就職活動の準備を進めるもよし、スキルアップに挑戦するもよし。何より、自分と向き合う貴重な時間として、この期間を大切に使ってください。合格発表の日、堂々と前に進むために、今できることを一歩ずつ始めましょう。
be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中です!以下よりご登録ください!

関連記事はこちら

