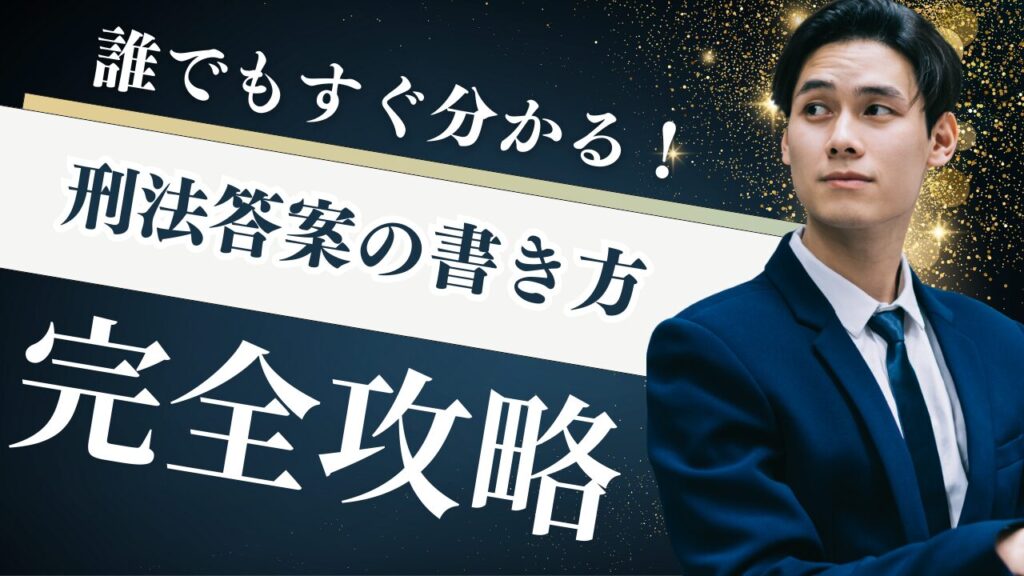
1 刑法答案の基本的な書き方
刑法の答案の書き方は知っている受験生も多いと思いますが、これから答案を書く方に向けて、ここで一度確認しておきましょう。
刑法は大学受験の科目で言えば数学のような科目にあたり答案のお作法が決まっています。数学で言うと証明問題に近い気がします。
刑法の問題では「甲の罪責を述べよ。」、「甲乙の罪責を検討しなさい。」というように、問題文に出てくる登場人物が行った行為に対してどのような犯罪が成立するかを検討させる問題が基本パターンです(一部例外もあり)。
そのため、刑法の問題を解く際にまず重要となるのが犯罪の定義になります。
犯罪とは、「構成要件に該当する、違法で、有責な行為」をいいます。
このような前提に立てば、ある行為に犯罪が成立するかを検討する場合には、
①まず当該行為が構成要件に該当するかをチェックする
↓
②次に例外的に違法性阻却事由がないかをチェックする
↓
③最後に例外的に責任阻却事由がないかをチェックする
上記のいずれもがクリアされれば犯罪が成立すると整理することができます。
これを答案の形に修正すると刑法の答案の書き方は、
第1 〜という行為に〇〇罪(刑法××条)が成立しないか(問題提起)。
1 構成要件該当性
(1)実行行為
(2)結果
(3)因果関係(順番に決まりはない。どちらから書いてもよい)
(4)故意+α
2 違法性阻却事由(ex.正当防衛、緊急避難)
3 責任阻却事由(ex.責任故意、原因において自由な行為)
4 結論
以上から、〜という行為には〇〇罪が成立する。
という風に書くことになるでしょう。
検討漏れのないように、また、読み手にとって分かりやすく論じるために上記のようなナンバリングを付すと良いと思います。
そして、法律科目の答案では、最初に問題提起をした上で、その判断は法的三段論法に従って
(1) 規範定立(大前提)
(2) 当てはめ(小前提)
(3) 結論
という段階に分けて行う必要があります。これは刑法についても同様ですので忘れないでください。
刑法についてはこの法的三段論法の判断も「構成要件該当性→違法性→有責性」としてそれぞれ細分化して行われることになります。
2 実際の問題を通して答案の書き方をマスターしよう
■問題文
甲は、対立抗争中の暴力団の組員に襲われた場合に備えて、護身用に登山ナイフを身に付けていたところ、ある日、薄暗い夜道を帰宅途中、乙が、いきなり背後から前に回り込んできて、右手を振り上げて甲を殴ろうとしたので、甲は自己の身を守るために、殺意を持って登山ナイフ(刃渡り15センチメートル)で乙の腹部を思いっきり一回突き刺し、乙は刺されたことが原因で失血死により死亡した。
■検討
まず、甲の罪責として検討されるべきものは殺人罪(刑法199条)になります。
刑法の条文を見ると、
(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
と定められており、殺人罪の構成要件を洗い出すことになります。各犯罪の構成要件の数は覚えておく必要があるので頑張って勉強してください。
殺人罪の構成要件は以下の4つになります。
【殺人罪の構成要件】
(1) 実行行為
(2) 死亡結果
(3) 因果関係
(4) 故意(殺意)
上記の構成要件を満たせば殺人罪の構成要件に該当することになり、違法性・責任についても認められれば犯罪が成立することになります。
しかし、本件では甲は乙による暴行を防ぐために反撃行為を行っているため、正当防衛(36条1項)の成否が問題となります。
正当防衛の成立要件は
【正当防衛の成立要件】
(1) 急迫不正の侵害
(2) 防衛の意思
(3) やむを得ずにした行為
の3つとなりますので、こちらも合わせて検討する必要があります。
責任阻却事由は存在しなさそうなので、本件での検討は不要です。
■答案
第1 甲が乙の腹部を登山ナイフで突き刺した行為に、殺人罪(199 条)が成立しないか。
1 構成要件該当性
(1) 実行行為
実行行為とは人を死に至らしめる現実的危険性を有する行為をいい(規範)、甲が刃渡り15センチメートルの登山ナイフで人体の数要部である腹部を思いっきり一回突き刺す行為は乙を死に至らしめる現実的危険性を有するものであるから(当てはめ)、殺人罪の実行行為に当たる(結論)。
(2) 結果
乙は死亡している。
(3) 因果関係
因果関係とは実行行為と発生した結果との間の関連性をいい(規範)、刑法上の因果関係が認められるためには当該行為の危険性が結果として現実化したか否かで判断するところ(当てはめ)、甲が乙のナイフを一回突き刺した行為が乙の死亡結果として現実化しているため、因果関係は問題なく認められる(結論)。
(4) 故意(殺意)
甲は、殺意を持って上記行為を行っているから、殺人罪の構成要件的故意(38 条1項)も認められる。
(5) 結論
したがって、上記行為は殺人罪の構成要件に該当する。
2 違法性阻却事由
次に、甲は乙に対する反撃として上記行為を行っているため、正当防衛(36 条 1 項)が成立し、違法性が阻却されないか。
(1) 急迫不正の侵害
急迫不正の侵害とは法益侵害が現実化しまたは差し迫っていることをいうところ、乙がまさに右手を振り上げて甲を殴ろうとしていたから、甲に対する法益侵害が差し迫っていたといえ「急迫不正の侵害」が認められる。
(2) 防衛の意思
防衛の意思とは、自己に対する侵害を認識しつつそれに対抗しようとする単純な心理状態をいうところ、甲は殺意を持っているもののあくまで身の危険を感じてそれに対抗しようとする意思を有しているため、防衛の意思が認められる。
(3) やむを得ずにした行為
正当防衛の場合、防衛者とその相手方とは正対不正の関係にあるから、かならずしも防衛行為が唯一の侵害を回避する方法であることは要求されないし、厳格な法益権衡も必要ない。したがって、反撃行為自体が防衛の手段としての相当性を満たしていれば「やむを得ずした行為」といえる。
甲は、素手で殴りかかられた行為に対して、殺意を持ってナイフを突き刺す行為をしている。かかる反撃行為は明らかに相当性を欠く過剰なものであるといえる。
したがって「やむを得ずした行為」とはいえない。
3 責任阻却事由
責任を阻却する事情は本件には認められない。
4 結論
以上からすれば、乙の腹部を登山ナイフで突き刺した行為に、殺人罪が成立し、過剰防衛(刑法36条2項)として刑が任意的に減免される。
be a lawyer受講者の方には答案の書き方に関する解説動画を無料で配布しております(youtube上に限定公開しておりますので受講者の方にはリンクを共有いたします)。
↓初回無料面談はこちら↓

be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


