刑法答案の書き方(答案の型)とは?
2025年10月7日
お知らせ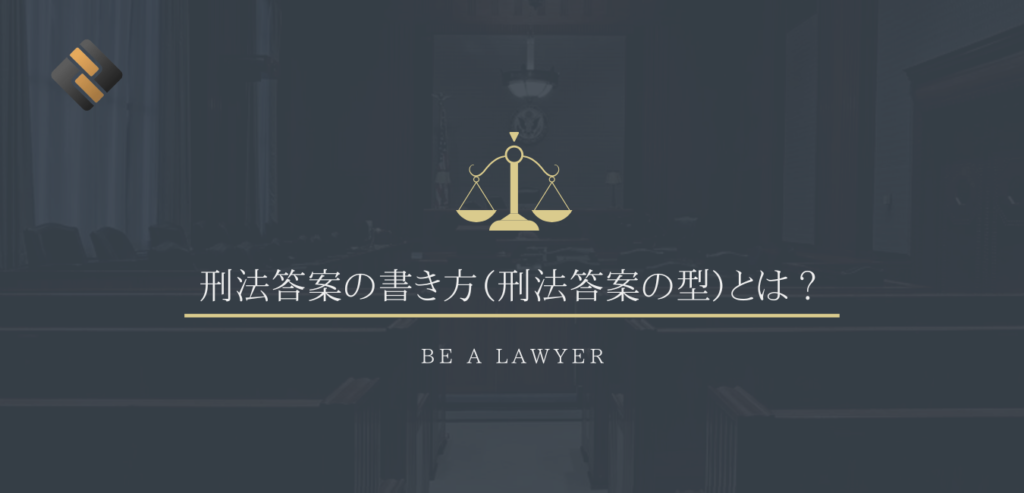
本記事は刑法答案の書き方がわからない方、これから刑法答案を書きはじめようとしている方向けの記事です。
1 はじめに
司法試験・予備試験個別指導専門塾be a lawyerは刑法に関して「答案の型」を押さえることが重要であると考えています。
答案の型とは答案のフレームワークを指しており、これを最低限守っていれば、答案の形になるというものです。
一定程度勉強が進んでいる方からしてみれば「当然じゃん」という感じかもしれませんが、今から答案を書き始める方はどこからどう書き始めて良いか分からないという方も少なくはないでしょう。そのような方にとっては問題文を見てもペンを動かすことすら困難です。
ただ、予め「これを見て書けば良い」、という答案の型を知っていれば、これまで手も足も出なかった問題に対して一定の解答を示すことができるようになります。もちろん、これだけで答案が書けるようになったわけではないですが、何か書けるようになったという小さな自信を生み、もっと書けるようになりたいと勉強意欲を向上させると信じております。
これから刑法答案を書き始める方はぜひ、下記の刑法答案「基本の型」を押さえてみてください。
2 刑法答案「基本の型」
| 甲の〜の行為に〇〇罪(刑法〇〇条)が成立しないか。 1.構成要件該当性 (主体、客体が問題となる際には言及した上で) (1) 実行行為 「〇〇」とは・・・をいう。本件の〜は(事実)、〜であり(評価)、・・・といえため、「〇〇」に当たる(結論)。 (2) 結果本件では〜の結果が発生した。 (3) 因果関係ア 因果関係の存否は、行為者に偶発的な結果を帰責させるべきでないことから、条件関係の存在を前提に行為の危険性が結果へと現実化したか否かで判断すべきである。かかる判断は①行為の危険性 、②介在事情の結果への寄与度、③介在事情の異常性を総合考慮しておこなう。 イ 本件では〜。 (4) 故意(構成要件的故意)故意とは客観的構成要件事実の認識・認容をいうところ、本件では〜であるため、客観的構成要件事実を認識・認容しているといえ、故意に欠けるところはない。 (5) 結論よって、〇〇罪の構成要件に該当する。 2.違法性 (1)正当防衛 (2)緊急避難 ((3)自救行為) 3.責任 (1)原因において自由な行為 (2)心神耗弱・心神喪失 (3)違法性阻却事由の錯誤(責任故意) 4.結論 以上より、甲の〜には〇〇罪が成立する。 |
3 答案の書き方解説動画
短い動画ではありますが、簡単な解説動画もございますのでよろしければご覧ください。
be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


