
はじめに ― 「答案の型」を身につけることの重要性
司法試験や予備試験の論文試験における民法では、知識をただ暗記して吐き出すだけでは合格答案になりません。他科目でも共通ですが、大切なのは、「答案の型」を身につけることです。
一度、答案の型を意識して答案を書けるようになると、どんな事案が出ても落ち着いて処理できるようになります。
論証パターンを反復し、処理の順序を体に馴染ませておくことで、安定した答案が書けるようになるのです。
Step 1:事案の理解と問題の設定
民法の事例問題を解く際にまずやるべきことは「当事者が何を求めているのか」を整理することです。
例えば、「Aは土地の引渡しを求めたい」「Bは契約を解除したい」「Cは損害賠償を請求したい」といったように、当事者の求めていることを具体的に言葉にしてみます(この際、要件事実の理解があるとより正確な整理ができるようになるのでおすすめです。)
そのうえで、それを法律上の権利に置き換えます。
引渡請求が物権的請求なのか、それとも契約に基づく債権的請求なのか。こうした位置づけをはっきりさせることで、検討すべき論点が浮かび上がってきます。
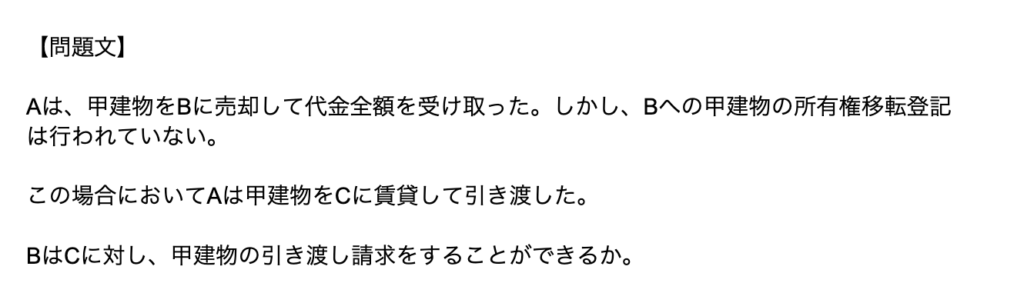
上記の事例において、BはCに対して甲建物の引渡しを求めています。引渡し請求の根拠としては物権的請求と債権的請求のいずれかが考えられますが、BとCの間に契約関係はありませんから、今回は物権的請求を選択すべきだとわかります。
そして、Bは甲建物の明渡しを求めているので、Bの請求の根拠は「甲建物の所有権に基づく明渡し請求権」であると整理することができます。
次に、「甲建物の所有権に基づく明渡し請求権」が発生するための要件として、①Bが甲建物の所有権を有すること、②Cが甲建物を占有すること、が必要となりますので、本件の事情を踏まえて①、②の要件充足性を検討することになります(原則論)。
論述例は以下のようなイメージです。
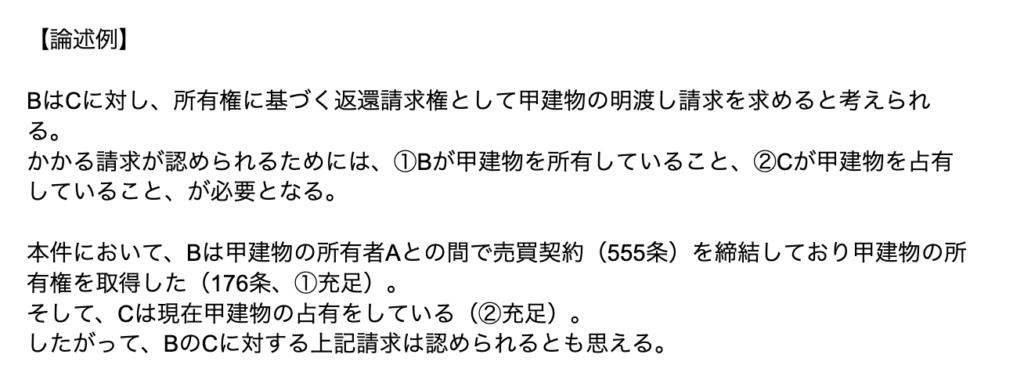
Step 2:法的検討の流れを組み立てる
次に、請求を認めるための要件を三段論法で検討します。
① 規範:どのような枠組みで判断すべきなのか
② 当てはめ:問題文の事実が枠組みに該当するのか
③ 結論:該当するのか、該当しないのかの見解を示す
この流れを守るだけで答案の骨格はかなり整います。答案が苦手な人はいつまで経っても三段論法が守れない人が多いです。
また、試験では「相手方の反論」を忘れずに想定しましょう。
たとえば、同時履行の抗弁(民法533条)や解除の主張など、相手が言いそうなことを一度は答案に取り込み、こちらの見解を示すことで、答案が説得的になります。
上記の事例では、Cは177条の「第三者」としてBが登記を具備するまでは引渡しを拒絶できると反論することが想定されるでしょう(対抗要件の抗弁)。
177条の「第三者」とは当事者及びその包括承継人以外の者で不動産物権変動に関する登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう、と解されており、判例上賃借人はかかる第三者に該当すると解されています。
そのため、BがCに所有権を対抗するには甲建物の登記が必要になりますが、現時点でBは甲建物の登記を有していないわけですから、Cの反論が認められることになりそうです。
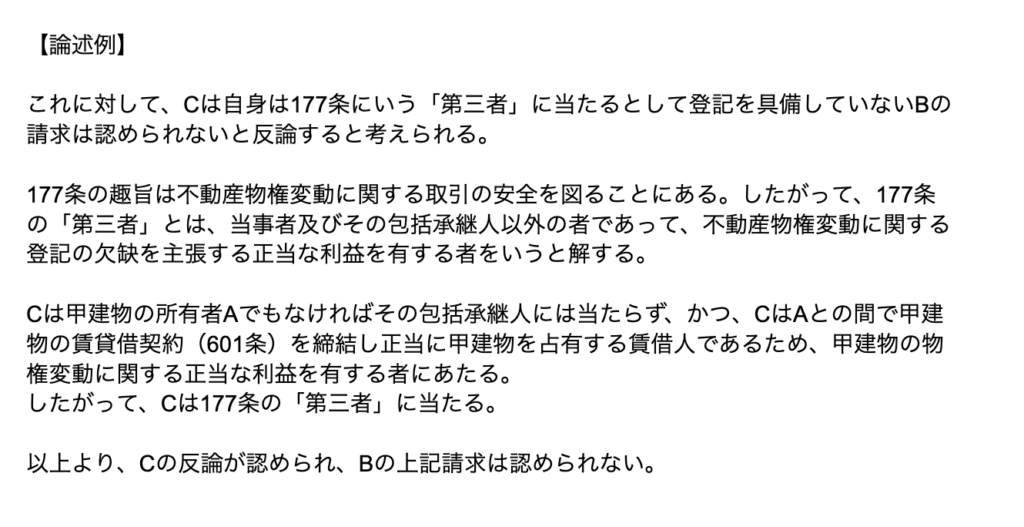
Step 3:答案の書き方 ― 読みやすさが命
採点者が読みやすい答案は、それだけで評価が上がります。
✔︎ 答案の冒頭で「訴訟物」と「請求の趣旨」を示す
✔︎ ナンバリングで論理の階層をはっきりさせる(第1 → 1 → (1)…)
✔︎ 一文は短く、冗長な表現は避ける
こうした小さな工夫の積み重ねが、答案全体の印象をぐっと良くするので意外と馬鹿になりません。
Step 4:実践で磨きをかける
答案の型を知っていても、実際に時間内で書けなければ意味がありません。
だからこそ、過去問や答練を使った「制限時間内で書き切る練習」が欠かせません。
✔︎ 論証パターンを繰り返し書いて体に染み込ませる
✔︎ 接続詞や助詞を意識して、論理の流れを滑らかにする
✔︎ 構成に使う時間を決めて(予備試験なら20分、司法試験なら40分)、残りで一気に書き上げる
こうした積み重ねによって、初めて「答案の型」が出来上がります。
Step 5:添削・個別指導で答案をブラッシュアップする
Step4までは1人でも実践できる内容でしたが、第三者から見て高い評価を受ける答案になっているか否かを自分で判断するには限界があります。
そこで答案の型が間違っていないか、説得的な文章が書けているか、の最終チェックとしてはやはり(指導実績豊富な)合格者による答案添削や個別指導を受ける必要があります。
我流で勉強を進める人も見受けられますが、試験直前になって「実は第三者から評価されない答案だった」と気づいても手遅れになってしまいます。そのため、早めに合格者からのお墨付きをもらうことが重要と言えます。
民法答案作成の流れ(まとめ)
1. 設問を丁寧に読み、当事者の請求を整理する
2.それを法律上の権利に引き直す
3.三段論法で要件を検討し、あてはめて結論を出す
4.相手方の反論も取り込んで検討する
5.過去問や演習で型を実際に使って練習する
おわりに
民法答案は、答案の型を意識すれば誰でも一定の形で書けるようになります。
大事なのは、最初から完璧な答案を書くことではなく、同じ型を何度も繰り返すこと。そうするうちに、論点の見落としも減り、答案の読みやすさも自然と向上していきます。
勉強を続けるなかで「自分なりの型」ができてくれば、それが合格答案への一番の近道になるはずです。

be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


