司法試験に受かるための勉強法【司法試験50位台合格者の学習戦略とは?】
2025年7月16日
お知らせ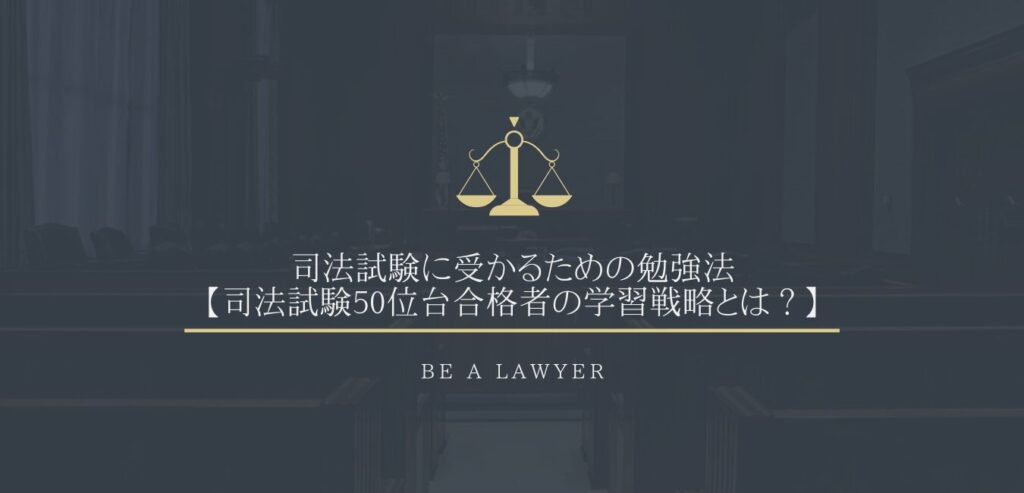
○論文
論文試験は司法試験のうち9分の8の点数の割合を占めており、メインで力を入れるべき試験です。内容として基本7科目+選択1科目の8科目ありますが、今回はその全ての一般的な勉強方法について紹介します。
1.過去問演習
論文試験を制する1番の方法は過去問を反復して潰すことです。世の中には沢山の演習本がありますが、本番試験のクオリティに勝るものはありませんし、敵を知ることが敵を倒すための近道です。過去問は問題だけでなく出題趣旨と採点実感が載っているため、問題作成者が何を考えて問題を作り、実際の答案をみて何を考えたかが載っている貴重な資料です。そのため、過去問を実際に起案して時間感覚や難しさを知り、出題趣旨や採点実感を読んで自分の答案の出来ばえを知ることができます。最初にやる作業として、何年の何の科目にどのような論点が出ていたかを表にまとめると、その分野の勉強をするときに出題趣旨や採点実感を利用して知識や書き方を学ぶことができます。また、出題趣旨や採点実感から論証を作ったり改造したりすることもおすすめです。
過去問を何年分やるかについては意見が分かれますが、周りの受験生に勝つという観点からは、本番まで1年など時間があるならば出来るだけ全年度やって、様々な出題範囲について学ぶほうが安心です。時間がない場合には過去最新の5年分、10年分などと区切り、全科目について取り組んでください。起案の時間すらないという場合には答案構成のみをして、出題趣旨・採点実感を見ることを繰り返せばいいです。
2.参考答案
自分で過去問演習をやることも大事ですが、他の受験生の答案とそのランクを知ることも大事です。過去の受験生が本番で書いた答案を再現した答案は、その具体的な点数やランクが出ているので非常に参考になります。出題趣旨や採点実感は優秀答案を想定にして書いていますが、そうでなくても合格ラインにある答案のレベルを知れば闇雲に上を目指さなくても合格に近づくことができます。また、不合格答案を見ることで何がアウトなのかを知ることもできます。参考として、辰已法律研究所の出版している「論文過去問答案パーフェクトぶんせき本」は科目ごとに過去の過去問の問題文・出題趣旨・採点実感・1年ごとに8通ほどの再現答案とそのランクが載っており、この本を使うことで過去問演習及び参考答案の勉強を効率的にすることができます。選択科目については、同じく辰巳法律研究所の「1冊だけで」シリーズがまとめているのでおすすめです。
3.基礎知識
こちらはインプットですが、司法試験に受かるための基礎的な知識や論点を知っていることは当然に重要です。ここで大事なのは、インプットの媒体を一元化することで手を広げすぎないということです。予備校のテキストや基本書など、自分の決めたインプット媒体を決めたら何回も周回して、それを隅々まで潰すのが最も効率がいい方法です。その過程で効率よく論点を知り、その書き方を学ぶための論証集を使うことも有用です。論証集については丸暗記にするのではなく、アウトプットの際に柔軟に変えることを念頭においてなぜそのような論証が生まれるのかの意味を考えることが重要です。
多くの合格者が使っていた基本書について下記にまとめたので、インプットにつまずいた際には参考にしてみてください。
・憲法
『芦部憲法』、『基本憲法Ⅰ・Ⅱ』
・行政
『基本行政法』
・民法
『民法(全)』、『潮見債権各論Ⅰ・Ⅱ』、『契約法新版』
・商法
『会社法(田中亘)』、「会社法(高橋美加ほか)」、『会社法〔第6版〕(LEGAL QUEST)』
・民事訴訟法
『民事訴訟法〔第4版〕(LEGAL QUEST)』
・刑法
『基本刑法Ⅰ』、『基本刑法Ⅱ』、『応用刑法Ⅰ』、『応用刑法Ⅱ』
・刑事訴訟法
『刑事訴訟法〔第3版〕(LEGAL QUEST)』、『基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編(基本シリーズ)』、『基本刑事訴訟法Ⅱ-論点理解編(第2版)』、『事例演習刑事訴訟法〔第3版〕』
4.百選判例の勉強
百選判例も基礎知識に含まれますが、重要な勉強として項分けしました。筆者は刑法以外の百選を重点的に潰して周回していました。科目によりますが、司法試験の論文試験では百選判例を元ネタにした問題が出たり、某百選判例との違いについて聞かれる問題が出たりするなど、確実に問題作成者が百選判例を意識していると思われます。また、百選は多くの大学の法学部や法科大学院で使用されており、その結果多くの受験生が使用していると考えられるため、潰しておいた方が遅れを取らないという意味で安心です。特に重要な科目として、憲法、行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、を挙げます。この中でも行政法、商法、民事訴訟法は過去問で大きく取り上げられている判例がある科目ですので、それにチェックをつけることで今後出る判例を予想することもできます。
5.模試
最後に、司法試験を受ける年には模試を受けることをおすすめします。模試は本番と同じ日程で問題を解くことができるので当日のスケジュール間隔を知ることができ、その結果から他の受験生の中の自分の立ち位置を知ることができます。
模試はTKC、辰巳法律研究所、LEC等で開催されていますが、会場が本番と同じ場所で模試を受けられるTKCがおすすめです。本番と近づいた方が自分が力を出せると思って遅めに受ける方もいますが、3月,4月の早い時期に模試を受けて早めに結果を知った方が軌道修正の時間が長くなりますし、未熟なまま模試を受けるのは他の受験生も変わらないため、筆者は3月のTKC模試をおすすめします。また、複数回受ける方もいますが、受験前に時間が取られてしまうこともあり1回で十分だと考えています。
○短答
短答は侮られがちですが、全得点の9分の1の割合を占めています。短答で高得点を取ることは合格推定が働き合否までの過ごし方にも影響を与えます。実際、1点変わるだけでも順位が20位近く変わることもあり、論文より確実に点数をとれる短答を少しでも上げることは合格への近道といえます。
・過去問(全科目)
こちらも論文と同様に、やはり過去問演習をすることが1番重要です。過去問演習の媒体は問いませんが、何回も何回も演習することで問題のコツや出方を知りましょう。この時、問題をやりすぎて覚えてしまっては無意味なので気をつけましょう。何回やっても絶対に間違えないという問題があれば、その問題にマークをつけるなどして苦手な問題に絞っていくと本番前にそれだけやれるので効率よく演習できます。
・条文(民法、憲法統治)
民法、憲法のうち統治は条文の勉強が重要になってきます。まず、民法は論文の勉強がそのまま生かされる科目ですが、条文がそのまま問題になっている場合が非常に多く、満点を狙える科目といっても過言ではありません。実際筆者は民法の素読を行ってから点数が伸び、本番は9割近くを取ることができました。1000条以上ある民法の条文を全て読むのは大変ですが、毎日夜寝る前など地道に少しずつ読んでいって周回するとスルスル解けるようになり非常におすすめです。次に憲法ですが、憲法は統治の問題で条文問題が問われることが多く、それに備えて条文の素読を行うのがおすすめです。民法とは違って憲法の統治は普段論文で勉強しないところですので、過去問演習と同時に素読して頭に入れることをおすすめします。
・論文の勉強(民法、刑法、憲法人権)
全ての科目では論文分野と試験範囲が被るため、論文の基礎知識がそのまま短答式試験にも生かされます。そのため、論文のための勉強をすることが短答のための勉強にもなります。短答の過去問を演習する際に必要なレベルの知識が見えてくるはずですので、論文のための基礎知識の勉強の際に同時に短答のための勉強となるように意識してみてください。
○総評
残念ながら、司法試験に受かる絶対の近道や飛び道具はありません。
これまで受かってきた全ての受験生が地道な勉強をしていることに間違いありません。ただ、今回はその中でも多くの受験生がやってきた再現性のある勉強方法をわかりやすくまとめたので、是非ともこれを活かして合格へと近づいて欲しいです!
be a lawyerの公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信しております!よろしければご登録ください!


