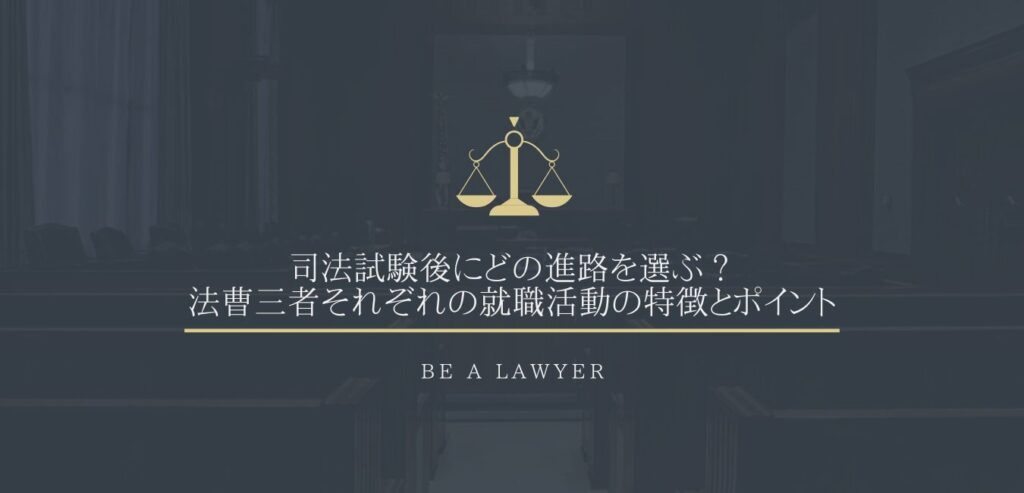
こんにちは、be a lawyer講師のHMです。
法曹の就職活動は一般就職と似ているようで違う点がたくさんあります。今回は法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)の就職活動それぞれについて紹介します。
1.弁護士
弁護士の就職活動は一般就職と似ており、基本的には弁護士事務所や一般企業、官公庁が弁護士を募集しているため、それに応募して面接等を経て内定が出るという流れを経るのが基本となります。
弁護士募集の一次媒体は弁護士事務所や一般企業、官公庁のホームページとなり、そこからフォームを入力したり履歴書を提出したりすることで応募が可能となります。応募している事務所を載せている求人サイトとして有名なのはアットリーガル、ロイヤーズインフォ、弁護士ドットコム、ひまわりサイトなどがあります。特にどこの事務所に行きたいなどと決まっていない場合でも、このような求人サイトを毎日更新して出てきた事務所の応募要綱を見てみるというのも手の一つと思われます。私は特に企業法務に興味があったので、インターンを探すためにロースクール1年目の春から夏は毎日アットリーガルの「在学生サマクラ募集情報」をチェックしていましたし、就活対策のページを読んで相場感を掴むようにしていました。そして、ロイヤーズインフォで事務所の口コミや評判を見たり、合同説明会の情報を得たりすることもありました。ロイヤーズインフォは情報格差をなくすためのサービスなので、特に情報が欲しい方は詳しく見るのがおすすめです。また、そもそも募集していない事務所だとしても、ダメ元で連絡をしてみて話を聞いてみたり就職希望であることを伝えたりすることも方法の一つです。
弁護士事務所の中でも企業法務系事務所や規模が大きめの事務所の就職は現在非常に早期化しているので注意が必要です。早い場合には司法試験を受ける半年以上前に内定が出ている場合もあり、基本的に内定の枠は早い者勝ちなので、かなり早期から情報収集をして自身の希望を固める必要があります。また、事務所が公式に募集を始める前という早期に内定をもらうためには、インターンに行くことが必要なこともあります。予備試験ルートで司法試験を受ける方は、短答式試験の合否が出た後には短答式試験合格者向け、論文式試験を受けた後にはもう予備試験論文受験者向けのインターン募集が始まっている場合があるので、応募しましょう。予備試験ルートの方は特に勉強しなければならない時期や試験直後に応募しなければならず、休む暇がなく大変なので、あらかじめ証明写真(写真機ではなく写真館で撮るのがおすすめです)や一般的な履歴書(事務所によって形式指定されることも)、志望理由や学生時代に力を入れたことについて書いて用意しておくことが大切です。ESの書き方については別の記事で紹介する予定ですが、ブラッシュアップを複数繰り返すのが通常なのであらかじめ用意する方がいいです。そして、法科大学院ルートで企業法務を狙う方は、未修1年次及び既修1年次の夏休みや春休みにインターンに行き、司法試験前に内定もらったり司法試験後に本格的な面接を経て内定をもらったりするケースが多いです。そのため、3〜7月には上記の求人サイトを見て応募をし、夏休みにインターン、11〜1月に応募をして春休みにインターン、(もらう人はインターンから司法試験前後の間に内定)、司法試験後に正式な募集及び面接をして内定、という流れになります。インターンによって日当・交通費の有無・制限、日数、内容は非常に様々なので、募集要項をよく読んでから応募しましょう。
上記で紹介したのは企業法務系や規模の大きめの事務所で早期の就職活動の場合ですが、一般民事・刑事系の事務所や比較的規模の小さな事務所は司法試験終了後・合否発表後から始まることがほとんどです。修習中に就職活動をしている人もたくさんいますし、上記のように早期に就職を終えているパターンがあったとしても全く焦る必要はありません(修習のうち弁護修習で配属された事務所にそのまま就職する方もいるとか)。
次に、組織内弁護士(インハウス)について紹介します。組織内弁護士は主に一般企業や官公庁という組織の中で働く弁護士であり、法律事務所の中にあっても独立した地位にある弁護士とは異なります。一般企業の法務部等へ就職する場合は、一般就職と同様にTOEICやSPIのスコアが必須の場合があるため注意が必要です。法律事務所を挟まずにいきなりインハウスに行く弁護士はいまだに珍しいとされていますが、インハウス弁護士を望む企業は多く、ロースクールでの説明会も開かれていることがあるため、話を聞くことが大事です。また、法律事務所からインハウスに移る場合は、エージェントを経由して面接を経ることが多いようです。
2.裁判官
裁判官の就職活動は、司法試験後の修習の中で全て行われる特殊な内容になっています。修習では、修習生が修習地によってクラスに分けられ、そのクラスごとに民事裁判教官、刑事裁判教官、検察教官、民事弁護教官、刑事弁護教官の5人の教官がおり、主にはこのうちの裁判教官が裁判官のリクルートを行うことになります。リクルートの仕方についてはグレーゾーンな部分が多いですが、志望度が高く、修習に意欲的に取り組んでいる優秀な人物がリクルートされる可能性は高いです。そして、修習のカリキュラムとして、①導入修習②実務修習③選択型実務修習、④集合修習(③④は逆の場合あり)とありますが、このうち②の中である「問研起案」で良い成績(ABC評価のうちA)を取ることが大切と言われています。問研起案とは修習の修了試験である二回試験の模擬試験のようなもので、民事裁判・刑事裁判・検察の各クールで1回ずつ行われるものです。
裁判官の場合は総合的な優秀さが必要と言われるため、全ての科目でAを取ることを目標とするべきです。司法研修所から与えられらる白表紙という資料をよく読み、問研起案や二回試験の対策としてまとめられた資料が代々使われているのでそれを人から貰うなどして勉強するのが主な対策です。そして、実務修習中に行う起案(犯人生の認定や和解条項の作成などをします)に積極的に取り組み、リクルーターである裁判教官に裁判官を希望していることを率直に伝えた上で面談を重ねることも大事です。また、実務修習では結果簿といって日々の修習で行ったことを記すのですが、それをしっかりと書くことも大切です。
さらに、これは噂レベルなのですが裁判官になるにあたっては司法試験の順位も見られている可能性が高いので司法試験で出来るだけ良い順位を取るように努力するのも手の一つです。
3.検察官
検察官も裁判官と同様に、修習において教官のリクルートを受けて任官することになります。検察官の場合は任官にあたって実務庁から推薦を受けることが必須となるため、実務修習での修習によく取り組むことが1番重要です。そして、上記の検察教官からプレゼンを受けることも必要なため、教官との面談では検察志望である旨をアピールして飲み会の場などでコミュニケーションを取ることも大事です。
ちなみに、実務修習の私の里親検事は、修習で幹事や挨拶係などまとめ役を行うことも大事だと言っていました。そして、検察の場合も問研起案があるのでそれで良い成績を取ることももちろん重要になります。検察の場合は起案に決まった型があるので、白表紙やテスト対策資料を勉強することで型を覚えて付箋をうまく利用しながら解くのが対策になります。
法曹の就職活動は以上になります。
法曹三者といっても、弁護士の場合は法律事務所だけでなく組織内弁護士、さらには即独といっていきなり独立するケースもあり、その分岐は様々です。本当に自分に向いていること、やりたいことは何かを見極めるためにも様々なルートを調べてたくさんの人の話を聞いて決めてみてください。
be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信しておりますのでぜひご登録ください。


