【司法試験超直前期の過ごし方】試験前にやるべきこと・やるべきではないこと3選(2025年版)
2025年7月12日
お知らせ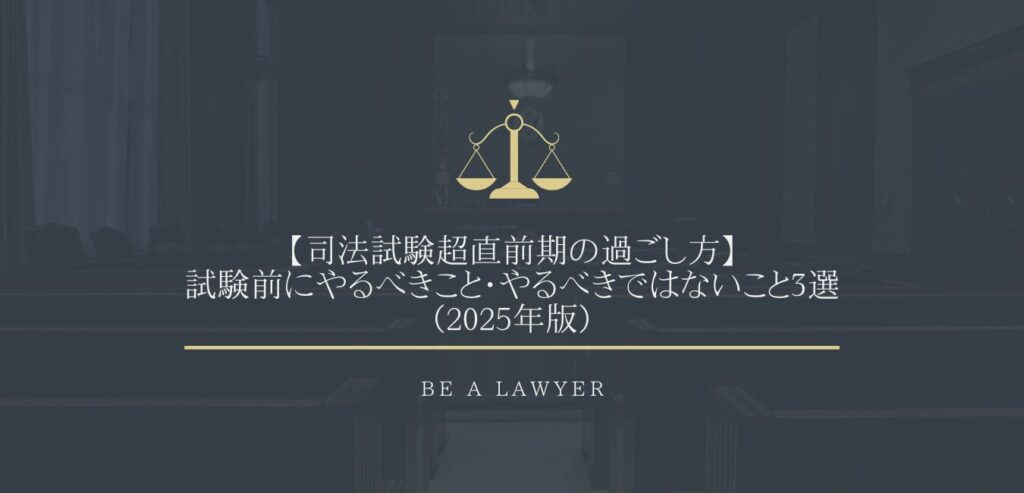
令和7年度司法試験まで残りわずかとなりました。これまで積み上げてきた知識やスキルを「答案として出力できる形に整える」ことが、この時期の最大の目標です。しかし、プレッシャーや不安で学習効率が下がったり、やるべきことを見失ってしまう受験生も少なくありません。
本記事では、司法試験超直前期における効果的な学習法・過ごし方・メンタル管理法を徹底解説します。合格を掴み取るための最終調整にお役立てください。
1. 司法試験超直前期にやるべきこと3選
(1) これまでに書いた答案・模試の復習
直前期に新しい知識を詰め込むのは非効率です。そして、これまでやってきたことを本番で発揮することが重要となります。そのため、これまでに書いた過去問や受けた模試に絞って徹底的に復習を行いましょう。例えば、これまで一度解いたことのある問題をもう一度解き直して120分の時間制限内に処理ができるかを最終確認しておくのも良いと思います。これまでの復習をする中で理解に不安が残る論証があれば再度確認しておきましょう。
(2) 短答式試験対策
短答式試験は直前まで点数を上げることができるため、試験直前まで徹底的に過去問演習を繰り返しましょう。これまで間違えたことのある過去問に的を絞って最後にもう1周回してみるのも良いでしょう。
(3) 睡眠と生活リズムの調整
試験直前期はとにかく規則正しい生活を心がけてください。焦る気持ちは分かりますが直前期に無理をし過ぎてしまい、試験当日体調を崩して実力を発揮できないと本末転倒です。あまり長時間勉強をせずに体調管理を最優先しましょう。
2. 司法試験超直前期にやるべきではないこと3選
(1) ❌新しい教材に手を出す
→ 「あれもこれも」と広げるより、今まで使ってきた教材を復習することで深い理解が得られます。新しいものに手を出すとうまく消化しきれないままに本番に臨まざるを得なくなり、結果といて不安を煽るだけです。
(2) ❌ 他人と比較して焦る
→ SNSや予備校の成績など、他人の状況に惑わされすぎると、自分の学習リズムが崩れます。SNS上には「優秀そうな人」が多いように感じることもあるでしょうがその真偽は不明です。「昨日の自分」だけをライバルにしましょう。
(3) ❌ 本番に向けた準備を後回しにする
→ 試験会場までの経路確認、持ち物リストの作成、模擬試験の受験票準備など、事務的なことも早めに済ませるのが安心です。
試験当日は渋滞や公共交通機関の遅延などのリスクも踏まえて早めに家を出て試験会場付近で時間を潰しましょう。
3. 試験本番までのメンタル管理法
司法試験超直前期は、不安や焦りからメンタルが低下しがちですよね。そこで必要なのが、自分なりのメンタルコントロール法です。
(1) 答案に完璧を求めすぎない
→現行の司法試験の合格率は40%を超えており、点数で言えば全科目で50点を取れば合格できます。確率論でいえば、両隣の受験生に勝てば合格です。その意味でいえば司法試験では完璧な答案は求められておりません。
あなたが分からない問題にぶち当たった時は両隣の受験生も分からない可能性が高いです。焦らず冷静にあなたがこれまで学習してきた知識の中から書けることを淡々と書いていきましょう。
(2) これまでの努力や成果を振り返り自信を持つ
→これまであなたがやってきた勉強に自信を持ちましょう。仕事、家族、趣味等の時間を犠牲にして勉強に打ち込んできた方は少なくはないと思います。あなたがやりたいことを我慢してこれまで行ってきた努力はあなたを裏切りません。自分を信じて、本番で存分に力を発揮してください。
(3) 「できることに集中する」マインドを持つ
→司法試験ほどの膨大な出題範囲の試験において全ての論点の理解を完璧にすることはおよそ不可能だと言えます。ですが、これまであなたが法学部、ロースクール、予備校で学んできたことの理解の精度を上げることは可能です。これまでにやってきたことに焦点を絞り、できることをやって本番に備えましょう。
4. 試験当日に意識すべきこと
(1) 分からなくとも焦らないこと
司法試験の問題は非常に難易度が高いです。それが8科目もあるのですから分からない問題があって当然です。分からない問題が出たときは問題文の事実や誘導にヒントが落ちていないか入念に読み込んでこれまであなたがやってきた勉強の中から何か使えそうな判例がないか検索してみてください。
(2) 絶対に途中答案にならないよう時間配分に留意すること
途中答案はそれだけで「時間内に処理ができなかった受験生」と採点官の心証を悪くする代表例の一つです。論述が多少薄くなっても構わないのでなんとしても最後まで書き切ってください。
(3) 設問の指示に忠実に従うこと
「A県の反論を踏まえて〜」、「参考判例に言及しつつ」、「〇〇の代理人の立場に立って〜」等、司法試験の問題には指示があることが多いです。これは出題者からのメッセージであるため必ず従いましょう。設問の指示に従っていない答案はこれも「設問の指示に従えない受験生」と採点官の心証を悪くしてしまいます。設問に指示がある場合には見落とし防止のため蛍光ペンや赤ペン等で目印を付しておくと良いでしょう。
(4) 現場思考問題こそ法的三段論法を徹底すること
司法試験の問題の中には前例がないような現場思考型の問題が出題されるケースがあります。現場思考型の問題はどの受験生にとっても初見の問題となるため焦る必要はありません。現場思考型の問題については周りの受験生もそれほど高度な法律論を展開できるわけではないからです。そのため、とにかく法律の基礎である法的三段論法を忠実に守りつつ、問題文の事実を拾えるだけ拾って結論を導くことを意識してみてください。それだけでも大事故は防止できます。
(5) 特定の科目・設問が出来なくても不安にならないこと
言うまでもなく司法試験は8科目の論文試験と短答式試験の合計点で合否が決まります。1、2科目くらい出来が悪い科目があっても合否には大きくは影響しません。出来ない科目や設問があっても振り返らず次の科目の準備を怠らないようにしましょう。
5. まとめ:直前期は「やることを絞る」が鍵
司法試験の直前期は、全てを完璧にしようとするのではなく、「やるべきことを絞る」ことが重要です。
✔︎ 新しいことに手を出さずにこれまでやってきたことに絞って復習を行う
✔︎ メンタルと生活リズムを整え、本番で最大限のパフォーマンスを発揮できるよう備える
✔︎ 他人に惑わされず、自分のやるべきことに集中する
どんなに不安があっても、これまでの努力は確実にあなたの力になっています。最後まで自分を信じて本番で力を発揮してください。

be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


