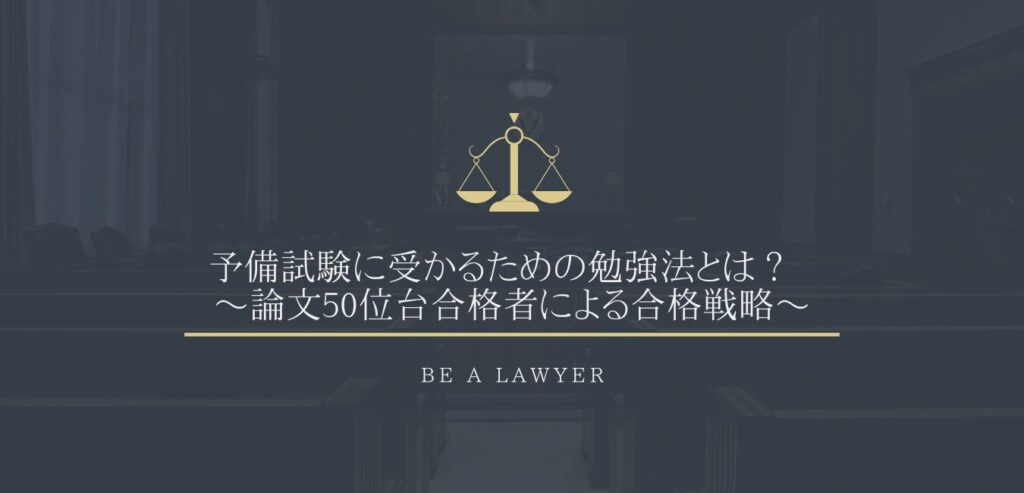
1 はじめに
こんにちは、be a lawyer講師のM.Hです。今回は予備試験に論文試験50位台、口述試験20位台で合格した私自身の経験を踏まえ、効率的かつ戦略的に予備試験に合格するための勉強法について解説させていただきたいと思います。
予備試験は、短答式・論文式・口述式の3段階からなる試験で、どれか一つでも対策を誤れば突破は難しくなってしまいます。では、限られた時間とリソースでこの難関試験を突破するにはどのような勉強法が有効なのでしょうか、以下解説していきます。
2 短答式試験の勉強法
(1) 短答式試験への向き合い方
短答式試験の勉強法は人によって大きく異なります。なぜなら、270点満点中、60点を占める「一般教養科目」で取れる点数が人によって大きく異なるからです。国立大学の学部生などが40点近くをとる一方で、平均点は20点前後にとどまります。例年、1点の上に何十人もの受験生がいることを考えれば、これが大きな差だということが分かるでしょう。そこで、まずはご自身が一般教養科目でどれくらいの点数を取れるのか見極めることをお勧めします。その上で、短答の学習に割く時間を決めてください。例えば、一般教養科目で高得点の獲得が見込める人は、正答率の高い問題に絞って過去問を解いても問題ありません。一方で、それ以外の人は、よほど現在の問題と傾向の違う問題以外は全て解いておくのが安心と言えるでしょう。
使用する教材としては、受験生の多くが使用しているのが、辰巳法律研究所の「短答過去問パーフェクト」ですので、7科目全てでこちらを使用することをお勧めします。
(2) 短答パーフェクトの使用例
同教材の使用法として、参考までに私の使い方をご紹介します。
私の場合、記号式の問題に苦手意識があったことと、一般教養科目でどれくらいの点数を取れるのか読めなかったことを踏まえ、短答の学習にはそれなりに時間を取ると決めていました。その上で、出来るだけ効率的に問題演習を行うことができるよう、情報の一元化を行うため、全てを短答パーフェクトに集約することにしました。
短パフェは、表のページに問題があり、裏のページに解答・解説があるという仕様になっています。これを何周も回していくにあたって、いちいちページの表、裏をめくって確認するのは時間がかかりますので、赤シートで隠せる色のペンを使用して、表のページに答えを書き込みました。そして、正誤に関わらず、解答の根拠を自分で言うことができなかった問題については、裏ページの解説を参考にしながら自分の言葉で根拠をまとめて、表ページに書いておきます。これで自分のための問題集が完成するので、2周目以降はひたすら表ページを見て、赤シートで答えを隠しながら解いていけば足り、余計な時間を使わなくて済みます。誰に見せるわけでもないので、解答の根拠は自分が分かるような簡潔な言葉で書きましょう。短答式試験では、過去問と同じ問題が幾度も出題されますが、出題の形式が毎回同じとは限りません。同じ知識でも、さまざまな角度や表現で問われることが多いのです。したがって、事前の勉強で重要なのは、その問題に正解したか否かではなく、解答の根拠を言えたか否かなので、この点の学習こそ、気を抜かず丁寧に取り組んでください。
3 論文式試験の勉強
・総論
予備試験の中でも、最も合格が難しいとされているのが、論文式試験です。多くの受験生が、勉強時間の大半を論文式試験対策に割くことになります。
毎回4ページにわたる起案をする時間は取れないため、主な勉強方法は答案構成になります。初学者の段階では、答案構成も難しいと思いますが、短期間で2〜3周するうちに徐々に感覚が掴めてきます。感覚が掴めるまでは、同じ科目を集中的に繰り返すことが重要です。最初に取り組む科目としては、商法や刑事訴訟法が良いでしょう。出題される範囲がある程度決まっており(いわゆる「典型論点」が多い。)、答案構成のコツを掴みやすいです。
・憲法
憲法は答案の型が比較的明確に決まっている科目ですので、まずはその型の暗記をすることから始めましょう。ここで、単なる形式の暗記にとどまらず、「適合性」、「必要性」といった用語の意味をきちんと理解することが重要です。さらに、予備試験の憲法の問題は、問題文が非常に長いです。問題文に示された具体的な事情を、どの要件の中で使うべきか、瞬時に判断ができるようになるまで、問題演習を繰り返しましょう。
・行政法
行政法は、基本的には処分性/原告適格の問題が交互に出題されるため、この2分野の学習がメインになります。どちらも論証が長く、規範の意味も分かりにくいので、正確な暗記と当てはめの練習をいかに丁寧に行うかが合否の決め手となります。
・民法
予備試験の民法はその出題範囲が非常に広く、典型論点を押さえただけでは太刀打ちできないことに注意する必要があります。基本書や予備校の基本テキストをよく読んで理解し、未知の論点が出題されたときも、ある程度対応できるようにしましょう。
・商法
商法は、条文数が非常に多いため、まずは条文操作の訓練から始めることが大切です。条文の所在や構造を理解しておかないと、問題演習を通じて知識を定着させることも難しくなります。また、商法は典型論点の出題頻度が高く、パターンもある程度決まっているため、論点ごとの知識を正確に暗記し、すぐに書き出せるようにしておくことが得点の鍵になります。したがって、条文理解と並行して、論証の暗記にも時間をかけましょう。
・民事訴訟法
民事訴訟法は、手続の仕組みを前提とした抽象的な概念が多いため、まずは「既判力」といった基本用語の意味を正しく理解することから始めましょう。制度趣旨や手続の流れをイメージしながら学習することで、問題文の事情との関係も見えやすくなります。規範力や複数当事者がメイン論点となる問題では、問題文の事実関係を図にまとめる作業が非常に有効です。
・刑法
刑法では、まず構成要件の把握が基本になります。各論点が、犯罪成立要件のどの段階(構成要件該当性、違法性、責任など)に属するかを常に意識しながら、知識を整理・暗記していきましょう。この「位置づけ」の意識があるかどうかで、答案の論理性が大きく変わってきます。また、共犯等の複雑な論点は、理解に時間がかかる分野です。知識の暗記だけでなく、何度も答案構成や論証練習を繰り返すことで、理解を深めていく必要があります。初見の事案にも対応できるよう、類似パターンでの練習量を意識して積み重ねましょう。
・刑事訴訟法
刑事訴訟法は、典型論点が頻出であり、誰もが対策をしてくる分、差がつきにくい科目とされています。だからこそ、典型論点の処理を「正確」かつ「瞬時に」できるようになることが合格の鍵です。そのためには、論点ごとの当てはめの練習を徹底することが重要です。捜査手続や伝聞法則、訴因など、それぞれの場面に応じた論証・判断枠組みを確実に身につけることで、安定した得点が見込めるようになります。
4 口述式試験の勉強法
・総論
口述式試験の大きな特徴は、合格発表から試験当日までの期間が非常に短いという点です。理想としては、論文式試験が終わった段階から準備を始めておけると良いのですが、実際には気力が尽きていてなかなか手がつかないという人も多いでしょう。そのため、残された1か月弱の期間で、いかに効率的に学習できるかが非常に重要になります。
・民事系の対策について
民事系では、まず大島本を繰り返し読み込み、特に事例問題については、問われた内容に口頭で答えられるようになるまで繰り返し練習しました。
手続法の分野については、短答対策時に自作したメモを使って全体像を再確認しつつ、重要な条文は素読や暗記で対応しました。民事執行・保全に関しては市販のテキストを使用し、抜けがないように薄くカバーしました。また、民法や民訴については、口述で論文レベルの知識が問われる可能性もあるため、論証集を軽く一周して、ざっくりと復習しておきました。特に「典型論点が聞かれたのに答えられない」ことを避けるため、全体を網羅的に見直しておくのが安心です。
・刑事系の対策について
刑法では、まず『基本刑法 各論』の設問を一通り解き直し、特に出題されそうだと感じた項目については、設問だけでなく本文も読み込み、理解を深めるようにしました。
刑事訴訟法については、短答対策時に作成したまとめノートを活用して細かい知識を確認しつつ、全体像の把握には『刑事実務基礎の定石』を用いました。逮捕や勾留といった重要な手続や、過去問で繰り返し問われている条文については、丸暗記して即答できるようにしておく必要があります。また、論文試験の知識も問われる可能性があるため、論文対策で使用していた予備校の論証集で典型論点を復習しました。加えて、法曹倫理については条文を素読し、条文番号や趣旨を自然に口に出せるようになるまで確認を重ねました。
5 終わりに
予備試験は確かに難しい試験ですが、正しい方向へ向かって継続的に努力をすれば、合格も決して不可能ではありません。本記事で紹介した勉強法をもとに、自分に合ったスタイルを見つけてみてください。日々の積み重ねが、やがて大きな成果となって返ってくるはずです。
皆さんの合格を心より応援しています。
↓初回無料面談はこちら↓

be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


