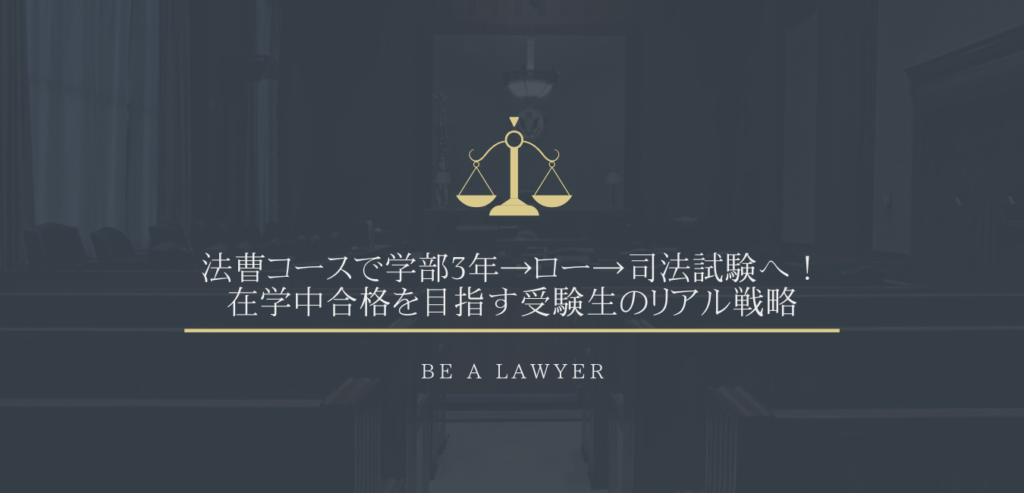
はじめに
こんにちは、be a lawyer講師のAIと申します。
私は都内私立3卒→都内国立ロー在学中受験で令和6年司法試験に合格(1000位台)しました。
今回は、在学中の受験生や早期卒業でロースクール入試をご検討されている方向けに、早期卒業から在学中受験で司法試験に一発合格するための学習戦略をご紹介したいと思います。よろしければご覧ください。
早期卒業(法曹コース)により、学部3年間で法律科目を中心に必要単位を取得し、ロースクールに既習で入学して、2年目の7月に司法試験となります。学部試験、ロー入試、司法試験と内容が重なる部分があり中間目標を立てやすい一方で、司法試験では短答があったり、ロー入試では書類審査があったりなど、時期により対策が異なることから、戦略的に学習する必要があります。そこで、まずは、私の学習スタイルをざっくりとご紹介し、学部時代とロー時代に分けて、学習方法を詳細に書かせていただきます。
学習スタイルについて
これは何のために行っているのか、目的を意識し、勉強用のメモに書き留めていました。ただ読んでいるだけ、書いているだけという、時間の無駄を防ぎたかったからです。メモなので、細かく書く必要はないですが、1か月単位、1週間単位で、タスクを列挙すると自分のモチベも上がります。また、何か(論証や短答知識)を覚えた際には、数時間後、数日後に人に説明できるかということも、意識しました。私の場合、論文ゼミは組んでおらず、独学であったため、周囲に法律の知識を有しない人がいると仮定していました。論文添削も単発で数回ほど受講した程度で、ほとんどが自己添削でした。添削を講師の方などにお願いすると客観的に評価していただけるというメリットがある一方で、返却までの間に、既に問題内容を忘れ、なぜその書き方になったのかのプロセスを思い出せない傾向にありました。また、ある程度の参考答案はネットで入手できました。以上の理由から、自己添削が多くなりました。自己添削では、参考答案や解説と比較して、足りなかった知識、使いたいキーワードや条文、順序などを意識して、採点者になったつもり学習しました。
学部時代の勉強法
学部1年から法律科目の履修があったので、学習を始めましたが、授業レジュメからのスタートでした。法律用語の慣れという意味で、1週間ごとに進み、薄くまとまっているので丁度よかったです。そして、予備試験受験の有無にかかわらず、短答の勉強もするべきだと思います。分厚い問題集に抵抗がある方は、薄めのものでも良いです。たしかに短答プロパーという言葉もあり、短答のみで論文の実力がつくことはあまり期待できないと思います。しかし、民法や商法では、短答の直しで条文を確認することでその趣旨を考えたり、具体的事情のあてはめを想定したりします。この過程で、論文対策と兼ねることができます。また、刑法の学説対立問題などは、短答で触れた経験が論文での立場が指定される設問において大きく役立ちます。論文対策は、ネットにある論証集や書店で気に入ったものを使いました。全科目をそろえなくても良いと思います。私の場合は、学部1年次に、民法及び憲法のえんしゅう本を購入し、直前期まで使用しました。学部2年次の夏には、7科目の全範囲をざっくりと終えていたので、予備試験論文の過去問にチャレンジしました。やはり良問がそろっており、70分で解くものなので量も適していると感じたからです。また、学部3年次には刑訴のエクササイズ(薄いが網羅的にまとまっている)と行政法の基礎演習を買いました。これらの演習書では、論文の型を身に着け、知識も広げるイメージを持って取り組みました。完全に答案構成をしたり、プロセス過程をすべて示したりする訳ではなく、インプットした条文や要件・効果を確認する程度でした。解説を読む際に、付箋にまとめたり、レジュメ(場合によっては基本書)に戻ったりしました。
学部試験はGPAを軽視してしまうと、ロー入試を突破できない可能性が高まりますし、そもそも書類の段階で足切りにあい、筆記にチャレンジできないことになります。GPAは、意外にも法律科目で最優秀の評価(いわゆるS~CのSやA~DのAなど)が取れないこともあります。そこで、法律科目以外の科目(特にレポート科目や語学)は、準備をしました。期末は年2回ですし、レポートであれば参照できるので、法律科目の勉強と並行していました。
ロー入試の過去問に着手したのは、学部3年次の6月でした。これは、形式に慣れることと論証を使いことなせるかのチェックが目的でした。形式に慣れるとは、時間配分や問の数、民法であれば家族法の出題の有無など、特徴を掴むことです。論証の使いこなしは、論証を示すだけでなく、問題文のいかなる事実からその論証が必要になるのか、あてはめで拾うべき事実は何なのかなども含みます。私の場合、ちょうどこの時期から自作論証集を作り、wordに打ち込んでいました。それぞれの科目で、問題文の誘導への乗っかり方、現場思考問題に対する確認順序、形式など過去問から学べることは多いです。論文では、あてはめのストックや規範のチェックに集中しました。ロー入試の過去問は参考答案がネットにアップされていることがあります。また、参考答案のアップがなくとも、公式サイトで出題趣旨が掲載されていることもあります。過去3年分ぐらいは、答案構成をして実際に起案しました。試験時間も意識はしますが、科目によっては延長して書ききることもありました。2回目に解く際は、時間節約のため、答案構成のみになることもありました。
ロースクール時代の勉強法
入学すると、予習復習に追われ自分の学習時間を作る余裕や体力がなくなりました。というのも、周囲のレベルが高く、ローのソクラテスに自信がなかったこと、定期的にレポートの提出や発表が求められることなど、バタバタした生活となったためです。授業の予習は最低限に抑えること(自分が指名されるときだけ答えるようにしておく)は、よく言われると思いますが、ある程度は基本書のページをメモするだけにするなど、濃淡をつけることが鍵となります。他方で、授業が全く司法試験に役立たないかというとそうでもないので、科目や先生によって、利用できる部分を見極めて、自分スタイルを構築するのが良いです。私は、「判断枠組みは~」「~な事実は、抽出しましょう」などの先生の説明は聞いていました。それ以外の議論の際は、何となく聞いたり、別の内職をしたりしていました。
短答と論文の学習配分(1週間あたり)ですが、ロー1年目の冬までは1:2、直前期(本番4か月前から)は1:1ぐらいの割合で学習しました。短答は直前に詰め込めば何とかなるとの意見もありますが、上記のように短答の学習意義も感じていたので、ゼロにするということはありませんでした。短答に定期的に触れることで知識が身につくことはもちろんですが、学習計画の迷いを回避することになります。例えば、①民法は家族法分野で満点を取りたいから直前に集中させ、今の段階では物権と債権に集中させる、②刑法は早く正確に解き満点を目指す、③憲法は統治の典型問題はスラスラ解き、人権は判旨の要約と反対意見を押さえるなど、戦略を立てることになります。直前期や本番期間に何をやろう?どの分野を復習しようという、緊張や不安からくる放心状態を最も恐れていましたが、実際には戦略のおかげで回避できました。
論文の学習では、上記のえんしゅう本でチェックすることもありましたが、ロー1年目の夏休みから司法試験の過去問も利用しました。過去問は問題が長く、検討と起案、解説の読み込みをフルで行うと、ほぼ一日かかってしまうので、科目によっては設問1だけにするなど、軽く触れる程度でも良いです。優先順位が高いのは、令和の過去問ですが、ロー2年目の春休みには、平成25年までさかのぼりました。
それぞれの科目で、問題文の誘導への乗っかり方、現場思考問題に対する確認順序、形式など過去問から学べることは多いです。論文では、あてはめのストックや規範のチェックに集中しました。これらの使えるフレーズは自作論証集にいれていました。
このようにある程度、学習リズムを身に着けてしまえば、淡々とこなしていくだけなので、意外と本番まで続けることができます。受験生の皆様を応援しております。
be a lawyerの公式LINEでは司法試験・予備試験受験生向けに有益な情報を発信しています!友だち登録はこちら↓


