令和6年司法試験行政法の優秀答案とは?(論文50位代合格・評価A)
2025年4月1日
司法試験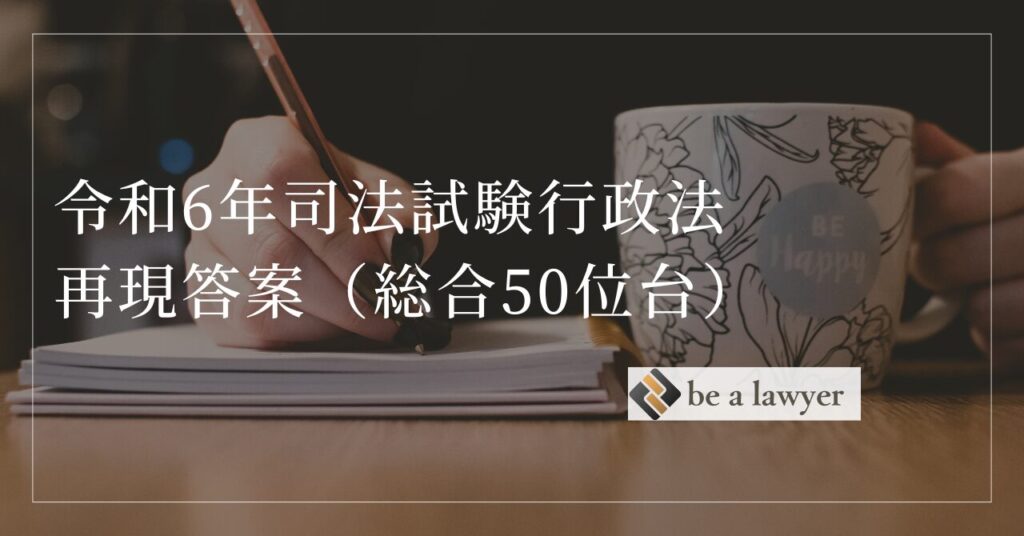
こんにちは、be a lawyer編集部です。
今回はbe a lawyer所属講師の令和6年司法試験の参考答案を掲載いたします。上位合格者の答案から学べることは多いと思いますのでぜひご覧ください。
【令和6年司法試験行政法 再現答案(評価A・論文50位代)】
第一 設問1小問(1)
本件事業計画変更認可は取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項かっこ書)に当たる。以下、説明する。
1 「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。考慮要素は公権力性と直接・具体・法効果性である。
2 本件事業計画変更認可はQ県知事が法38条1項、2項、17条柱書を根拠とし、優越的地位に基づいて一方的に行うものである。
本件事業計画変更認可は、B組合が本件都市計画変更を受けて、平成28年認可に係る事業計画を変更すべく、法38条1項をもとに事業計画の変更の認可を申請したことに対して行われたものである。B地区組合は組合施行による第一種市街地再開発事業(都市計画法12条4号)において、B地区を「施行地区」(法2条3号)として設立された市街地再開発組合である(法11条1項)。そして、平成28年認可はB地区を施行区域とする第一種市街地再開発事業に関する都市計画についての認可であるところ、今回B組合は施行地区にC地区を編入する本件都市計画変更を行っている。
第一種市街地再開発事業においては、原則施行地区内の宅地の所有者に対し、それぞれの所有者が有する宅地の価額の割合に応じて再開発ビルの敷地の共有持分権が与えられ、当該敷地には再開発ビルを建設するために地上権が設定され、当該敷地の共有者には、地上権設定に対する補償として権利床が与えられることになっている。これを、事業施行前における宅地の所有権が区分所有権等に変換されたという意味で権利変換というが、認可を行った後は法19条1項の公告手続、法71条の期間の経過後、権利変換計画の決定及び認可(法72条)が行われる。そうすると自動的に権利変換処分が行われる(法86条1項、2項)ため、施行地区内の宅地所有者等は権利変換処分を受ける義務を負うといえる。さらに、法71条1項は宅地所有者等に対して権利変換を希望しない申出によってこの処分を受ける義務を免れる手段を設けており、その点でも法が右所有者等に法効果が具体的に及ぶことを前提としているといえる。そのため、この本件都市計画変更を認可する本件事業計画変更認可は直接、具体的に、施行宅地内の宅地所有者の権利変換処分義務を負わせるという点で法的な効果を及ぼすものといえる。
以上より、本件事業計画変更認可は処分にあたる。
第二 設問1小問(2)
本件事業計画変更認可が違法であることについて、Dとしては①法16各項の手続に瑕疵があること、②都市計画法13条1項13号の実体的要件を満たさないこと、③法3条4号の実体的要件を満たさないこと、の3つの事項を主張することが考えられる。以下、説明する。
1 ①について、法16条1項は「第11条第1項(中略)の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ」ること、同条2項は施行地区の関係者について「縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる」としている。しかし、今回Q県知事はR市長に事業計画の縦覧及び意見書提出手続を実施させなかったため、手続き上瑕疵があるとも思える。
しかし、法38条2項は事業計画の変更の認可の申請があったときに政令で定める軽微な変更を除いて法16条を準用するとしている。そして、都市再開発施行令は各号について軽微な変更について定めているところ、本件の事業計画の変更は都市計画の変更に伴う設計の概要の変更(1号)、事業施行期間の変更(3号)、資金計画の変更(4号)には当たらない。また、2号は「施設建築物の設計の概要の変更」だが、施設建設物はいわゆる再開発ビルを指し、本変更はこれに当たらない。さらに、5号は「第2号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更」で施設建築敷地内の主要な給排水施設や消防用水利施設等の位置の変更等が挙げられるが、これにも当たらない。
以上より、本変更は軽微な変更に当たらず、法16条が準用されるため、手続を履践しなければならない場合でもあったにも関わらず事業計画の縦覧及び意見書提出手続を行なっていない。そして、右手続きは前述のように、事業計画の変更が宅地所有者の将来一定の割合で権利床を取得できるという法的地位に対して効果を及ぼすことから、事前に事業に関係する宅地所有者に対して変更を知らせて意見の機会を与えるために行われる重要なものである。それにも関わらず右手続きを履践しないことは取消事由となる。そのため、Dは上記主張をすることが考えられる。
2 第一種市街地再開発事業の施行区域は都市計画として定められており、「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること」という都市計画基準(都市計画法13条1項13号)を満たす必要があり、これは施行地区を変更する際も同様である。そして、この要件は都市計画に基づく開発が、一体の土地によって都市機能の向上を一体的総合的に行うため(都市計画法13条柱書き)に定められていることから、施行地区の土地はそれらが一体となって総合的に都市開発に利用されるべきであることを要すると解釈する。
もっとも、今回施行地区に編入されたC地区は元々の施行地区であるB地区から見て河川を越えた対岸にある空き地であり、地区周辺の人通りが少なかった。そもそも、C地区については、その周辺からB地区側へ橋が架かっていないためにB地区側からの人の流入も期待できず、駅方面へ行くにはかなりの遠回りをしなければならないという状況であった。そのため、C地区とB地区は河川によって完全に分断されており、人の出入りも少ないため、C地区を編入してもこれらが一体の都市として機能するとは考え難い。そうすると、「一体的に開発し、又は整備する必要がある」とはいえず、この要件を満たさない。そして、このように要件を満たさない土地を含めた事業変更は実体的に違法であることから、その変更の認可を認めている本件事業計画変更認可についてもこれを違法事由として主張できる。
したがって、Dは上記要件を満たさず法の趣旨に反するにも関わらず変更を認可したことが違法と主張すると考えられる。
3 法3条4号は、都市計画に定める施行区域について「当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献」しなければならないという条件を定めている。この条件は施行地区を変更する都市計画にも同様に適用される。
しかし、C地区は今まで空き家として放置されており、前述の通り人通りが少なく、駅から行きにくい土地であった。また、C地区は河川沿いの細長い土地で利用もしにくく、実際所有者のEは長年土地の活用に苦労していた。事業計画の変更においてC地区は公共施設として公園を新設するための土地とされているが、このような事情からすれば公園として生かすことが難しい土地であり、C地区を公園として利用することは「都市の機能の更新に貢献」するとは言い難い。そして、前述のようにこの違法は本件事業計画変更認可の違法事由にもなる。
したがって、Dは上記要件を満たさず法の趣旨に反するにも関わらず変更を認可したことが違法と主張すると考えられる。
第三 設問2
Dは本件権利変換処分の取消訴訟である本件取消訴訟において、本件事業計画変更認可の違法性を主張することができるか。
1 事業計画変更認可と権利変換処分は別個の処分であるため、先行処分である事業計画変更認可の違法を後行処分である権利変換処分の取消訴訟で主張することは公定力に反する。さらに、先行処分の出訴期間が過ぎているのにも関わらずその違法を後行処分の訴訟で主張できるとなると、6か月の出訴期間によって法律関係の早期安定を図った法の趣旨(行訴法14条1項)に反する。そのため、既に認可の公告があった日から6か月以上経過している現在、違法性を承継させる旨の本来上記主張は認められない。
しかし、違法性の承継を認めないとすると実効的権利救済の観点から妥当でない場合がある。そのため、先行行為と後行行為が同一目的を達成するために行われ、両者が相結合して初めてその効果を発揮するものであり、先行行為の適否を争うための手続的保障が十分に与えられていない場合には、実質的に同一の処分であり実行的権利救済の必要性がある場合として、違法性の承継が認められると解する。
2 これについてQ県は、先行処分である本件事業計画認可は具体的に施行地区をどのように発展させるかを決定するためのもので、後行処分の本件権利変換処分は宅地の所有権を区分所有権に変換する手続きであるから、それらが同一目的を達成するために行われるとはいえないと反論する。もっとも、前述の通り、事業計画認可を行うと公告や一定期間の経過を経て自動的に権利変換処分がなされるので一連の手続きに位置付けられる。そして、事業計画認可は後々権利変換を行うことを想定して行われることから、どちらも宅地所有者に権利変換を義務付けるというゴールに向かって一体として行われるものと評価できる。
次にQ県は、事業計画変更の申請にあたって宅地所有者の一定の同意が必要であること(法38条2項、14条1項)、事業計画の縦覧や意見書提出ができること、施行地区が変更された場合に公告される(法38条2項、19条1項)ことから、先行処分の段階でも事業計画変更認可の段階でその違法性を争うことができたはずであると反論する。しかし、これらの手続きによっては権利変換の際に具体的にどれくらい権利床を得られるかを知ることはできないため、これらによって手続的保障があったとは言い難い。
3 以上より、Dは本件権利変換処分の取消訴訟において、本件事業計画変更認可の違法性を主張することができる。 以上

