令和6年司法試験憲法の優秀答案とは?(論文50位代合格・評価A)
2025年3月29日
司法試験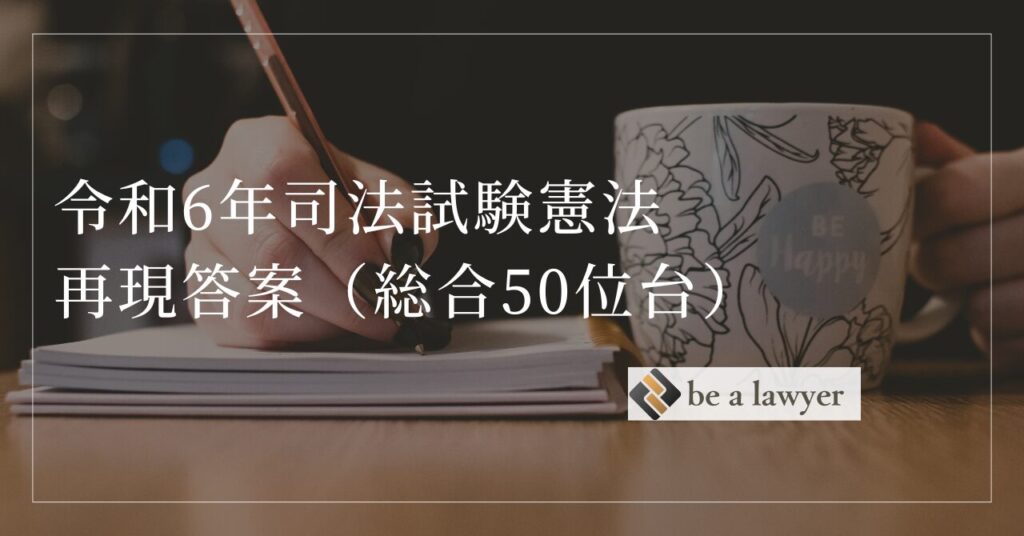
みなさんこんにちは、be a lawyer編集局です。
今回はbe a lawyer所属講師の令和6年司法試験の参考答案を掲載いたします。上位合格者の答案から学べることは多いと思いますのでぜひご覧ください。
【令和6年司法試験憲法 再現答案 評価A】
第一 本件法案規制①の憲法適合性
本件法案の規制①は犬猫販売業者の販売業を免許制にするものである。これは、犬猫販売業者の犬猫販売を行う自由(以下「自由①」)を制約していて違憲である。以下、説明する。
1 そもそも自由①は憲法上保障されているか。
憲法22条1項は「職業選択の自由」について明文で保障している。しかし、職業はそれを継続的に遂行しなければ無意味である。つまり、職業は、その開始、継続、廃止において自由であるだけでなく、活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるべきである(薬局距離制限事件)。そこで、職業の遂行についても職業の選択と同様のレベルで保障されていると解釈するべきである。そして、自由①は犬猫の販売業という職業の遂行に含まれる自由であるから、憲法は自由①を保障している。
2 本件法案規制①は自由①を制約するか。
本件法案の規制①は「販売場ごとに、その販売場の所在地の都道府県知事から犬猫の販売業を営む免許…を受けなければならない」としており、今まで免許なく行えていた犬猫販売について規制を課している。このように条件を付している点で自由①は制約される。
3 制約の合理性を判断するためには、制約される自由の性質と、制約の手段の厳しさから基準を設定する。
そもそも、職業とは、人が自らの生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、職業を通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである(薬局距離制限事件)。そのため、職業の遂行の自由は非常に重要な権利である。もっとも、職業はその性質上社会的相互関連性があり、精神的自由とは異なって制約が内在的にあるものである。そのため、事の性質より公権力による規制の要請が強く現れる。そして、制約の目的が消極目的(国民や社会に対する危険や弊害を防止する目的)の場合は立法裁量が縮減し、積極目的(社会経済の発展目的)の場合は広範な立法裁量が認められるとする考えがある(規制目的二分論)。しかし、本件法案の制約の目的は「人と動物の共生する社会の実現」(本件法案第1)であり、安易にどちらの目的か判断できず規制目的二分論を取るべきではない。
規制①は、犬猫の販売について免許という条件を課して、原則禁止した上で公権力に免許の付与の判断権限を与えている。これは行政上の特許とするものと考えられる。また、免許制は公権力の同意を得なければならない点で許可制と同様のものといえ、職業遂行の自由そのものに対する強力な制限方法である。さらに、免許を与え得るか否かの判断については、犬猫の需要均衡(本件法案第2第2号)やシェルターの収容能力(本件法案第2第3号)は販売業者が自ら変えることのできない客観要件である。そのため、強度の強い規制である。
以上より、規制①の目的が重要で、その目的と規制の手段に実質的関連性がある場合には制約が正当化される。
4 規制①をはじめとする本件法案の究極的な目的は人と動物の共生する社会を実現することであり、そのために犬猫の虐待・遺棄を防止して国民の生命尊重、友愛及び平和の情操を涵養する事が目的である。これは動物の愛護及び管理に関する法律と目的を同じにしており、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することに役立つ。また、犬猫の虐待・遺棄が社会問題になっており、現在侵害されている犬猫の生命身体を守り、人々の動物愛護の気持ちを育むことは平和な社会の実現に寄与し、憲法の平和主義にも適う。したがって、上記目的は重要である。
規制①は、免許制という手段をとっており、その免許の付与において販売場(1号)、犬猫の需要均衡(2号)、③犬猫シェルターの収容能力(3号)、という3つの事項を検討する。したがって、免許制自体と共に右3つの事項も手段として許容されるか判断する必要がある。
- 免許制自体
本件法案規制①は犬猫の販売は免許がなければ行なってはいけないとしており、これによって犬猫販売業者として適切な業者に限定して右販売をさせることが可能となる。現在、販売業者が売れ残った犬猫を遺棄したり、安易に買取業者に引き渡し、結果として、犬猫が殺され山野に大量廃棄されたりしたことが大きな社会問題となっている。このような事実からすれば、悪徳な販売業者を規制し、犬猫の生命身体を守るためには免許制を用いる関連性がある。また、免許の発行数が限定されることから、販売業者が自律的に免許維持のために適切な運営を行うことが期待される。また、犬猫が代表的なペットとはいえ、免許制の対象は犬猫の販売に限られており、犬猫以外のペット飼育者は半数近くの割合を占めることから、結果として犬猫の販売ができなくなった場合に即座に販売業者が廃業を余儀なくされることはない。そのため、目的達成の手段として過度ではない。
したがって、免許制自体は実質的関連性を有し、合理的制約として許容される。
- 販売場
1号は、販売場ごとに設けられた犬猫飼養施設の状況により免許付与が適当でない時に免許を与えないこととする要件裁量を付加している。具体的には、犬猫販売業者は免許申請の前提として、販売場ごとに、犬猫販売頭数に応じた犬猫飼養施設を設けることが必要であり、各犬猫飼養施設につき、犬猫の体長・体高に合わせた檻や運動スペースについての基準及び照明・温度設定についての基準が満たされる必要がある。このような施設を用意することは施設に過度に犬猫が収容されることを防ぎ、飼育崩壊による犬猫への虐待・遺棄を未然に防ぐことができ、関連性がある。また、上記基準は動物愛護管理法上の販売業者の登録制の現行基準より厳しいが、国際的に認められた範囲内であり、過度といえない。
したがって、上記事項についての要件裁量の存在は実質的関連性を有し、合理的制約として許容される。
- 犬猫の需要均衡
2号は、犬猫の需給均衡の観点から、犬猫販売業免許を与えることが適当でないときに要件裁量を与えている。この要件は都道府県ごとの人口に対する犬猫の飼育頭数の割合や犬猫の取引量等を考慮して各都道府県が基準を定める予定であり、売れ残り自体よりも売れ残った犬猫の管理を適切にすべきという意見がある。しかし、販売に対して価値を失った売れ残りが多くなることで販売業者が赤字になり、それによって処分・遺棄が横行する可能性が高いから、売れ残りがどれくらい生じるかは重要である。また、6か月と短いスパンで売れ残りが発生してしまうことから需要に対して供給が過多になるとそのまま売れ残りが大量発生する可能性も高い。そのため、免許の発行に際して需要均衡を検討することは目的に適っており適切な要件である。
したがって、上記事項についての要件裁量の存在は実質的関連性を有し、合理的制約として許容される。
- 犬猫シェルターの収容能力
3号は犬猫シェルター収容能力の観点から免許付与に適当でないときについて要件裁量を付与している。犬猫シェルターは犬猫を飼えなくなった人が犬猫を持ち込む施設であり、この収容量を超えた場合には犬猫の不当な遺棄・処分が増えてしまう。そこで、販売数自体を減らすことでシェルターへの持ち込みを減らす必要性があるとして上記要件が付与されたと考えられる。しかし、販売業者が犬猫の適切な管理を行うのはその売却までの期間であり、売却後は買主の所有物として飼い主が責任を持って飼育するべきであるから、シェルターの収容数オーバーの責任を販売業者に押し付けるのは妥当でない。確かに、多くの都道府県はシェルター収容数が公共団体や民間団体で引き取っている頭数を超えないようにするための方策を検討してほしいと要望しているが、犬猫の販売規制が右方策になる関係性にあるとはいえず、直接犬猫の飼い主に働きかける方策をとるべきである。そのため、上記要件は目的に関連性がなく、わずかな関連性があっても過度に販売業者に責任を押し付けるものとして実質的な関連性があるとはいえない。
したがって、上記事項についての要件裁量の存在は実質的関連性を有さず、合理的制約として許容されない。
5 以上より、規制①の手段は目的との実質的関連性がなく、自由①への制約は正当化されないから違憲である。
第二 本件法案規制②の憲法適合性
規制②は犬猫販売業者が犬猫のイラスト、写真及び動画を用いて広告を行う自由(以下「自由②」)を制約していて違憲である。以下、説明する。
1 自由②は、犬猫を販売するにあたりその魅力を人々に向けて発表するものとして「表現」をする自由と評価できる。犬猫販売という営利の目的であることから前述の職業遂行の自由にあたるとする評価もあり得るが、目的が営利というだけで直接的には表現そのものであることから、直接的に表現の自由と評価すべきである。そして、憲法21条1項は「一切の表現の自由」を保障しており、自由②は憲法によって保障されている。
2 規制②は「犬猫販売業者は、犬猫の販売に関して広告するときは、犬猫のイラスト、写真及び動画を用いてはならない。」としており、自由②を禁止しているから、制約がある。
3 自由②は、犬猫販売業者が商品である犬猫の魅力を消費者に対して伝える手段で業者の利益に密接に関連している。そして、広告を通して外部からの見方を作る手段であることから、個性を作り出すという意味で自己実現の価値を有し、思想の自由市場への働きかけも可能となる。また、現代社会においてイラスト・写真・動画を用いて視覚的に商品を伝えることは広告手段の中でも大きな影響を持っており、重要な精神的自由の1つである。もっとも、主権者の中で政治的意見を通して民主主義にアプローチするための自己統治の価値があるとはいえず、自己統治の価値を有する自由に比べると重要性が劣る。
制約②は犬猫の広告に際してその内容を問わず、広告でイラスト・写真・動画を使うという手段について全て禁止するもので、内容規制でなく内容中立規制である。また、表現そのものを規制するのではなく、表現によって発生する可能性のある、軽率な犬猫の購入ひいては犬猫の不当な処分・遺棄という社会問題の発生を防ぐために行われるため、間接的・付随的な制約である。したがって、規制の強度自体が強いとは評価できない。
そこで、規制②の目的が正当であり、その手段が目的と合理的関連性を有する場合には制約が正当化される。
4 規制②は安易な犬猫の購入を防ぐことによって「人と動物の共生する社会の実現」することが究極目的で規制①と同様であり、前述の通り正当であるといえる。
規制②は犬猫のイラストや写真、動画を用いての広告についてオフラインオンラインを問わずに一律に規制している。この手段を用いる理由としては、品種等の文字情報に比べて、イラスト・写真・動画は、視覚に訴える情報であり、購買意欲を著しく刺激し、十分な準備と覚悟がないままの購入につながるというものである。しかし、視覚に訴える情報によって犬猫の購入に興味をもつ消費者の全てが安易に商品に惹かれるわけではなく、右情報を遮断することによって目的を達成することができるかの関連性に乏しい。目的を達成する直接的な方法としては広告の規制ではなく、購入の際の厳格な審査や購入後のサポートによってなすことができ、販売業者の表現の自由を狭めることの合理性も乏しい。
また、視覚的広告を全て規制したとしてもあくまで文字情報を用いれば商品の詳細な情報を広告することができるという説明があるが、犬や猫はその見た目が重要な商品情報であり、犬や猫の可愛らしさを文字情報のみによって伝えることは非常に困難である。また、地上の看板広告やインターネット上の広告は、道を歩いているときやネットを閲覧している時にふと目に入るタイプの広告であり、このような広告は性質上文字ではなく視覚的に印象的で興味を持ってもらえるようなイラスト・写真・動画を用いることが効果的である。そのため、右手段を用いる広告を規制することは営利目的の犬猫販売業者の販売利益を大きく下げることになると考えられる。そうすると、イラスト・写真・動画の使用を全て一律に規制することはその目的に比してあまりにも過度な規制手段を用いており、目的との間に因果関係があるとしても合理的な関連性があるとはいえない。
5 以上より、規制②の手段は目的との合理的関連性がなく、自由②への制約は正当化されないから違憲である。
以上

