令和6年司法試験民法の優秀答案とは?(論文50位代合格・評価A)
2025年4月9日
司法試験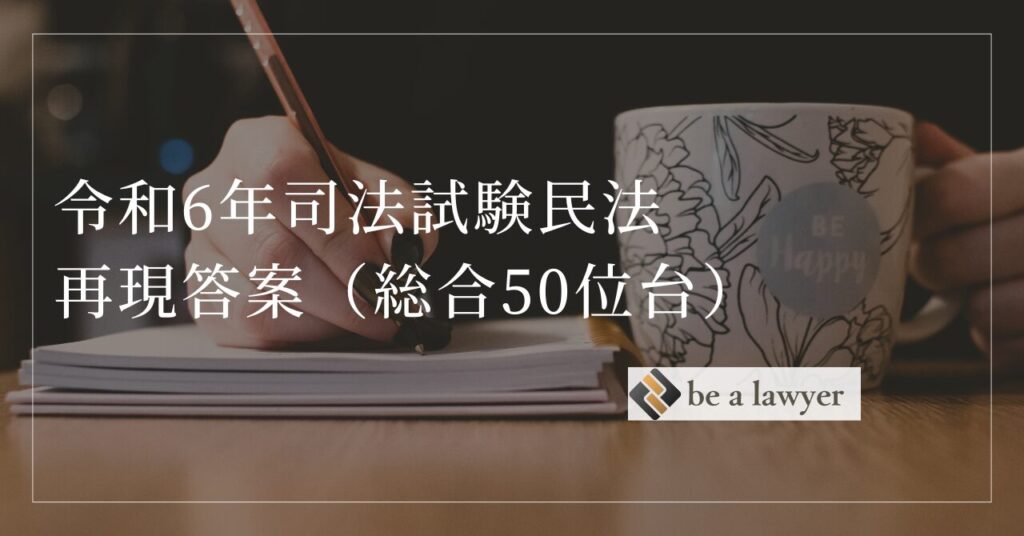
be a lawyer編集局です。今回は令和6年司法試験民法の再現答案を投稿いたしますので、学習にお役立てください。
第一 設問1(1)問ア
Cは、下線部アの反論に基づいて請求1を拒むことができるか。
1 本件でAは、甲土地をCが利用していることから、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求しているところ、Cはアの反論において、契約①に基づいて甲土地を占有する権利を有すると主張している。
2 契約①はCB間において甲土地を目的としてなされた賃貸借契約(民法(以下法文略)601条)である。契約当時甲土地の所有権はAにあり、賃貸人であるBは甲土地を所有していなかったのであるから、Bは甲土地を使用収益する権限を有していない、つまり契約①は他人物賃貸借契約だったと評価できる。そして、契約締結後にBは死亡していて、Bの権利義務はAが相続(896条)している。そうすると、Aは契約①における賃貸人の地位を相続することになる。
しかし、通常他人物賃貸借契約が行われた場合には、目的物の所有者はそれを貸す義務を負わず、賃借人による請求を拒否することができる。にも関わらず、相続という偶然の事情で賃貸人の地位を相続した場合には賃貸人として義務を果たさなければならないことは不合理である。そのため、他人物賃貸借の賃貸人の地位を相続したその目的物の所有者は、賃貸人の地位と所有権者の地位両方を有すると考えるべきである。そうすると、Aは甲土地所有者の立場から、過去にBが勝手に行った契約①について履行を拒否することができる。
3 したがって、Cは、下線部アの反論に基づいて請求1を拒むことができない。
第二 設問1(1)問イ
Cが下線部イの反論に基づいて請求1を拒むことができるか。
1 下線部イの反論は、300万円の損害賠償を受けるまでは甲土地を占有する権利がある旨のものである。上記に記載したように、本件でAは契約①の賃貸人の地位を相続しているところ、契約①には甲土地の使用及び収益が不可能になった場合について、損害賠償額を300万円と予定する旨の特約(420条)が付されている。今回Aは甲土地所有権者として契約①の履行を拒んでいるので、Cは甲土地の使用及び収益が不可能になったといえ、CはAに対して300万円の損害賠償請求権を有することになる。そこで、Cは下線部イの反論において、右債権を被担保債権として甲土地を留置する権利(295条)を主張していると考えられる。
2 留置権が認められるためには、物を留置することと被担保債権の履行について牽連関係があることが必要である(「その物に関して生じた債権」)。本件では、AはCに対して甲土地の変換請求権をもち、CはAに対して上記損害賠償請求権を有しているのだから、Cが甲土地を留置することに牽連性が認められるとも思える。
しかし、今回Aは他人物賃貸借と賃貸人の地位の相続によって偶然上記損害賠償請求権を負うことになっており、本来はCに対して即座に甲土地変換請求をできるはずであった。また、仮に相続が生じていない場合には賃貸人のBは甲土地に権利を有さずこのような留置権を所有者のAに主張することができなかったはずであるから、相続があった場合にだけ本来主張できないはずの留置権を認めることはAに不測の損害を与える点で不合理である。そのため、牽連性は認めるべきでない。
3 したがって、Cは、下線部イの反論に基づいて請求1を拒むことができない。
第三 設問1(2)問ア
請求2は認められるか。
1 請求2は、DがAに対して、同年8月31日に支払った令和4年9月分の賃料の一部を返還する旨のものである。本件でAは契約②によって乙建物についてDとの間での賃貸借契約(601条)を締結しているところ、Dは賃料前月末日払の約定より令和4年9月分の賃料を支払っている。しかし、乙建物の一室である丙室が雨漏りによって同年9月11日から30日までの間使用ができなくなっていた。そこで、Dは請求2によって、丙室を使用できなかった分の賃料について不当利得返還請求(703条)をしていると考えられる。
2 賃貸借契約において賃貸人は目的物を使用収益させる義務を負い、賃借人は目的物を使用収益する権利を有するところ、今回丙室が雨漏りしたことで20日間Dは同室を使えなかったのであり、これは賃借物が一部滅失した(611条1項)と評価できる。その場合、使用収益できなくなった分の賃料が減額される。そのため、Dは本来払うべきでなかった分を含めて令和4年9月分の家賃を払っているといえ、それがDの損害であり、Aの利得である。また、これらの間には因果関係があり、法律上の原因もない。そのため、一部の家賃について給付利得として、DからAへの不当利得返還請求が認められる。
3 したがって、請求2は認められる。
第四 設問1(2)問イ
請求3は認められるか。
1 請求3は、DがEに支払った30万円を直ちに償還するようDがAに請求する旨の物である。Dは丙室の雨漏りの際にEに依頼して修繕工事である本件工事を行い、この報酬として30万円を払っている。これは目的物の修繕に必要な費用であるため、請求2は必要費償還請求権(608条1項)といえる。
2 しかし、目的物の修繕は607条の2各号の事情がない限り賃借人ではなく賃貸人が行うべきものであり(606条1項)、今回賃借人のDが主導して修繕を行っていることから償還請求が認められるかが問題となる。
この点、DはAに対して丙室の修繕が必要であることを通知しておらず、本件工事の実施について急迫の事情はなかったため、賃貸人のAが修繕義務を負っていたといえる。しかし、賃貸人賃借人どちらが修繕したかに関わらず、それによって目的物の価値が回復されているのだから、目的物を所有している賃貸人が修繕費用を負担すべきであることに変わりない。しかし、本来賃貸人が修繕すべき立場にあって賃借人が修繕した場合で賃貸人が修繕した場合の金額を超えて費用を支出した時は、その超えた分を「賃貸人の負担に属する必要費」(608条1項)とすることは賃貸人に対して著しく不合理であり、本来の負担分のみ償還できると解する。
そのため、本件では必要費償還請求自体はできるものの、本来Aが修繕していれば本件工事と同じ内容及び工期の工事に対する適正な報酬額として20万円しかかからなかったため、その限度で償還請求が認められる。
3 したがって、請求3はその一部(20万円)が認められる。
第五 設問2
請求4は認められるか。
1 請求4は、Iが丁土地を占有するFに対して丁土地を明け渡すよう請求したものである。この前提としてIが丁土地を所有していることが必要であるところ、今回、丁土地は元々Gが所有していたところ、GH間の離婚に伴う財産分与(768条)としてGがHに譲渡し(契約③)、HI間の売買契約(555条)によってHがIに売却して(契約④)、結果現在Iが所有しているとも思える。
2 もっとも、Gは契約③について錯誤(95条1項)により取り消す旨の意思表示をしていることから、これによって契約③が無効となり(121条)、Iが丁土地を所有していないとも考えられる。
契約③でGは財産分与の際の課税が自分でなくHに課されると誤解しており、これが「法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」かが問題となる。これが認められるためには、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」(95条2項)である必要がある。これは、錯誤が本来意思表示者側の勘違いであることからも、当事者間において「基礎とした事情」が当然契約の前提になっていてそれが異なる場合には契約の効力がなくなるというレベルまで認識していたことを要すると解釈する。
そして、契約③の際にGは丁土地以外の財産もなく失業中で収入がなかったため、財産分与で300万円もの課税をされた場合には生活がままならなくなる可能性があり、これはGがHに伝えていた。また、GはHに対して、Hに課税されることを心配して気遣う発言をしていて、Hも自身に課税されることを前提として「大丈夫」と答えているため、Hに課税されるという事情が法律行為の前提になっていて、尚且つそうでない場合(Gに課税される場合)には財産分与をやり直すような事情であることを互いに認識していたといえる。また、どちらに課税されるかは、その金額が多額のものであることから「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」(95条1項柱書)といえる。さらに、本件では契約者が「同一の錯誤に陥っていた」(95条3項1号)ため、Gに「重大な過失」があったか(95条3項柱書)は問題とならない。
以上より、Gによる契約③の錯誤取り消しは有効であり、遡及的に無効となっている。
3 しかしながら、Iは契約③の錯誤取り消し前にHとの間で契約④を締結しているため、「善意で過失がない第三者」として、契約③が無効となっても丁土地の所有権を主張できると思われる。
「善意で過失がない第三者」とは、錯誤による法律行為について新たに法律上の利害関係を有するようになった者で契約時に錯誤の存在について善意無過失であった当事者及びその包括承継人以外の者を指すところ、Iは契約④を締結した時に、Gが契約③に係る課税について誤解していたことについて善意無過失であった。そして、Iは丁土地についてHからIへの所有権移転登記をしていないところ、第三者として保護を受けるために登記の具備まで必要かが問題となる。しかし、錯誤は意思表示者の勘違いによりなされる点で錯誤ある契約をした者に帰責性があり、その保護を厚くする必要がないから、第三者側に登記まで要件を要求する必要はないと考えるべきである。そのため、Iは「善意で過失がない第三者」といえる。そして、本来契約③は遡及的無効になることから、保護のために所有権を得られる善意無過失の第三者は、本来の所有者から直接所有権を承継すると考えるべきである。
3 そして、丁土地を占有しているFについて見ると、Fは錯誤取り消しを有効と考えていたGとの間で丁土地の売買契約を行って(契約⑤)丁土地を購入している。この点でFとIは丁土地所有権につきGから所有権を承継できるかという対抗関係に立つと考えられる。このような不動産に関する物権の得喪の対抗要件は登記をすること(177条)であり、今回丁土地の登記名義はHにあることからIもFも対抗要件を具備していない。したがって、Iが請求4をするためには、GからHへの丁土地所有権移転登記を取り消してもらってからGからIへの丁土地所有権移転登記を行うことで対抗要件を具備しなければならない。
4 したがって、請求4は認められない。
以上

