東北大学法科大学院(東北大ロースクール)に受かるための勉強法と入学後の過ごし方とは?
2025年10月6日
法科大学院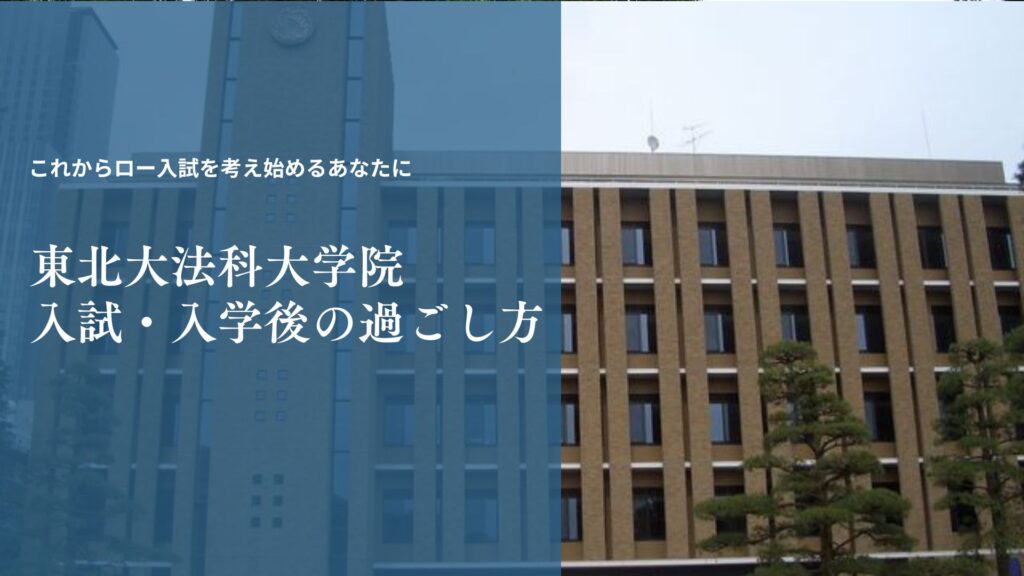
<はじめに>
こんにちは、be a lawyer講師で東北大学法科大学院出身のYです。
これから、東北大学法科大学院の入試問題の特徴と受験生が採るべき対応策・勉強法、入試前後の状況、東北大学法科大学院入学後の過ごし方について書いていきたいと思います。
これから東北大学法科大学院への進学を考えている方はぜひ参考んしてみてください。
<東北大学法科大学院の入試の特徴・勉強法>
(1)憲法
結論から述べると、憲法は年度によって出題傾向が大きく変わります。断定的なことは言えませんが、作問される先生が異なるためではないかと強く推認されます。ある年度は、細かな学説やおよそ司法試験の論文式試験では問われる可能性が低いようなややニッチな論点が出題されたりしています。例えば、令和5年度の前期入試では、外国人、団体・法人、天皇の人権享有主体性について問われていますし、令和4年度の前期入試では、憲法13条後段の「公共の福祉」に関する学説対立が問われています。この出題傾向に基づいて作問された場合は、はっきりいって、対策のしようがないかもしれません。憲法の学者の道も考えていた私であっても、特に有効な手段は思いつきません。ただ、対策が全くできないわけではなく、最終的には相対評価なので、周りに書き負けないことが重要になってきます。そのためには、基本書、ロープラクティスやサブノートなどの演習書等を用いて、基本的な論点の理解を深めることが必要だと思います。
また、ある年は第1問~第3問などに分かれて、最高裁判例の基本的な理解度を測る問題も出題されています。近年では、この出題傾向が顕著です。政教分離原則や学問の自由に関する設問など、司法試験でも出題実績のある論点について出題されています。この出題傾向に基づいて作問される場合、複数の判例が問題文中に言及され、それらについての基本的な理解が問われています。判例に基づいて出題される場合は、学説上の対立が問われる問題に比べて、憲法判例百選・精読憲法判例等を用いた「判例学習」という形で対策がしやすいのではないかと思います。ただ、この出題の場合も、「法律上の争訟」該当性など、いわゆる統治分野からの出題もあるので、基本的な論点については併せて勉強をしていくべきだと思います。
(2)民法
民法の特徴は、(解答は5行程度で行いなさい。)というように、行数指定があるという点だと思います。私も最初見た時は驚きましたし、何をどれだけ書くべきかがわかりませんでした。しかし、今になって思うのは、「書くべき分量」についてヒントが与えられているということです。3行程度の場合は、端的に問われた内容に答えれば足りますし、問題文中に「簡潔に」と指示がある場合があります。10行程度の場合は、法定三段論法や法律要件をすべて検討することが求められていると考えられます。出題傾向については、民法総則、物権、債権、親族・相続法と多岐にわたっています。ですので、特定の分野は全く勉強しないことはかなりのリスクとなるでしょう。しかしながら、その中でも、民法総則、債権分野が頻出分野と言えるでしょう。債権分野・民法総則分野を中心に問題提起も含めて数行程度で簡潔にまとめる練習をする必要があるでしょう。
(3)刑法
刑法はとてもオーソドックスな事例問題が出題されます。分量は問題用紙A4で1枚から2枚です。しかし、試験時間との関係で、非常にタイトとなっています。入学後の定期試験でもそうですが、時間は非常にタイト、点数評価は厳しい、というのが通常です。そして、先生が何度もロースクールの授業等で仰っているのが、「何が何でも論点をすべて拾って書き切る」ということです。そのためには、多少論証の理由付けが足りなくなっても仕方がない、と割り切ることが必要だと思います。私は、理論的に考えることが好きだったのですが、その先生に、「理解はその通りだけど書ききれないと意味ないよ」と言われていました。圧倒的な理解・知識のもとで、いかに短く論証を展開して多くの論点を処理するか、というのが重要になってきます。また、学説対立があるものについては、基本刑法などに記載がある通説的な理解で答案を展開すれば足り、「特定の学説の立場に立てば減点される」ということはないと思います。
(4)商法
近年、手形小切手法や商法総則からの出題はなく主に会社法からの出題がなされます。商法は、一番対策の甲斐がある科目ではないかと思います。というのも、商法は一貫して、典型論点に関して「5行程度で簡潔に説明しなさい」という出題であり、この傾向は今後も維持されると思われるからです。特に利益供与に関する会社法120条や取締役の対第三者責任に関する会社法429条1項の「損害」概念についての問題が頻出です。
商法は、答案を作り、講評と照合して修正・訂正をすることで、一種の完全答案を完成させることができます。これを公表されている過去問のすべてについて行うことで、東北大学法科大学院入学の商法対策は十分と言えるでしょう。
(5)民事訴訟法
一昔前は既判力ばかり問われていましたが、現在はそのような偏った出題はされていません。二重起訴、弁論主義、処分権主義、自白、既判力といった幅広い分野・論点から出題されています。特徴としては、最初の設問で訴訟物が問われることがあります。私も学部時代は要件事実論を勉強していなかったので、ロースクール受験生の段階で訴訟物がきちんと答えられていたか否かは自信がありません。しかし、ロースクールに入学すると授業がありますし、予備試験でも必要になってくるので、余裕があれば、新問題研究要件事実や大島本に軽く目を通しておくこともよいでしょう。また、前述のように、基本的な問題が出題されますので、ロープラクティス民事訴訟法や事例から考える民事訴訟法等の基本的な演習書の典型問題を解けるようにするのが一番だと思います。
(6)刑事訴訟法
刑事訴訟法は過去問の講評が数行程度で書かれているため、あまりこれを読んでも長安作成の上での参考にはなりません。しかしながら、法科大学院では常に司法試験を意識して授業が展開されています。司法試験では基本的に過去の司法試験で出題された論点の焼きまわしが多いです(令和7年度司法試験の316条の32は初出だと思いますが)。その影響もあってか、法科大学院入試問題も基本的に司法試験に出題された論点しか問われていません。しかし、範囲としては領置や強制処分該当性などの捜査に関する問題のみならず、違法収集証拠排除法則や伝聞法則など証拠法に関する出題もされています。法科大学院受験生にここまで求めるのは酷かもしれませんが、判例学習に加え、司法試験の問題を解き、出題趣旨や採点実感を読み込んだうえで答案を作成することが、東北大学法科大学院入試の刑事訴訟法攻略の一番の近道だと思います。
<入試前後の状況>
私は、東北大学法科大学院の受験を考え始めたのはGWが終わってからと非常に遅かったと思います。ほかの国公立大学の法科大学院が第一志望だったので、前期試験が夏にあるということで、力試しのために受けてみようというのが本音のところでした。そこからは、過去問を見たうえで、商法の答案例のサンプルを作って友人に出題してもらい口頭で答えるなどの練習をしていました。
入試は東京会場で受験しました。入試のために前乗りしてホテルに宿泊していたのですが、試験当日、名前が酷似した別の試験会場にいってしまいました。ギリギリ間に合ったものの、猛ダッシュして汗だくで試験会場に入ったのち、座ってすぐ試験が始まるという具合でした。皆様は、試験会場の名前にはよく注意していただくようにお願いします。
東北大学法科大学院の受験者数が増加していたこともあり、とても不安でした。しかし、秋には別の国立大学の受験も控えており、東北大学法科大学院の入試にはない行政法がかなり苦手で不安でしたので、行政法の勉強を中心に過ごしていました。
<東北大学法科大学院入学後の過ごし方>
東北大学法科大学院への進学を決めて最初に行うべきことは家探しです。東北地方に親戚や友人知人は全くいなかったので、内見には行かずに家を決めました。私の場合は幸い良い物件に恵まれましたが、皆さんは一度足を運んでみた方がいいと思います。
東北大学法科大学院の授業は一部を除いて、ほぼすべての授業が司法試験を意識して作られています。授業の中で、司法試験問題の解説がなされたり、演習書や類似問題の解説がなされたりするなど、非常に手厚かった印象です。他の法科大学院に進学した友人の話を聞くと、司法試験に特化していない法科大学院もあるようですのでそこはよかったかなと思います。ただ、他の法科大学院と比較すると、その場で起案する、いわゆる即日起案系の授業は少なかった印象です。もっとも、自分で自習したり、友人たちと自主ゼミを組んで起案をしたりしている人も多かったので、そこまで難点にはならないかもしれません。
人数も、既習1年目・未修2年目の段階で、既習50人前後+未修10人前後、合計60人前後と他の法科大学院と比較して少数なので、仲良くなりやすい環境だったのかなと思います。もちろん、自主ゼミを組むなどして、その中で、数人単位のユニットのようなものができるのは、どのコミュニティでも同じだと思います。
先生方に関しても、私が言うのもおこがましいですが、本当に優秀な方ばかりで、(立場上答えられないものを除き)何を聞いても答えてくださいます。また、私は、すべての授業終わりに最低1個は質問をするという自分ルールを作っていたのですが、どれだけ多くの質問をしようが、必ず時間を作って答えてくださいます。しかも、先生方ほぼ全員が、司法試験員や予備試験委員を経験又は現在進行形で担っておられる方なので、「答案を作成する」という観点から必要十分な情報を教えてくださいます。
ですので、入学後は授業内容を吸収することに尽力し、長期休みは司法試験や予備試験の問題の演習を行うことにすれば、司法試験対策という点でも事足りると思います(司法試験の答案を添削してくれる先生方もいます)。
<おわりに>
ここまで、東北大学法科大学院入試の特徴・分析・勉強法のみならず、入試前後の過ごし方、入学後の授業その他の過ごし方についての記事を書いてきました。東北地方に現存する唯一の法科大学院であり、首都圏、関西圏から地理的距離があるため、あまり地縁がない方も多いかもしれません。しかし、司法試験を受験する身からすれば、合格ために必要な知識は東北大学法科大学院のある東北大学片平キャンパスで全て習得することができると思います。
私は、東北大学法科大学院に進学・卒業してよかったと感じているので、多少のバイアスはあるかもしれませんが、東北大学法科大学院のよさを感じていただければ幸いです。長文読んでいただき誠にありがとうございました。
be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


