早稲田大学法科大学院(早稲田大ロースクール)に受かるための勉強法と入学後の過ごし方とは?
2025年10月5日
法科大学院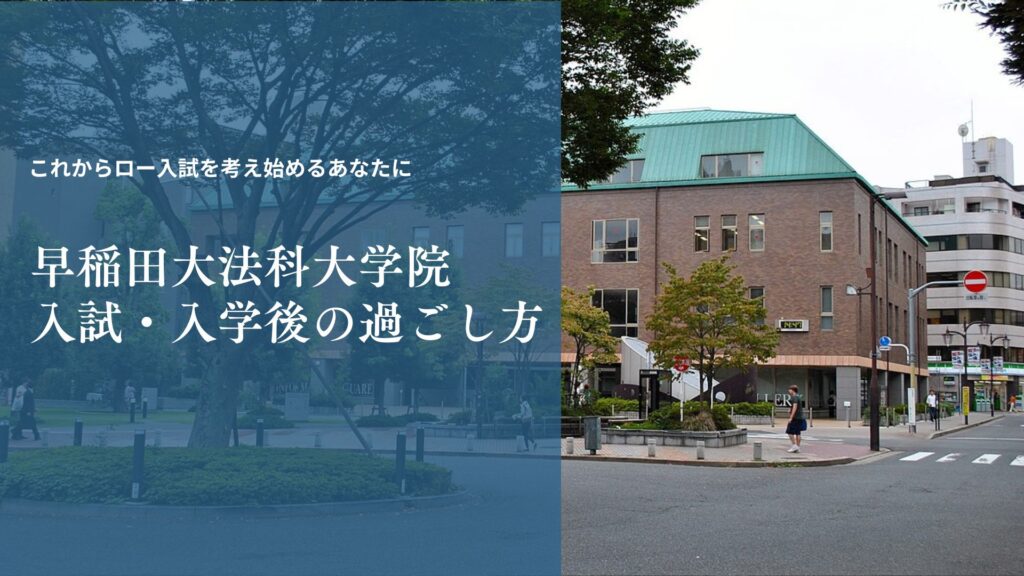
こんにちは、be a lawyer講師のkです。今回は私が早稲田大学法科大学院に入学するまでにした勉強法と入学後の過ごし方を説明していきたいと思います。
これから早稲田ローに入学する方や来年の早稲田ロー入試を控えている方はぜひご覧ください。
第1 早稲田ロー入試まで
1. はじめに
私は、大学2年から予備校で学習を始めました。学習と並行して、4年の12月まで体育会の部活に所属し週4日から5日ほど活動していました。皆さんの中には、課外活動や仕事で限られた勉強時間しか取ることができない方も多くいらっしゃると思います。そんな方もロースクールを十分に目指すことができるということを知っていただけると幸いです。
2. 学習履歴
2年
学部2年の1年間は、大学の授業や予備校の基礎講座にて法学の基礎を学びました。ここでしっかりと全ての講座を視聴しきれたので、その後の論文の勉強が楽になったと思います。
3年
予備校の講座や答練で論文の勉強を始めました。それと並行して、基礎講座の知識を定着できるようテキストを何度も読み返しました。他の活動との兼ね合いで可処分時間が少なかったため、基本書などには手を出さず、予備校のテキストのみを使用して勉強をしていました。
4年
私は、9月に慶應ロースクールと予備試験、10月に早稲田ロースクールを受験しました。直前期は予備校の論文テキストと論証集を各科目できるだけ多く周回できるよう、頭の中で答案構成をし、答案を見て自分の考えが間違っていないか等を確認していました。慶應ロースクールは補欠合格、予備試験は1400位代で不合格となってしまいましたが、早稲田ロースクールは、法曹コースの開放型で合格し、給付型の奨学金をいただくことができました。
3. 入試対策について
配点は、民法120点、刑法100点、憲法、民訴法、刑訴法、商法が各80点なため、配点が高い民法と刑法を重点的に勉強しました。問題自体は、癖が少なく典型的な論点を聞かれることが多いため、基礎的な知識の質を上げることが合格への近道だと思います。
また、試験時間については、民法、刑法、憲法が180分、民訴法、刑訴法、商法が150分となっているため、時間配分が重要になります。上三法についてはそれぞれ配点が違うため、それを逆算して試験時間を配分する訓練をすると良いと思います。過去問に目を通し、本番どのような順番で、どの科目に何分かけて答案を書くかをイメージしましょう。
第2 法科大学院(ロースクール)入学後の過ごし方
0. 入学前
早稲田ロースクールでは、入学手続きのための書類の送付の際に推薦図書として各科目数冊ずつ基本書を読むことを推奨されます。確かに入学後に基本書を読むためにまとまった時間を取るのは長期休み中などでないと難しいので、それまでほとんど基本書を読んだことがない方は、何冊か読んでみてもいいかもしれません。もっとも、効率的に学習をしたいのであれば、短答の過去問に取り組んだり、基礎講義や論文講義の復習を入学前にしっかりとしておくことをお勧めします。
1. 授業
早稲田ロースクールの特色として、2年次の授業が全て司法試験の試験科目であるということが挙げられます。そこで、各科目についてどのように勉強するのがおすすめかを以下に紹介します。
・憲法
憲法は、2年後期に2単位(週1コマ・全13回、以下同様)のみとなっています。授業の内容は、人権分野を中心に、統治の重要な部分も含めて判例に沿って解説がされていくというものです。もっとも、司法試験の対策としては不十分であることは否めないため、早期から司法試験の過去問を検討するなど授業以外の学習時間を意識的に取ることをお勧めします。
・民法
民法は、2年前期に4単位、後期に2単位を取ることになります。事前に事例問題が公開され、その問題を検討するというのが大まかな授業の流れです。授業で扱う事例問題は、内容・網羅性ともに素晴らしく、授業の復習をしっかりと行えば十分に司法試験で通用する力をつけることができるため、授業の予習復習を重点的に行うことをお勧めします(もちろん短答については過去問等を勉強することが必要です。)。
・刑法
刑法は、2年前期に総論、2年後期に各論をそれぞれ2単位取ることになります。先生によってレジュメの網羅性や量がまちまちであるため、各先生にあったスタイルの勉強方法を見つける必要があります。また、卒業生の先生が土曜日に刑事系過去問演習ゼミを開講しているため、ぜひ活用してみてください。
中間テストでは、短答の過去問が出題されるため、しっかりと中間対策をすれば、司法試験の直前期に楽になると思います。
・民事訴訟法
民事訴訟法は、2年前期に2単位、後期に4単位を取ることになります。特に後期の4単位は、どちらの授業も非常にレベルの高い内容が要求されるため、しっかりと予習復習をする必要があります。早稲田ロースクールの民訴法の授業をしっかりと学習すれば、司法試験では民訴法を得点源にすることができるため、食らいついていきましょう。
・刑事訴訟法
刑事訴訟法は、2年前期に捜査法、2年後期に公判・証拠法等をそれぞれ2単位取ることになります。こちらも先生によって授業のスタイルが大きく異なるため、刑法と同様各先生にあったスタイルの勉強方法を見つける必要があります。また、卒業生の先生が土曜日に刑事系過去問演習ゼミを開講しているため、ぜひ活用してみてください。
期末試験は、基礎的な問題が出題され、高得点勝負になるため、基礎の知識を大切にするような勉強をすることをお勧めします。
・商法
商法は、2年前期に4単位、2年後期に2単位を取ることになります。前期で会社法のインプットをし、後期で問題演習をするというイメージです。特に前期の2単位は予習に時間がかかる人が多く、油断をしていると会社法づけの生活になってしまうため、程よくサボりつつ向き合うことが大切になります。後期の演習授業は、先生によって独自の問題や司法試験の過去問など扱うものに差がありますが、前期にインプットを十分に行い、後期に演習をすることで司法試験に向けていい準備をすることができると思います。
また、前期の中間テストは司法試験の短答の肢別を解くことになります。予備試験の対策をしたことがない方は準備に時間がかかるため、早くから対策をすることをお勧めします。
・行政法
行政法は、2年前期に総論、2年後期に行政救済法をそれぞれ2単位ずつ取ることになります。中間テストが難しく、大きく点差がつくため、しっかりと対策することができれば良い成績を取ることができます。期末試験は、司法試験よりも少し簡単な問題が出るため、基礎的な知識をしっかりと定着することを目指しましょう。
・選択科目
選択科目は、前期後期に2単位ずつ取ることになります。それぞれについて言及することはできませんが、選択科目の単位を落とすと、他の成績がどれほど良くても在学中受験をすることができなくなるため、その点には注意が必要です。
2. 授業以外の学習
私は、授業以外に、司法試験の過去問を検討する自主ゼミを週に2回ほど行っていました。自主ゼミをすることにより、圧力を持って司法試験の過去問に取り組む時間を作ることができ、また、同じ年に司法試験を受ける人の答案と自分の答案を見比べることで自分の長所や短所を把握することができるため、お勧めです。
また、早稲田ロースクールはAA(アカデミックアドバイザー)制度という、OB・OGの先生方の学習支援体制が充実しています。刑事系の過去問検討ゼミ以外にも、司法試験に向けて有益な講座が数多く開講されるため、常にアンテナを張ってゼミの情報を仕入れることをお勧めします。
第3 最後に
ここまで読んでくださり誠にありがとうございました。
早稲田ロースクールは、学生が司法試験に合格できるよう各先生方が全力で向き合ってくれる環境が整っていると思います。ロースクール入試はゴールではなく、その先にはさらに大きい目標が待っていると思いますが、ぜひ頑張ってください。
be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


