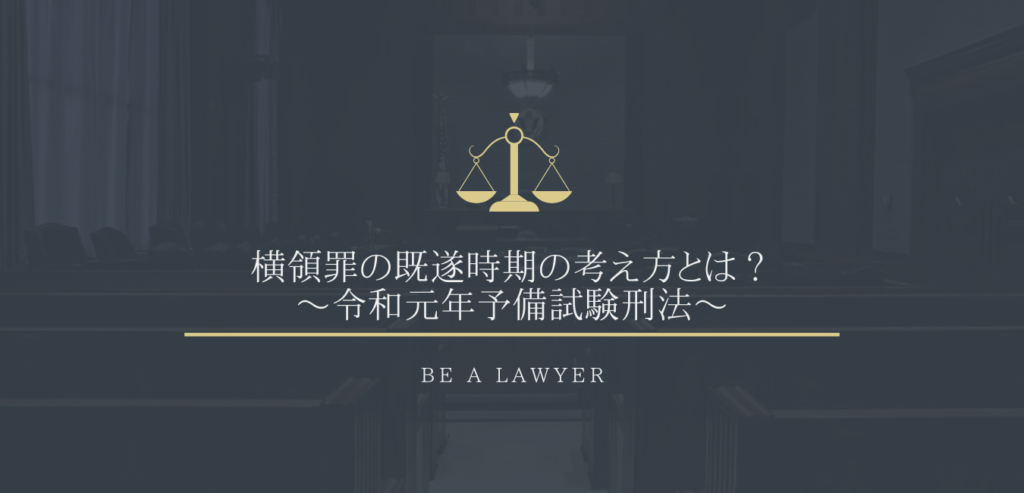
第1 はじめに
こんにちは、be a lawyer編集局です。
今回は、令和元年予備試験を題材として「横領罪の既遂時期」について実際の優秀答案と不合格答案の比較検討を通して、どのように答案を作成すれば安定して合格答案(上位答案になる可能性の高い答案)を書くことができるようになるかを解説していきたいと思います。
「横領罪には未遂犯処罰規定が存在しないため、既遂時期を検討する必要はないのでは?」
そのように考えている方は要注意です。横領罪について実行行為たる横領行為が認められても結果が発生していなければ「既遂」にはなりません。本記事では「横領罪の既遂時期」にフォーカスして横領罪について検討していきたいと思います。
第2 優秀答案と不合格答案の比較検討
【A答案】
1 甲が本件土地をAに売った行為について、業務上横領罪(刑法(以下法令各略)253条)が成立しないか。
⑴「業務」とは、人が社会的地位に基づき反復継続して行う事務のうち、委託信任関係に基づき物を占有管理するものをいう。本件甲は不動産業者であり、日常的に反復継続して、営業として不動産の管理を行う物であり「業務」を満たす。
⑵もっとも、甲は本件土地の登記済証や委託事項欄の記載がない白紙委任状等を預かっているだけであり「占有」しているといえるか問題となる。しかし、「占有」とは、他人の物を処分することが可能な支配が及んでいることを指すため、事実上の占有でなくとも法律上の占有があるといえれば、横領罪において「占有」していると認められる。本件において、甲は本件土地につき登記済証や委任事項欄の記載がない白紙委任状等を預かっており、真正な代理人であると誤信させ本件土地の処分権限を有するものとして、本件土地を処分することが可能な地位にいるといえる。したがって、甲は本件土地を「占有」しているといえる。
⑶ 次に、「横領」とは不法意思の一切の発現行為をいい、不法領得の意思とは自己の占有する物をその委託の趣旨に反して権限ないのに所有者でなければなしえないような行為をする意思をいう。
⑷ 本件において、甲はVから本件土地についての抵当権設定に関する代理権を与えられているに過ぎないにもかかわらず、甲は本件土地をAに対して2000万円で売却している。このことからすれば、甲の行為は委託の趣旨に反するといえる。また、土地の売却行為は本来所有者でなければできない行為である。以上からすれば、甲の行為は「横領」に該当する。意図的に行なっており、故意(38条1項本文)も認められる。
⑸ しかし、本件において未だ所有権移転登記はなされておらず、不動産の権利移転はなされているとはいえないのではないか。
横領罪における保護法益は委託者の信頼及び委託者の所有権の保護にある。そして、横領行為により契約がされればその時点で委託者の信頼は害されるといえる。また、契約の相手方はその時から履行を請求することができるようになる。そして、これにより委託者は表見代理などによって責任を追及されるような立場に立たされ、利益を侵害されるといえる。したがって、契約時点で保護法益に侵害が生じており既遂となる。
本件において甲はAとの間で某月5日に売買契約を行い本件土地の移転時期を16日としている。しかし、委託者たるVが同月13日に帰国し、甲の行動を知って14日に甲に本件土地の移転登記はなし得ない状態となっている。しかし、Aは本件売買契約により移転を請求することができるため、5日の売買契約時点で保護法益に侵害が生じたといえ、既遂となっている。
したがって甲のかかる行為は既遂である。また、甲の故意に欠けるところはない。
⑹ よって甲の行為に業務上横領罪が成立する。
【C答案】
第1 甲がV所有の本件土地の所有権移転登記に必要な書類をAに交付し、本件土地の所有権をAに移転させる旨合意した行為について業務上横領罪(253条)が成立しないか。本件では、背任罪(247条)の成立も問題となるも、横領罪と背任罪は、法条競合の関係にあるから、重い業務上横領罪の成否から検討する。
1 「業務」とは、社会的生活の地位に基づき、委託を受けて他人の財物を占有・保管することを反復・継続して行う行為をいう。横領罪における「占有」とは、委託信任関係に基づく事実上または法律上の支配をいい、登記を通じた法律上の支配も認められる。
2 本件では、甲は、不動産業者という社会生活上の地位に基づき、本件土地所有者のVが登記名義人である本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りて欲しいとの委託を受けている。そして、甲は、Vから同依頼に係る代理権を付与され、本件土地の登記済証や委任事項欄の記載がない白紙委任状等を預かったことで、登記を通じた法律上の支配により他人Vの財物である本件土地を業務上占有しているといえる。
3 「横領」とは、不法領得の意思を実施する一切の行為をいう。横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有が委任の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。
4 本件では、甲は、Vが登記名義人である本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りてほしいとの委託の任務に背いて、権限がないのにも関わらず、所有者Vでなければできないような本件土地をVに無断でAに売却するという処分をする意思を発現しているから「横領」したといえる。
5 甲は、銀行等から合計500万円の借金を負っており、その返済期限を徒過し、返済を迫られている状況にあったことから、本件土地の登記済証等をVから預かっていることやVが海外に在住していることを奇貨として、本件土地をVに無断で売却し、その売却代金のうち1500万円を借入金と称してVに渡し、残金を自己の借金の返済に充てようと考えていることから、業務上横領の認識・認容があるといえ、故意が認められる 。
6 よって、甲の上記行為に、業務上横領罪が成立する。
【比較検討】
優秀答案は法律上の占有の意義を正確に指摘した上で、登記済証及び白紙委任状を預かっていることからすれば、本件土地を自由に処分(売買)することができる地位にあることを指摘できています。また、規範→当てはめ→結論の法的三段論法を守っており、非常に読みやすい文章で書かれています。
優秀答案は横領罪の既遂時期について判例の理解をただ機械的に貼り付けるだけではなく、判例の事案と本問との異同を踏まえつつ、契約時点で横領の既遂時期を肯定することができています。このように判例の射程に言及できている点は高く評価されたと考えられます。
他方で、不合格答案は不動産を客体とした横領の既遂時期を意識することができておらず残念です。本件は二重譲渡事例ではないものの、不動産の横領の既遂時期を登記完了時点と解する判例が存在するからにはかかる判例の射程が及ぶか否かを検討する必要があり、答案に自らの考えを示す必要があるでしょう。
優秀答案と不合格答案の当てはめからもわかるとおり、横領罪の既遂時期については判例との異同を踏まえて論じられているか否かで答案の評価には差が生じているといえます。
第3 本問に関連する論点の考え方
1 横領罪の保護法益
横領罪は他人の占有を侵害する罪ではないため、窃盗罪等の移転罪とは異なり、占有が保護法益となるわけではありません。横領罪の保護法益は、財産犯であることに鑑み、第一次的には「所有権」、横領行為が他人の信頼を裏切るという背信的側面を有することに鑑み、第二次的には「委託信任関係」であると考えられます。
2 業務上横領罪(253条)の構成要件
⑴ 総論
| 【客観】 |
| ①「業務上」 |
| ②「自己の占有する」(委託信任関係に基づくことが必要) |
| ③「他人の物」 |
| ④「横領」 |
| 【主観】 |
| ⑤故意 |
| ⑥不法領得の意思 |
⑵ 意義
①「業務上」
「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続してなされる事務のうち、委託を受けて物を占有・保管することを内容とするものをいいます。
典型例は,質屋、倉庫業、運送業者、クリーニング業者などです。このほかにも、会社・団体等の金銭を保管する会社員・銀行員なども業務者にあたるとされています。
②「自己の占有する」
「自己の占有」は、他人からの委託信任に基づく占有であることが必要です。つまり,その要素としては(ⅰ)委託信任関係と(ⅱ)占有に分けることができます。ここでは,(ⅰ)委託信任関係については条文上に現れていないことから,忘れないように留意してください。
(ⅰ)委託信任関係について
横領罪の客体は、自己の占有する他人の物であるが、その占有は他人からの委託信任関係を原因とするものであることが必要です。なぜなら、何人の占有にも属していない他人の物や偶然に自己の占有に帰属した物に対する横領については、254条により占有離脱物横領罪が成立するとされていることから、252条の横領罪はそれ以外の場合、すなわち、他人からの委託信任関係に基づいて他人の物を占有するに至った場合を対象としていると解されるからです。つまり、252条との区別のために委託信任関係が必要であると整理することができます。
委託信任関係は、物の保管を内容とする契約、法定代理人や法人の機関としての地位、売買契約の売主としての地位、雇用契約、さらに、事務管理、慣習、条理ないし信義則からも生じ得るので検討の際にはこれらの関係性が認められないか探してみてください。
(ⅱ)占有について
横領罪の占有は、処分の濫用のおそれのある支配力を指し,具体的には物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
なぜなら、窃盗罪のような移転罪は他人の物に対する実力的支配を排除するところに本質があるため,事実用の支配が問題となるのに対し,横領罪は,他人の物を自由に処分しうる状態にある者がその物を領得するところに特徴があり、他人の物を自由に処分しうる状態にあるという点では事実上の支配も法律上の支配も何ら異ならないからです。
なお,法律上の支配が具体的に問題となる場面としては本問のような不動産の占有の場面が挙げられます。
※不動産の占有
判例上、不動産の占有者は所有権の登記名義人と考えるのが原則です(最判昭和30年12月26日刑集9巻14号3053頁)。
もっとも、登記名義人でなくとも、他人の不動産の登記済証や白紙委任状などの登記に必要な書類を預かっている者については、これらの書類を使って不動産を自由に処分することができる地位にあると評価できることから、法律上の支配を認めても問題ないと考えられています(福岡高判昭和53年4月24日判時905号123頁)。本問の甲もこれと同様に考えて、不動産の占有を肯定することになるでしょう。
③「他人の物」
「他人の物」とは、そのままですが行為者以外の自然人または法人の所有に属することです。
④「横領」
「横領」とは不法領得の意思を発現する一切の行為をいう。そして不法領得の意思とは「⑴他人の物の占有者が委託の任務に背いて、⑵その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」を指します。
当てはめの際に⑴と⑵のいずれの要素も認定することを忘れないようにすることが重要となります。受験生の答案を見ていると特に⑴の点の検討漏れが多く見受けられるため、委託信任関係の内容を認定し、行為者の行為が⑴を満たしていることを必ず認定するようにしましょう。
横領の検討過程をフレームワークにすると以下のようになります。
| STEP1:「横領」の定義を示す。 |
| ↓ |
| STEP2:契約などから委託の任務を認定する |
| ↓ |
| STEP3:上記任務に背いていることを認定する |
| ↓ |
| STEP4:当該処分が所有者でなければできないことを認定する |
| ↓ (他人の物を自分の物であるかのように使用していることの認定) |
| ↓ |
| STEP5:「よって,○○時点で不法領得の意思が発現した」と既遂時期を示す(後述3のとおり) |
| ↓ |
| STEP6:「横領」にあたることの結論を示す |
⑤ 故意
故意とは、客観的構成要件事実の認識・認容をいいます。本問では特に問題とならないのでさらっと検討すれば十分です。
⑥ 不法領得の意思
横領罪にいう不法領得の意思とは、前記したとおり他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのにその物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思をいい、横領罪の場合には実行行為である横領の当てはめの中で不法領得の意思の有無を検討することになるため、主観的構成要件の中で再度検討する必要はありません。
3 「横領」の既遂時期
⑴ 横領の既遂時期とはなにか
上記したように、「横領」とは不法領得の意思を発現する一切の行為をいい、不法領得の意思とは他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのにその物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
そして、横領罪の保護法益は委託信任関係及び所有権であるから、横領罪が成立するためには、所有権侵害の結果発生が必要です。
つまり、横領行為が認められたとしても直ちに横領既遂罪が成立するわけではないという点に注意する必要がある点に留意する必要があります(横領があっても所有権侵害結果が生じていない場合には、横領未遂罪、つまり不可罰となる点に注意してください。これは殺人罪において殺人罪の実行行為があったとしても死亡結果が生じていなければ殺人未遂罪となることと同様に考えてもらえればイメージしやすいと思います)。
以上からすれば、横領行為が認められ、かつ、所有権侵害結果が生じることが認定できて初めて横領「既遂」罪、すなわち横領罪が成立すると考えることができます。
⑵ 「横領」行為と結果の発生
上記したように、「横領」行為があっても横領結果(=所有権侵害)が発生しない限り横領罪は未遂であり、横領未遂罪は存在しないことから不可罰となります。横領罪は領得罪であるから、横領行為によって他人の物を不法に領得し、所有権を侵害したという結果発生が必要なのである。これは、特に本問のような不動産の二重譲渡事例で問題となります。
判例・学説は、不動産の二重譲渡事例に関し、横領の既遂時期を所有権移転登記完了時点としています(西田典之『刑法各論[第6版]』等)。これは、民法177条が不動産の物権変動を不動産登記の移転時期に連動させており、単に売買契約を締結した時点では所有権移転が不完全なものにとどまるという考えに基づいていると考えられます。
不動産の二重譲渡事例においては、上記の考え方に基づき基本的には不動産移転登記の移転時期が既遂時期となると考えていただいて問題ないと考えられます。
⑶ 本問の考え方
ア 横領行為の認定
本件で、Vが甲に与えた権限は、本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りて欲しいというものであり、本件土地の売買契約を締結する権限は与えていないため、甲がVに無断で本件土地の売買契約を締結することは委託の任務に背いているといえます。
また、甲がAとの間で、本件土地を2000万円でAに売却する旨の合意をしたことは委託の任務に背いてその物について権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思の発現行為ということができます。
以上からすれば、甲の行為は、「横領」行為に該当することになります。
イ 所有権侵害「結果」の認定
不動産の二重譲渡において過去の裁判例では、第一譲渡後未だ登記を有していた売主が第二譲渡人と売買契約をした時点では横領罪は既遂とはならず、第二譲受人に対して登記を移転した時点で既遂となるとしているところ(福岡高判昭和47年11月22日判タ289号292頁)、同判例の射程は本件に及ぶか問題となります。
この点、不動産の二重譲渡の場合には売主たる所有者は、不動産を売却する権限を有しており、第一譲受人と第二譲受人のいずれが登記を取得するかは、自由競争の問題であるから、登記時点において領得行為を認めるべきであるという考え方に基づいていることは前記したとおりです。これは民法177条の適用を前提としたものであると考えられます。
これに対して、本件のようにそもそも不動産売却の権限がない者が売却する場合には、当事者間の問題であって、民法177条の適用が問題となる場面ではありません。そうすると、民法176条の意思主義に従い、売却行為自体が不法領得の意思の発現そのものであり、かかる時点で所有権侵害があったと評価することもできるのではないかと考えることができます(判例の射程を否定した場合の整理)。
以上からすれば、甲の売却行為によって所有権侵害「結果」を発生させたといえ、横領は既遂に至っていると評価することができるでしょう。
(※なお、判例の射程を肯定するとすれば、売買契約締結により横領行為自体は認められるものの、所有権移転登記前の時点では所有権侵害結果が発生していないと評価されることになり、(横領未遂=不可罰となる結果)横領罪の成立は否定されることになるでしょう。結論はいずれでも構いませんが、判例の事案とは異なる点を踏まえつつ、自説を展開する必要がある点に留意してください。)。

be a lawyer公式LINEでは受験生向けに有益な情報を発信中!以下より友だち追加してみてください!


