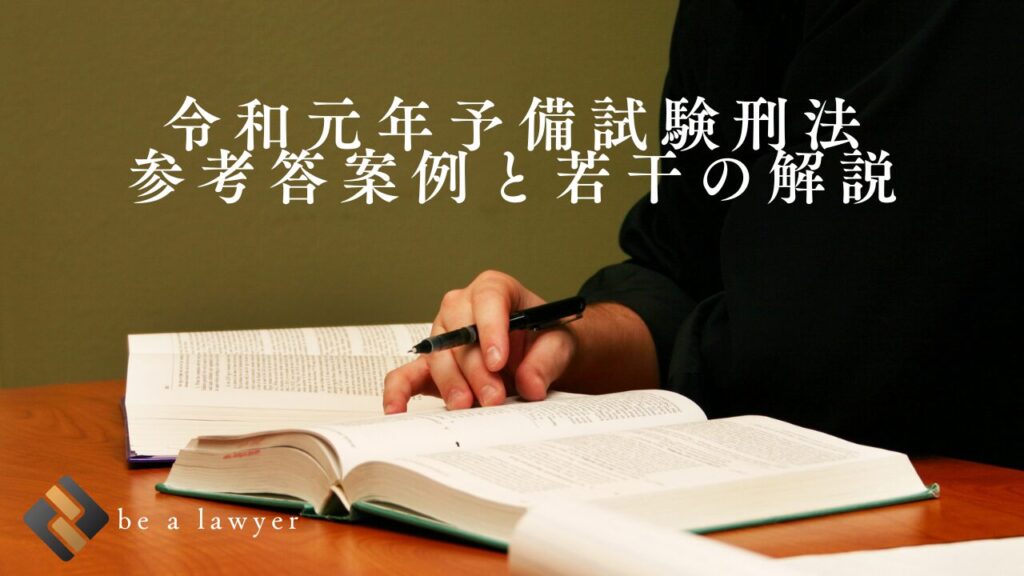
第1 はじめに
出題趣旨によれば、本問で論ずべき論点は大きく分けると、①私文書偽造罪、②(業務上)横領罪、③遅すぎた結果の発生、④抽象的事実の錯誤、である。
一つ一つの論点の難易度は高くはないが、70分という限られた時間の中で解答しなければならないことを考えると、整理して論じる力も要求され難易度の高い問題といえる。
司法試験・予備試験個別指導専門塾「be a lawyer」では、令和予備試験刑法をAランクに位置付けており、本問は過去問の中でも重要度の高い問題であることから、優先的に起案してもらいたい。
第2 論点解説
1 業務上横領罪
⑴ 構成要件
業務上横領罪の構成要件は、①他人の物、②業務上、③自己の占有、④横領、⑤不法領得の意思、⑥故意である。
⑵ 横領の認定方法
ア 「横領」の意義と認定における注意点
「横領」とは不法領得の意思を発現する一切の行為をいい、不法領得の意思とは他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのにその物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思をいう。
このように、「横領」行為が認められるためには、①委託の趣旨に反すること、②不法領得の意思(所有者でなければできないような処分をする意思)を発現させること、が必要である。したがって、受験生は、この点に意識して当てはめなければならない。いずれかが欠けている答案は当てはめとして不十分であることを意識して欲しい。
なお、横領罪は「横領」行為という客観的構成要件の検討の中で、主観的構成要件の一つである不法領得の意思を認定するという点に特殊性がある。
また、横領罪の保護法益は委託信任関係及び所有権であるから、横領罪が成立するためには、所有権侵害の結果発生が必要である。つまり、横領行為が認められたとしても直ちに横領既遂罪が成立するわけではないという点に注意する必要がある(横領があっても所有権侵害結果が生じていない場合には、横領未遂罪、つまり不可罰となる点に注意)。
以上からすれば、横領行為が認められ、かつ、所有権侵害結果が生じることが認定できて初めて横領既遂罪が成立するのである。
イ 論点1:「横領」行為と結果発生
上記したように、横領」行為があっても横領結果(=所有権侵害)が発生しない限り横領罪は未遂であり、横領未遂罪は存在しないことから不可罰である。横領罪は領得罪であるから、横領行為によって他人の物を不法に領得し、所有権を侵害したという結果発生が必要なのである。これは、特に不動産の二重譲渡事例で問題となる。
判例・学説は、不動産の二重譲渡事例に関し、横領の既遂時期を所有権移転登記完了時点としている(西田典之『刑法各論[第8版]』等)。これは、民法177条が不動産の物権変動を不動産登記の移転時期に連動させており、単に売買契約を締結した時点では所有権移転が不完全なものにとどまるという考えに基づいている。
ウ 本問の考え方
(ア)横領行為の認定
本件で、Vが甲に与えた権限は、本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りて欲しいというものであり、本件土地の売買契約を締結する権限は与えていないため、甲がVに無断で本件土地の売買契約を締結することは委託の任務に背いているといえる。
また、甲がAとの間で、本件土地を2000万円でAに売却する旨の合意をしたことは委託の任務に背いてその物について権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思の発現行為ということができ、「横領」に当たる。
(イ)所有権侵害「結果」の認定
もっとも、不動産の二重譲渡の判例では、第一譲渡後未だ登記を有していた売主が第二譲渡人と売買契約をした時点では横領罪は既遂とはならず、第二譲受人に対して登記を移転した時点で既遂となるとしているところ、同判例の射程は本件に及ぶか問題となる。
この点、不動産の二重譲渡の場合には売主たる所有者は、不動産を売却する権限を有しており、第一譲受人と第二譲受人のいずれが登記を取得するかは、自由競争の問題であるから、登記時点において領得行為を認めるべきである。これに対して、本件のようにそもそも不動産売却の権限がない者が売却する場合には、売却行為自体が不法領得の意思の発現そのものであって、かかる時点で所有権侵害があったと評価することができる(事案の違いを指摘して判例の射程を否定)。
よって、甲の行為は所有権侵害結果を発生させたといえ、横領行為は既遂に至っている。
(※なお、判例の射程を肯定するとすれば、売買契約締結により横領行為自体は認められるものの、所有権移転登記前の時点では所有権侵害結果が発生していないと評価されることになり、(横領未遂=不可罰となる結果)横領罪の成立は否定されることになる。)
-1-1024x536.png)
2 私文書偽造罪
⑴ 構成要件
有印私文書偽造罪の構成要件は、①権利義務に関する文書or事実証明に関する文書、②偽造、③他人の印章若しくは署名を使用したこと、④行使の目的、⑤故意である。
有印私文書行使罪の構成要件は、⑥偽造有印私文書、⑦行使することである。
⑵ 「偽造」の意義
「偽造」とは、作成権限がないのに他人名義の文書を作成すること(定義A)、または名義人と作成者の人格の同一性を偽ること(定義B)をいう。近年の最高裁の立場は、定義Bであると考えられることからすれば、受験生としては定義Bを使うのが無難である。
名義人とは文書から看取される意思の主体をいい、作成者とは文書作成に関する意思の主体をいう。
⑶ 論点2:代理名義の冒用
ア 総論
代理名義の冒用とは、Aを代理とする権限を持たないXが「A代理人X」として文書を作成した場合のように、代理権を持たない者が他人の代理人であるかのような肩書を付して文書を作成する場合である。
上記の定義からすると、作成者が代理人と表記された「X」であることについては問題とならない。問題は名義人を誰と考えるかである。この点に関しては、学説は①「A(本人)」とする立場、②「A代理人X」とする立場、③「X」とする立場、の3つに分かれている。①②の立場に立った場合には、名義人と作成者が異なることになるため、名義人と作成者の人格の同一性を偽ったことになり、私文書偽造罪が成立することになる。②の立場では、名義人は「Aの代理人であるX」というおよそ存在しない人物として文書を作成したという意味で私文書偽造罪が成立するのである。これに対して、③によれば、代理人の資格・肩書という文書の内容に虚偽があるにすぎないので、私文書偽造罪は成立しないことになる。
イ 本問における考え方
本問で②の立場に立って考えてみよう。甲は本件土地の抵当権設定の限度で代理権を有することにはなるが、甲は本件土地の売買権限については有さない。つまり、甲は「本件土地の売買契約締結の代理権を有しない甲」なのである。それにもかかわらず、甲が作成した売買契約書から看取されるのは、本件土地の売買契約締結の代理権を有する甲」であるから、その意味で名義人と作成者の人格の同一性を偽ったと評価できるため、私文書偽造罪が成立するのである(最決昭和45年9月4日刑集24巻10号1319頁も同旨)。
3 論点3:遅すぎた構成要件の実現
⑴ 総論
遅すぎた構成要件の実現とは、まさに本問の甲のように、第1行為時点で死亡結果が生じていたと思っていたのに、現実には第1行為の時点では死亡結果が生じておらず、第2行為を行った場合に、行為者にいかなる犯罪が成立するのかという問題である。このように、第1行為と第2行為という二つの行為が登場する以上、両行為を一体のものとして論じるのか、両行為は別個のものとして論じるのかを考える必要がある。
⑵ 行為の一体性
行為とは、主観と客観の統合体である。そのため、第1行為と第2行為が一体といえるかどうかについては、二つの行為の主観面と客観面の両方が関連しているかという点を検討する必要がある。
そのメルクマールとしては、主に3つが考えられる。まずは、それぞれの行為が同一の法益に対して向けられたものであるかどうかという点である(法益侵害の同一性)。例えば、住居侵入罪と窃盗罪を連続して行ったとしても、保護法益が異なることから行為の一体性は否定されるであろう。
次に、それぞれの行為が時間的・場所的に接着したものでなければならない(時間的・場所的接着性)。例えば、5月1日に行われたV方に対する窃盗と6月1日に行われたV方に対する窃盗は例え法益侵害の対象が同一であっても、行為の一体性は否定されるであろう。
以上2点は行為の客観面に関するものである。最後は主観面からであるが、それぞれの行為が連続した意思に基づいているかどうかである(意思の連続性)。例えば、正当防衛の意思で反撃行為を行った者が急迫不正の侵害がなくなった後もそのことを認識した上で傷害行為を行った場合には、行為の一体性は否定されるであろう。
⑶ 抽象的事実の錯誤
ア 総論
行為者の主観と現に実現された犯罪が異なるといういわゆる抽象的事実の錯誤の問題である。ロー生レベルであれば、知らない人はいない論点であり、解説は不要と思われる方もいるかもしれない。しかし、ほとんどの受験生が抽象的事実の錯誤について誤解しているため、あえてレジュメに掲載している。
イ 処理方法
① 重い犯罪の故意で軽い犯罪を実現した場合
→軽い犯罪の故意が認められるかどうかという故意責任の問題。故意責任の本質は〜で始まる論パで処理してもらえばO K。
② 軽い犯罪の故意で重い犯罪を実現した場合
→軽い犯罪の故意が認められることは明らかであるため、故意責任の問題ではない(要注意)。ここでの問題は、客観的には存在しないはずの軽い構成要件が客観的に存在したものとして扱うことができるかという問題である。このような扱いは、罪刑法定主義に反しないのかという疑問が生じるが、刑法38条2項がそれを認めていると考えるのである。つまり、同項の「重い罪によって処断することはできない」という文言を「思い罪によって処断することはできない(が軽い罪によっては処断することができる)」と解釈するのである。ただ、当然重い罪と軽い罪とは構成要件が重なるものでなければならないので、法定的符合説の立場から両構成要件が重なっていることを論証する必要がある。
⑷ 本問における考え方
本件で甲はVの首を背後からロープを用いて力一杯絞めた上(第1行為)、同人を失神させ、同人が失神している状態で同人を海に落として同人を溺死させている(第2行為)。
上記のメルクマールに沿って考えてみると、まず法益侵害が同一のものに向けられているかについては、第1行為がVの生命身体という利益に向けられていることは明らかである。次に、客観的にはVは第1行為の時点で死亡していないから、第2行為は客観的に見ればVの生命身体という利益に向けられたものであると評価することができる。したがって、第1行為と第2行為はVの生命身体という同一の利益に向けられたものであるということができる(法益侵害の同一性)。
次に、第1行為と第2行為の時間的・場所的接着性について見てみると、第1行為を行った場所から1キロメートル移動した港において、第1行為から約30分後に第2行為が行われていることからすれば、第1行為と第2行為の時間的・場所的接着性も認められることになるだろう(時間的場所的接着性)。
最後に意思の連続性であるが、第1行為の時点では甲はVを殺害する意図を有しており殺意が認められる。これが第2行為の時点まで継続しているかをみるに、甲はVの様子を見て第1行為により死亡したと思っていることから、甲の主観としては第2行為は死体遺棄罪の故意である。そうすると、第1行為時点で有していた殺意が第2行為時点まで継続しているとは言い難いため、意思の連続性が否定されることになろう(意思の連続性)。
以上から、第1行為と第2行為は別個のものであるから、それぞれ分けて構成要件該当性を検討することになる。
あとは、第1行為について殺人罪の成否、第2行為について死体遺棄罪あるいは過失致死罪の成否を検討してことになる。第1行為については、行為と死亡結果の因果関係、因果関係の錯誤が主な論点となる。第2行為については、まず故意犯である死体遺棄罪の成否を検討することになるが、問題は客観的に存在しないはずの死体遺棄罪が実現されたものとみなしてよいかという点である。この点については、上記に述べたように刑法38条2項の解釈の問題として処理することになろう。
-2.jpg)
【令和元年予備試験刑法 参考答案例】
第1 甲が、Aに対し、本件土地の売却を申し向けた行為に業務上横領罪(刑法253条)が成立するか。
1 本件土地は、Vが所有する物であるため「他人の物」に当たる。
2⑴ 横領罪は濫用の恐れのある支配力を処罰するものであるから、横領罪にいう「占有」とは事実上の支配のみならず法律上の支配を含み、本罪にいう「占有」は委託信任関係に基づくことが必要である。
⑵ 本件で、甲は、本件土地の所有者Vから、本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りて欲しいとの依頼を受けて、かかる依頼を承諾した結果Vから同依頼に係る代理権を付与され、本件土地の登記済証や委託事項欄の記載のない白紙委任状等を預かっている。そして、このような書類を所持していれば、甲は本件土地を売却等の処分をすることができるから、本件土地を法律上支配していると評価できる。また、甲は本件土地の抵当権を設定するという代理権を付与されて本件土地を法律上支配しているから、上記占有は委託信任関係に基づいているといえる。
⑶ よって、「自己の占有する」に当たる。
3 253条における「業務上」とは社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務であって、金銭等を委託を受けて保管することを内容とする職務をいうところ、本件で甲は不動産業者としてVから委託を受けて、本件土地の登記済証や白紙委任状を預かっているから、上記の占有は「業務上」に当たる。
4⑴ 「横領」とは不法領得の意思を発現する行為、すなわち、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき処分権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を発現する一切の行為をいう。
⑵ 本件で、Vが甲に与えた権限は、本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りて欲しいというものであるため、甲がAとの間で、本件土地を2000万円でAに売却する旨の合意をしたことは委託の任務に背いてその物について権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思の発現行為ということができ、「横領」に当たる。
⑶ もっとも、不動産の二重譲渡の判例では、第一譲渡後未だ登記を有していた売主が第二譲渡人と売買契約をした時点では横領罪は既遂とはならず、第二譲受人に対して登記を移転した時点で既遂となるとしているところ、同判例の射程は本件に及ぶか。
この点、不動産の二重譲渡の場合には売主たる所有者は、不動産を売却する権限を有しており、第一譲受人と第二譲受人のいずれが登記を取得するかは、自由競争の問題であるから、登記時点において領得行為を認めるべきである。
これに対して、本件のようにそもそも不動産売却の権限がない者が売却する場合には、民法177条の適用が想定されず、売却行為自体が不法領得の意思の発現そのものであって(民法176条参照)、かかる時点で確定的な所有権侵害があったと評価することができる。
よって、甲の行為は所有権侵害を生じさせたものであり横領行為は既遂に至っている。
5 以上より、甲の行為に業務上横領罪が成立する。
第2 甲が本件土地の売買契約書2部の売主欄にいずれも「V代理人甲」と署名したことは、有印私文書偽造罪及び同行使罪(159条1項前段、161条1項)が成立するか。
⑴ 「権利、義務・・・に関する文書」とは、私法上・公法上の権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする文書をいい、売買契約書は売買という法律効果を発生させる文書であるから、「権利、義務・・・に関する文書」である。
⑵「偽造」とは名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいう。名義人とは文書から看取される意思の主体をいい、作成者とは文書作成に関する意思の主体をいう。
本件で、甲は本件土地の抵当権設定の代理権を有しているが、売買の代理権は有しないのに、本件土地の売買契約書の売主欄に「V代理人甲」と署名している。そして、売買契約書という文書の性質上、契約書から看取する意思の主体は本件土地に関して売買契約締結の代理権を有している甲であるのに対して、本件売買契約書の作成者は本件土地の売買契約締結の代理権を有しない甲である。
したがって、甲の行為は人格の同一性を偽っているといえ、「偽造」に当たる。
⑵ 甲は本件売買契約書に「甲」と署名しているが、これは「本件土地の売買契約締結の代理権を有する甲」の署名と評価できるから、「他人の・・・署名を使用して」いる。
⑶ 「行使」とは偽造文書を真正な文書として相手方がその内容を認識可能な状態に置くことをいうところ、甲は本件売買契約書をAとの売買契約書に際して交付する目的を有しているから、「行使の目的」がある。以上より、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
⑷ また、甲は現に本件売買契約書をAに交付し、その内容を認識可能な状態に置いたから「行使
」したといえ、同行使罪が成立する。
第3 甲がVの首を締めて(第1行為)、その後海中に捨ててVを溺死させた行為(第2行為)について殺人罪(199条)ないし過失致死罪(210条)が成立するか。
1⑴ 行為は主観と客観の統合体であるから、行為の一体性は行為の時間的・場所的接着性と意思の連続性から判断すべきである。
⑵ 本件では、甲は首を締めてVを失神させた後、Vを失神させてから約10分という近接した時間にVを失神させた場所から約1キロメートルという近接した場所において、Vを海に落としているから行為の時間的場所的接着性は否定しがたい。他方、甲は第1行為の時点ではVを殺害する意思を有していが、第2行為の時点ではVの死体を海に遺棄するという意思しか有していない。そのため、意思の連続性を欠く。
以上より、第1行為と第2行為は一体のものとはいえず、別個に検討すべきである。
2 第1行為について殺人罪が成立するか。
⑴ 殺人の実行行為とは人を死に至らしめる現実的危険性を有する行為をいい、甲がVの背後から同人の首をロープで力一杯しめる行為は、Vが背後から首を絞められれば、同人に呼吸困難等を生じさせて窒息死させる現実的な危険性があるといえるから、殺人の実行行為に当たる。
⑵ Vは溺死している。
⑶ア 因果関係は当該行為の危険が結果として現実化したか否かで判断する。具体的には当該行為の危険性、介在事情の結果への寄与度、介在事情の異常性から判断すべきである。
イ 甲がVの背後から力一杯ロープで同人の首を締める行為は呼吸困難による窒息死を生じさせる現実的な危険性を有する行為である。そして、甲が失神したVを夜の海に落とす行為はVを溺死させる危険性を有するものであり、Vの死因が溺死であることからも結果への寄与度は大きいと言わざるを得ない。しかし、殺人犯が死体を遺棄することは通常あり得るものであって、介在事情は甲がVの首を絞めた行為に誘発されたものに過ぎないことからすれば、介在事情の異常性は小さい。以上より、甲の第1行為の危険がVの死亡結果として現実化したといえる。
ウ 以上から、第1行為とVの死亡結果に因果関係がある。
⑷ 故意責任の本質は反規範的人格態度に対する道義的非難であるところ、具体的な因果経過に錯誤がある場合であっても、危険の現実化の範囲内で一致していれば、行為者は規範に直面しているといえるから故意は阻却されない。
本件では、甲はVを窒息死させようとして実際は同人を溺死させており、甲の主観と現実に発生した客観は危険の現実化の範囲内で一致しているから、甲の故意は認められる。
⑸ 以上より、甲に殺人罪が成立する。
2 第2行為について死体遺棄罪の成否が問題となるも、殺人罪と死体遺棄罪は保護法益が異なるから、甲には死体遺棄罪の故意がなく同罪は成立しない。他方、第2行為は、甲が失神した人間を海に落としてはならないという注意義務に反してVを海に落とし死亡させたものと評価できるから、「過失」によって「人を死亡させた」といえ、過失致死罪が成立する。
第4 以上より甲に①業務上横領罪、②有印私文書偽造罪、③同行使罪、④殺人罪、⑤過失致死罪が成立し、②③は手段結果の関係にあるので牽連犯となり(⑥)、④⑤は法益侵害の対象が一つであるから包括一罪となり(⑦)、①⑥⑦は別個の行為から別の法益侵害したから併合罪(45条前段)となる。 以上
-1-1024x536.png)
-2.jpg)

